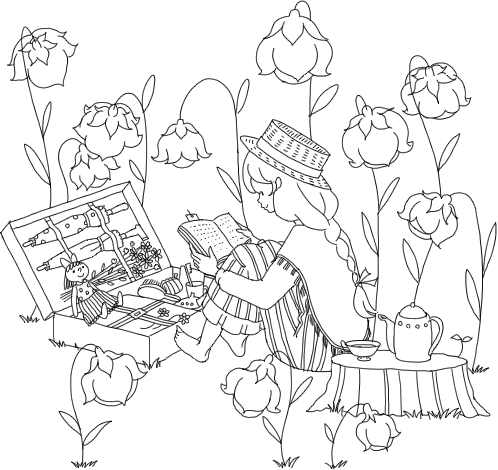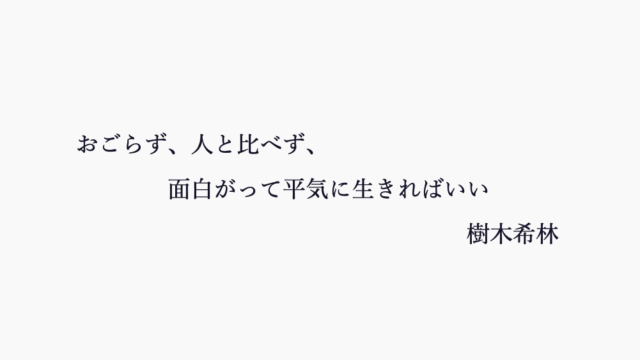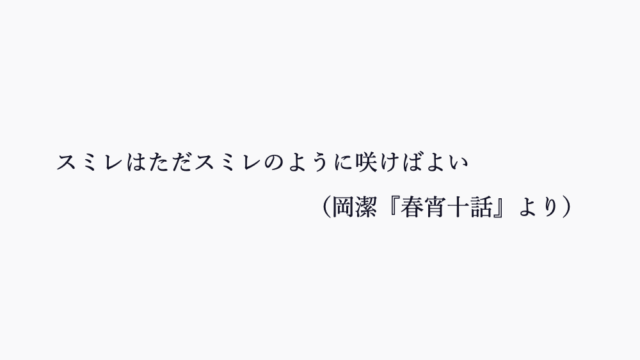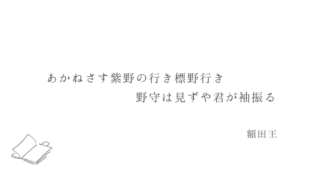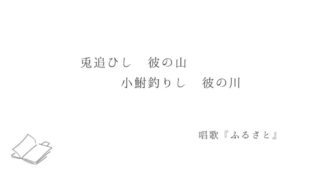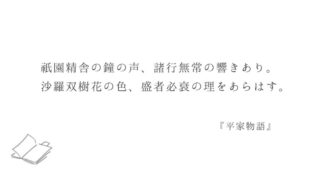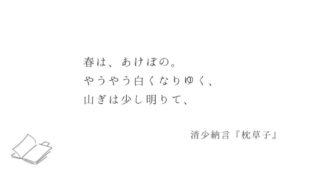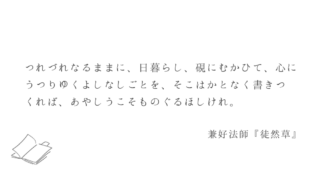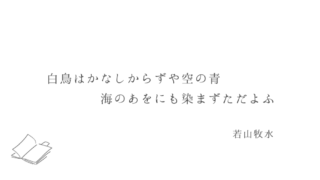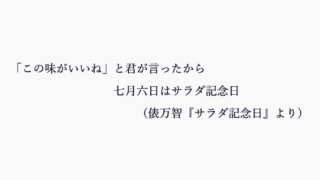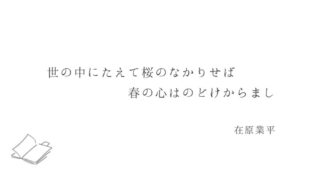宮沢賢治『よだかの星』の名言
外見が醜く、また自分が生き物の命を奪ってまで生きていることが耐え難く、絶望する鳥のよだかを描いた、宮沢賢治の童話『よだかの星』。
この童話のなかで特に心に響く名言が、「私のようなみにくいからだでも灼けるときには小さなひかりを出すでしょう」というよだかの台詞です。
これは、自分の存在を否定したいよだかが、物語の終盤、お日さまに、「あなたのもとに連れていってほしい」と懇願する際に言った言葉です。
よだかは、醜い鳥で、顔は味噌をつけたようにまだら、くちばしは平たく耳まで裂けています。
それゆえに他の鳥たちからは悪口を言われて嫌われ、また、強くて偉そうな鷹からは「名前を変えろ、さもないとつかみ殺してしまうぞ」と脅されるなど、なんとも可哀想な境遇です。
さらに、虫たちの命を奪いながら生きていることへの罪悪感にも苦しむよだかは、もうこのまま虫も食べずに飢えて死んでしまおうか、それともいっそ遠い遠い空の向こうに行ってしまおう、などと考えます。
そして、お日さまに、こんな風にお願いするのです。
お日さん、お日さん。どうぞ私をあなたの所へ連れてって下さい。灼けて死んでもかまいません。私のようなみにくいからだでも灼けるときには小さなひかりを出すでしょう。どうか私を連れてって下さい。
出典 : 宮沢賢治『よだかの星』
誰からも好かれず、他者の命を奪ってまで生きている、そういった自身への否定の象徴として語られる、“みにくいからだ”。
でも、お日さまに向かって呼びかけるその言葉からは、そんな“みにくいからだ”であっても、飛翔し、燃えることによって、「小さなひかり」を出せる──そのときくらいは、光ることができるはず──という祈りにも似た想いが伺えます。
この「小さなひかり」は、自己犠牲によって他の誰かを照らす光かもしれませんし、あるいは、自らの生を最期に輝かせる光を意味しているのかもしれません。
結局、よだかは、お日さまにお願いしても、星々にお願いしても、連れていってもらうことはできず、空高くどこまでも飛んでいき、そして、最期を迎えたのち、青白い美しい光の星となります。
この最後のシーンもまた、とても美しい映像的な表現で締めくくられています。
もうよだかは落ちているのか、のぼっているのか、さかさになっているのか、上を向いているのかも、わかりませんでした。ただこころもちはやすらかに、その血のついた大きなくちばしは、横にまがっては居ましたが、たしかに少しわらって居りました。
それからしばらくたってよだかははっきりまなこをひらきました。そして自分のからだがいま燐の火のような青い美しい光になって、しずかに燃えているのを見ました。
すぐとなりは、カシオピア座でした。天の川の青じろいひかりが、すぐうしろになっていました。
そしてよだかの星は燃えつづけました。いつまでもいつまでも燃えつづけました。
今でもまだ燃えています。
出典 : 宮沢賢治『よだかの星』
みんなからも嫌われ、強いものにいじめられ、生きていることの罪悪感にもさいなまれ、太陽や星々のもとにも受けいれてもらえずに、どこまでも空高く飛翔する。
そのことによって自ら、いつまでも燃え続けるよだかの星となる。
悲しいお話ではありますが、しかし同時に、悲劇では終わらないかすかな光も届けてくれるような物語です。
ちなみに、二人組バンドのヨルシカの『靴の花火』という初期の曲では、歌詞の途中、「僕の食べた物 全てがきっと生への対価だ 今更な僕はヨダカにさえもなれやしない」という一節が入り、ミュージックビデオでも、『よだかの星』の文章が登場します(参照 : ヨルシカ『靴の花火』MV)。