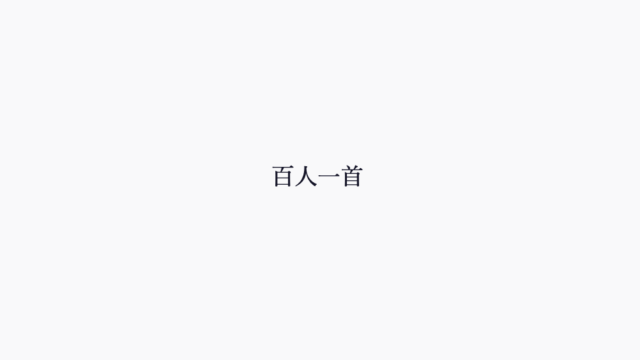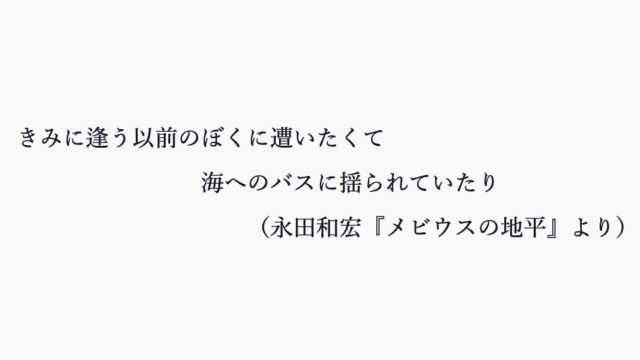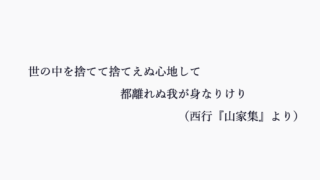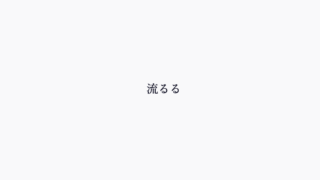道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ 西行
〈原文〉
道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ
〈現代語訳〉
道のほとりに清水の流れている柳の木陰がある。ほんの少し(休もう)と思って立ち寄ったら、(涼しくて)つい長居をしてしまったよ。
概要
作者の西行は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての日本の武士であり、のちに僧侶となる歌人です。西行法師として知られています。
武士だった頃の名前は、佐藤義清と言い、西行とは、歌をつくる際に使った号です。
生まれた年は、元永元年(1118年)で、文治6年(1190年)に、73歳で亡くなります。
 西行像(MOA美術館蔵)
西行像(MOA美術館蔵)
西行は、もともと鳥羽上皇の御所を守る優秀な北面の武士でしたが、1140年、まだ若くして出家し、数年ほど京都の鞍馬、東山、嵯峨などで過ごしたのち、一生を通じて全国各地を仏道修行の旅に出ます。
西行が出家した動機としては、親しい友人の死去や、高貴な女性への失恋などの説があります。
仏道修行の旅をしながら、西行は数多くの和歌をつくり、藤原俊成と並ぶ、平安時代後期を代表する歌人となります。
西行の和歌は、約2300首が伝わっています。
この「道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」という和歌は、鎌倉時代初期の勅撰和歌集『新古今和歌集』に収録されている歌です。
以下、和歌に出てくる語句の意味や現代語訳などを簡単に解説したいと思います。
冒頭の「道の辺」とは、「道のほとり」や「道ばた」を意味します。
続く「清水流るる」とは、「きれいな小川の流れる」という意味で、「流るる」は、「流る」の連体形です。
次に、その小川の流れる「柳陰」とあります。「柳陰」とは、柳の木陰を指すことから、ある夏、道のほとりに小川が流れ、風も心地よい柳の木陰がある、という情景が浮かびます。
この木陰で、「しばしとてこそ」、すなわち、「しばらくのあいだだけ(休もう)と思って」という意味の言葉が続きます。
最後の「立ちどまりつれ」は、「こそ〜つれ」が係り結びとなり、「(少しと思っていたのに)つい長居をしてしまったよ」という心情を表現しています。
さて、この西行の「道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」という和歌の現代語訳を言えば、「道のほとりに、清水の流れている柳の木陰がある。少しばかり(休んでいこう)と思っていたが、(あまりに涼しいので)つい長居をしてしまったよ。」という意味合いになります。
季節は夏、西行が東北を目指して旅する途中、木陰や川の水の涼しさやひとやすみしたときの心地よさが伝わってきます。
西行は、数多くの和歌を『新古今和歌集』に収録され、その数は94首と、『新古今和歌集』の歌人のなかでもっとも多い数となっています。
ちなみに、西行がこの和歌を詠んだとされる柳の場所として、栃木県那須の「遊行柳」が知られています。
遊行柳
のちに、西行を敬愛していた松尾芭蕉は、この遊行柳を訪れ、「田一枚 植ゑて立ち去る 柳かな(『おくのほそ道』)」と一句詠みます。
さらに、芭蕉を慕った俳人の与謝蕪村もまた、柳散清水涸石処々と漢詩調の句を詠んでいます。
平安末期の歌僧・西行は二十代と六十代の二度、みちのくへ旅したが、遊行柳で詠んだとされる歌が「道のべに清水流るる柳かげしばしとてこそ立ちどまりつれ」『新古今和歌集』に収められている。
江戸元禄期の俳聖・松尾芭蕉が『おくのほそ道』の途次にここで詠んだ句が「田一枚植ゑて立去る柳かな」『ほそ道』の地の文には、芦野の郡守戸部某(こほうなにがし)が「ぜひ見ていってほしい」と旅の前に折々話していたというくだりがある。
この郡守とは芭蕉の俳諧の門人だった芦野の領主・芦野資俊。句の「植ゑて立去」ったのは早乙女か、芭蕉か、はたまた柳の精かとさまざまに想像がふくらむ。
芭蕉の『おくのほそ道』には、この地に西行の「道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」で詠まれた柳があり、見てみたいと思っていたが、ようやく柳の下に立つことができた、ということが記してあります。
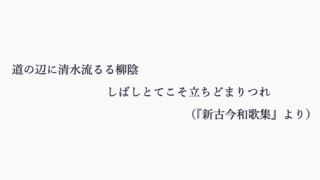
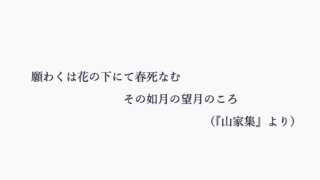
以上、西行の和歌「道の辺に清水流るる柳陰しばしとてこそ立ちどまりつれ」の意味でした。