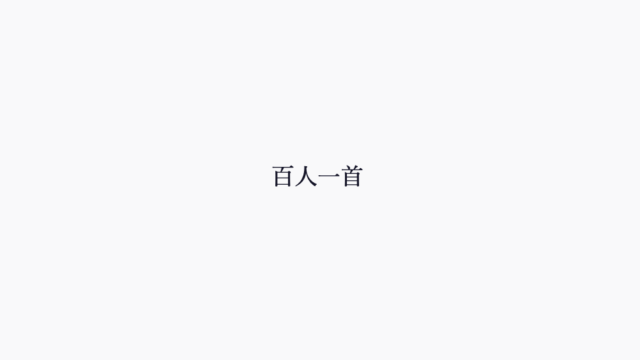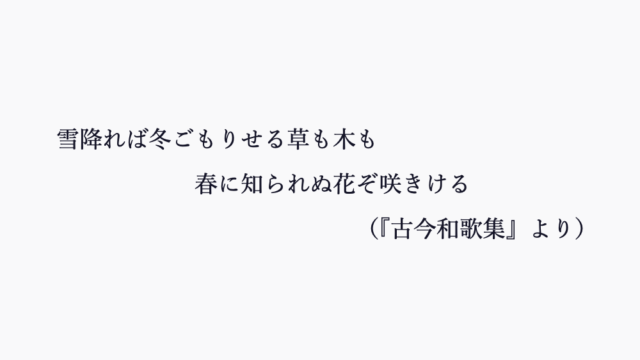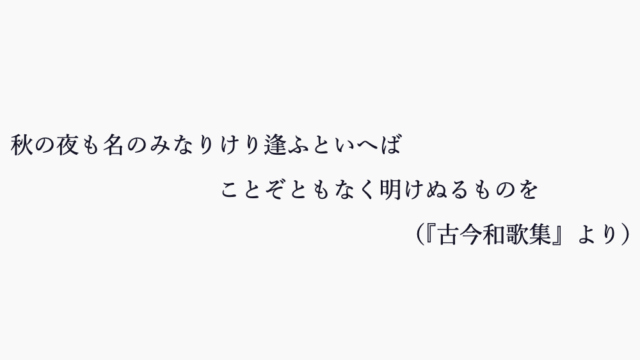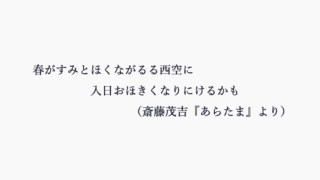世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし 在原業平
〈原文〉
世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし
〈現代語訳〉
もし世の中にはまったく桜がなかったなら、春を過ごす人の心はのどかだっただろうに。
概要と解説
作者の在原業平は、天長2年(825年)に生まれ、元慶4年(880年)に死没する、平安時代初期から前期の貴族、歌人です。
在原業平は、平城天皇の皇子阿保親王の五男であり、在原行平の弟になります。
また、六歌仙、三十六歌仙(他に、柿本人麻呂、山部赤人、大伴家持、小野小町など)の一人で、平安時代を代表する歌人として有名で、美男子としても知られています。
平安時代前期の勅撰和歌集『古今和歌集』では、約30首の和歌が選ばれ、『伊勢物語』では、主人公のモデルと考えられています。
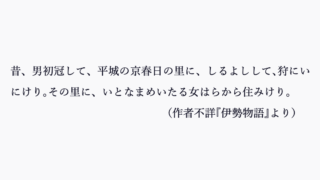
この「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」という業平の和歌は、渚の院という惟喬親王の別荘で開かれた、お花見の際に詠まれた作品であることが、『伊勢物語』に記され、『古今和歌集』にも収録されています。
現代語訳すれば、「もし世の中にまったく桜がなかったなら、桜の花が咲くのを待ち望んだり、散っていくことを悲しんだりすることもなく、春のひとの心はもっとのどかだっただろうに」といった意味になります。
作品の冒頭、「世の中に」のあとの「たえて」とは、「全く、全然」を意味し、「なかりせば」は、「もしなかったなら」を意味します。
この「せば…….まし」というのは、反実仮想の表現で、実際とは異なることを想像し、語る際に使われます。
たえて桜のなかりせば〜のどけからまし(全く桜がなかったなら、のどかだっただろうに)。
この「のどけから」とは、形容詞「のどけし(落ち着いている、ゆったり、のんびりしている)」の未然形です。
春というのは、冬が終わり、ぽかぽかと陽気に包まれ、風も心地よく、本来なら、のどかに過ごせる季節です。
しかし、人々は、桜が咲くのを待ち望んだり、桜の花びらが散っていくのを悲しみ、心は一向に落ち着きません。
もし桜さえなかったら、もっと春の心はのどかだったのに、という逆説的な表現で、それほど心をざわつかせる桜の、悩ましくも魅力的な様を歌っています。
この感覚は、現代でもとても分かりやすく共感しやすいのではないでしょうか。
桜の季節は、あっという間に過ぎ去り、また桜の散る光景は、儚くも美しいもので、人の心も、ざわざわとしながら、散りゆく様を眺めています。
ああ、もうこんなに美しくも儚い桜がなかったら、もっと穏やかだった春なのに、と思いながら、その悩ましくも素晴らしい花の魅力を歌っている、というわけです。
この桜に関する在原業平の歌、「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」を受け、詠んだ返歌として、『伊勢物語』では、作者の名前は不明ですが、お供のなかの一人の「散ればこそいとど桜はめでたけれ憂き世になにか久しかるべき」という歌が書かれています。
この返歌を現代語訳すれば、「桜は散るからこそいっそう素晴らしいのでしょう、この辛い世の中でいつまでも変わらずにいるものなど何があるでしょうか(いや、ありません)」という意味になります。
冒頭の「散ればこそ」に続く、「いとど」とは、「いっそう、ますます」という意味で、「めでたけれ」とは、「めでたし(素晴らしい、美しい)」の已然形です。
世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし(在原業平)
散ればこそいとど桜はめでたけれ憂き世になにか久しかるべき(詠み人知らず)
業平が、桜さえなければ、春の人の心はもっと穏やかだっただろうに、と歌えば、返歌で、桜は散るからこそいっそう素晴らしいのでしょう、この世にいつまでも変わらないものなどありません、と返します。
業平の和歌に、すでに悩ましくさせるほど美しくも儚く魅力的な桜、という意味合いは込められているでしょう。
そのため、返歌は、少し重複するような、分かっていることをあえて繰り返しているようにも思えますが、両者を合わせることで、より死生観として、この世の無常感まで広げられる、と解釈できるかもしれません。
以上、在原業平の和歌「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」の意味と現代語訳でした。