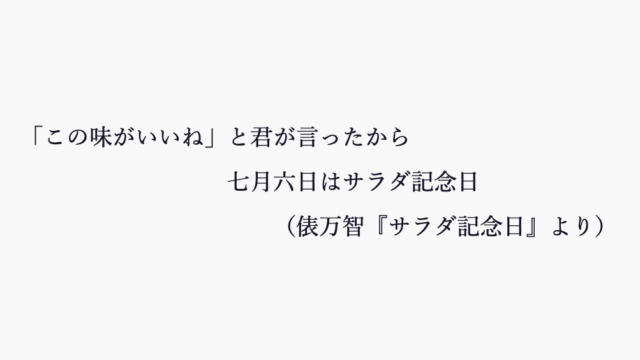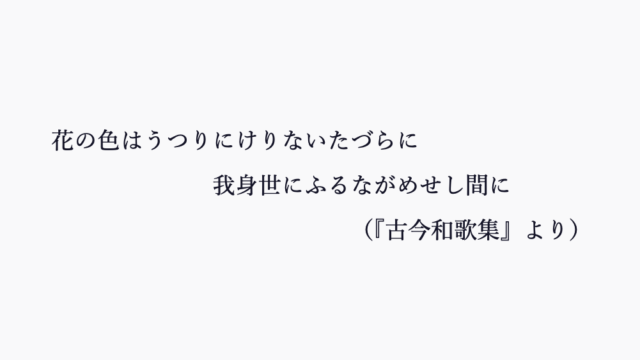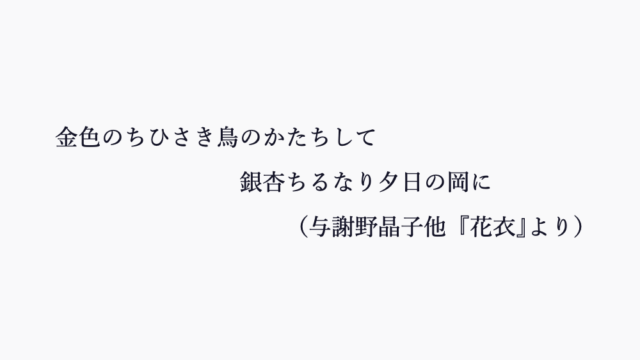春がすみとほくながるる西空に入日おほきくなりにけるかも〜意味と現代語訳〜
〈原文〉
春がすみとほくながるる西空に入日おほきくなりにけるかも
〈現代語訳〉
春霞が遠く流れている西の空に、今沈もうとしている太陽が大きくなっているよ
概要と解説
作者の斎藤茂吉は、1882年(明治15年)に山形県で生まれ、1953年(昭和28年)に亡くなる精神科医であり歌人です。
 斎藤茂吉
斎藤茂吉
家は経済的に余裕がなく、画家か、寺への弟子入りか、という考えがあったものの、同郷で東京に医院を開業しながら、跡継ぎのなかった精神科医の斉藤紀一のもとに、14歳の頃、養子候補として行くことになります。
短歌に関しては、中学時代から興味を抱き、創作を開始。高校時代には正岡子規の影響を受けます。東京大学の医科に在学中、伊藤左千夫に師事し、短歌の創作を本格的に始めると、1913年(大正2年)に歌集『赤光』で注目を浴びます。
精神科医としても活躍し、青山脳病院の院長なども勤めながら、歌人としても活動、歌集17冊の他、評論や随筆も数多く残しています。ただ、本人は、あくまで本業は精神科医だという姿勢だったようです。
斎藤茂吉は、夕陽にまつわる短歌もよく詠み、そのうちの一つの短歌「春がすみとほくながるる西空に入日おほきくなりにけるかも」は、斎藤茂吉が結婚してまもない頃に詠んだ作品で、当時住んでいた青山から眺めた景色を描いています。
現代語訳すれば、「春霞が遠く流れている西の空に、今沈もうとしている太陽が大きくなっているよ」といった意味になります。
春霞とは、冬から春にかけ、ぼんやりと霞がかって見えにくくなることを指します(霞に明確な定義はなく、昼は霞、夜は朧という呼び名になります)。
入日とは、西の空に沈んでいく夕日のことで、春霞のなかに沈んでいく夕陽が、ずっと大きくなって見えることへの美しさと、ほのかに漂う悲しみが歌われています。
今でこそ、東京はビル郡もありますが、その頃の東京は高いビルもなく、地平線に沈む太陽が、とても大きく見えたようです。
この作品は、斎藤茂吉の第二歌集である『あらたま』に収録されています。
以上、斎藤茂吉の短歌「春がすみとほくながるる西空に入日おほきくなりにけるかも」の意味と現代語訳でした。