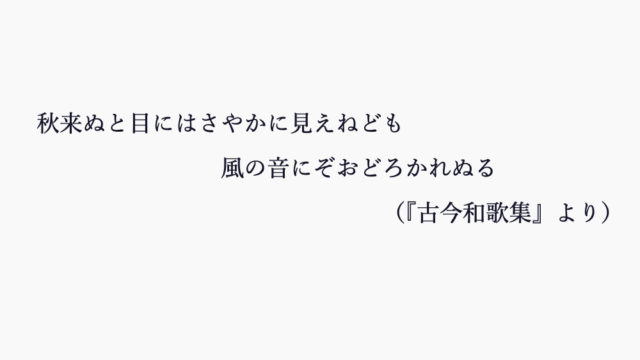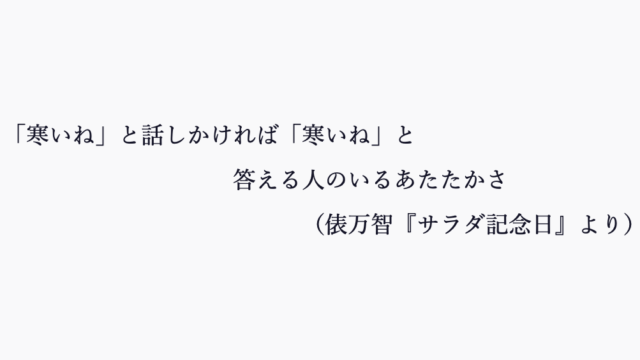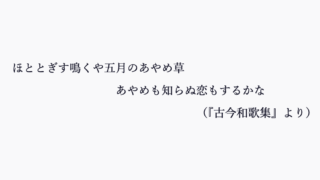春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空 藤原定家
〈原文〉
春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空
〈現代語訳〉
春の夜の浮き橋のように儚い夢から覚めると、山の峰で横雲が分かれて離れ離れになっている明け方の空よ。
概要
作者の藤原定家は、平安時代末期から鎌倉時代初期の代表的な歌人で、『新古今和歌集』の撰者の一人でもあります。
藤原定家が生まれた年は、応保2年(1162年)で、仁治2年(1241年)に亡くなります。
 藤原定家の肖像画
藤原定家の肖像画
和歌のうち、もっとも得意なジャンルが恋歌で、弟子には、恋歌の創作について、「恋の歌をよむには凡骨の身を捨て、業平のふるまひけむ事を思ひいでて、我身をみな業平になしてよむ」と語っています。
藤原定家自身は決して恋愛の道に明るいわけではなかったものの、恋歌を詠む際には、多くの恋をして美男子としても知られる在原業平(『伊勢物語』の主人公のモデルとも言われる)に成り切って詠む、ということを伝えています。
「恋の歌をよむには凡骨の身を捨てて、業平のふるまひけむことを思ひいでて、わが身をみな業平になしてよむ」。自分は奥手で恋の道には暗いけれども、恋歌を詠む時には、全身全霊、在原業平になりきって詠むというのです。もとより、実人生で定家が恋愛に明け暮れるということはありませんでした。
自分は恋愛のことはよく分からない。だから、恋愛の歌をつくる際には、その自分のことは捨て、恋愛についてよく知っている在原業平にすっかりなりきってつくる、ということです。
この「春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空」という和歌は、鎌倉時代初期の勅撰和歌集『新古今和歌集』に収録されている歌です。
以下、この和歌の現代語訳や語句の意味などを簡単に解説したいと思います。
冒頭は、「春の夜の夢の浮き橋が途絶えして」ということですが、これは、「春の夜に見た儚い夢から覚めたとき」という意味になります。
この「浮き橋」とは、水の上に筏や舟を浮かべ、その上に板を渡した橋で、舟橋とも言い、不安定なもの、不確かなものの比喩として使われます。
また、「夢の浮き橋」という表現で、「夢の中のあやうい通い路。また、はかないもの」を意味します。
下の句にある、「峰にわかるる横雲の空」とは、「峰によって雲が分断されて分かれる」という解釈と、「峰から雲が遠ざかり、離れ離れになる」という解釈があります。
いずれにせよ、峰のほうで夜明けの横雲が、遠く離れ離れになっていく情景が歌われています。
もう一度、最初から全体を通して振り返ってみましょう。
この藤原定家の和歌、「春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空」を現代語訳すると、「春の夜の浮き橋のように儚い夢から覚めると、山の峰で横雲が分かれて離れ離れになっている明け方の空よ」となります。
春の夜の浮き橋のように、不確かで儚い夢というのは、一つの恋を比喩的に表現していると捉えることもできるでしょう。
その儚い恋の夢から覚めたとき、明け方の空を見れば、山の峰で離れ離れになっている横雲がある、という悲しい恋を風景で描いた歌なのかもしれません。
春と言えば、恋の季節でもあり、恋心という幻想に浸ったような心情を、「春の夜の夢」と表現し、その儚さを、浮き橋に喩える、というのは、とても美しい描写です。
また、その儚い恋が途絶える、夢から覚める、別れが訪れる、ということを、離れ離れになっていく明け方の雲として描く、というのも、なんとも巧みで映像的な表現と言えるでしょう。
どこか、ぽつんと残された自分と、空の風景だけがあるような寂しさも伝わってきます。
以上、藤原定家の和歌「春の夜の夢のうき橋とだえして峰にわかるる横雲の空」の意味と現代語訳でした。