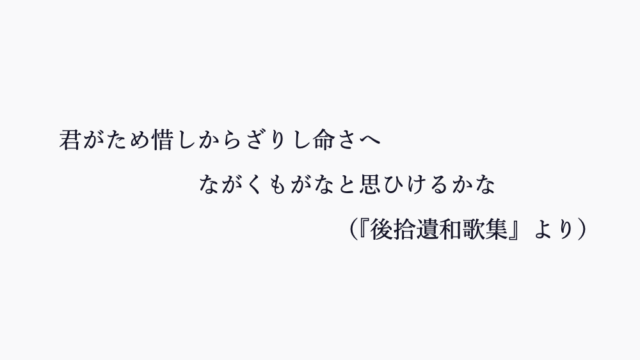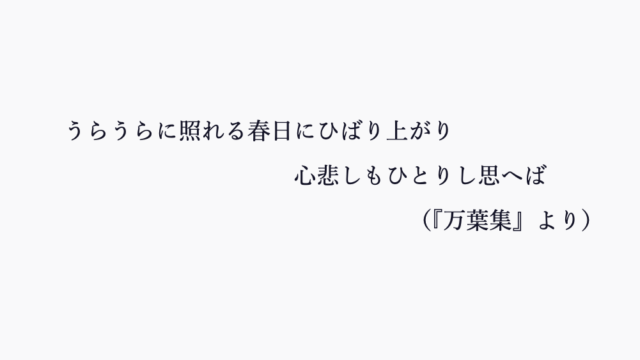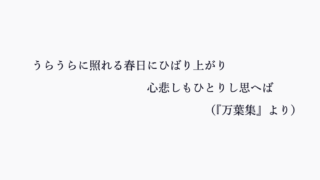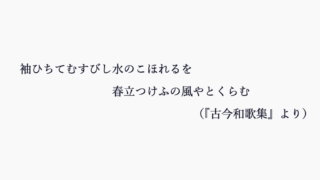秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる 藤原敏行
〈原文〉
秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる
〈現代語訳〉
秋が来たと、はっきりとは目に見えないが、風の音を耳にすると、秋のおとずれにはっと気づかされる。
概要と解説
作者の藤原敏行は、平安時代前期の貴族・歌人・書家で、その時代に和歌の名人とされた三十六歌仙の一人でもあります。
生まれた年代は不詳ですが、亡くなった年は、昌泰4年(901年)または延喜7年(907年)と考えられています。
書家として秀でていた藤原敏行は、空海と並べられるほどの書道の大家でもあります。
和歌は、勅撰和歌集である『古今和歌集』に収録されている他に、家集『敏行集』などもあります(勅撰和歌集とは、天皇や上皇の命令によって編集された和歌集のことです)。
この「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」という和歌は、『古今和歌集』に収録され、よく知られた藤原敏行の代表的な歌の一つです。
詞書として、「秋立つ日詠める(立秋の日に詠んだ)」という言葉がついています。
詞書とは、和歌の前に書かれ、その和歌の詠まれた状況や題名などが書かれた文章のことを意味し、「題詞」や「詞」ということもあります。
以下、この和歌に関する心情や語句の意味などを簡単に解説したいと思います。
まず、冒頭の「秋来ぬ」とは、読み方が、「こぬ」ではなく「きぬ」となります。
これは、「秋が来ない」ではなく、「秋が来た」という意味になります。このときの「ぬ」は、完了の助動詞です。
この「秋来ぬ」に続く、「見えねども」とは、「見えないけれども」という意味です。
それから、「さやかに」というのは、「はっきりと」という意味になります。
この「さやか」というのは、現代でも使われる言葉で、漢字で書くと「明か/清か」となります。
さやかは、「はっきりと」という以外に、「さえて明るいさま」「音や声がさえてよく聞こえるさま」「さわやかなさま、爽快なさま」といった意味もあります。
こういった点から、「目にはさやかに見えねども」というのは、「(秋が来たと)目にははっきりとは見えないけれども」となります。
そして、最後の「おどろかれぬる」とは、「はっと気づかされる(おどろく=はっと気づく)」という意味です。
この「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」という歌を、全体を通し、分かりやすく現代語訳すれば、「秋が来たと、はっきりとは目に見えないが、風の音を耳にすると、秋のおとずれにはっと気づかされる。」という意味になります。
立秋は、現在の8月上旬頃なので、まだ夏の盛りであり、はっきりと秋が姿を見せることはありません。
しかし、かすかな風の音に、「ああ、秋が来たのだ」と感じ取ることができる、という心情を詠んだ歌です。
確かに、立秋の頃になると、まだまだ景色は夏真っ盛りで、秋の雰囲気を目に見えて捉えることはないものの、風のなかに、かすかな秋のおとずれを感じることがあります。
目には見えなくても、夏から秋にかけての季節の移り変わりの予感をすくい取る歌であり、決して凝った表現というわけではありませんが、季節の変わり目を繊細に捉え、真っ直ぐ表現した和歌と言えるでしょう。
江戸時代には、「秋来ぬと」と聞けば、「風の音」と口に出るほど、立秋を詠んだ和歌の代表作として一般に浸透していたそうです。
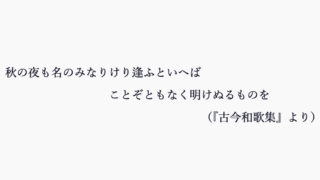
江戸時代中期の俳人である与謝蕪村の作品にも、藤原敏行の歌を踏まえた、「秋来ぬと合点させたる嚔かな」という句があります。
この「くさめ」というのは、「くしゃみ」のことです。
この与謝蕪村の句は、「秋が来たと、くしゃみをしたことで納得がいったよ」という意味の作品です。ある種のパロディのような感覚だったのでしょうか。
また、藤原敏行が詠んだ秋の作品としては、以下の和歌なども挙げられます。
秋の夜のあくるもしらず鳴く虫は我がごと物や悲しかるらむ
現代語訳 : 秋の長い夜が明けるのも知らずに鳴き続ける虫は、私のように悲しいのだろうか。
この歌では、秋の夜、悲しみのあまり一晩中泣いていたら、ふと、虫たちも鳴いていたことに気づき、あの虫たちも私のように悲しいのだろうか、という心情が詠まれています。
何人か来て脱ぎかけし藤袴くる秋ごとに野辺をにほはす
現代語訳 : どんな人が来て脱いで掛けていったのだろうか、藤袴は秋が来るたびに野辺によい香りを匂わせる。
藤袴とは、秋の七草の一つで、人の着る袴に見立てて詠んだ歌です。
以上、藤原敏行の代表作、「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」の意味と解説でした。