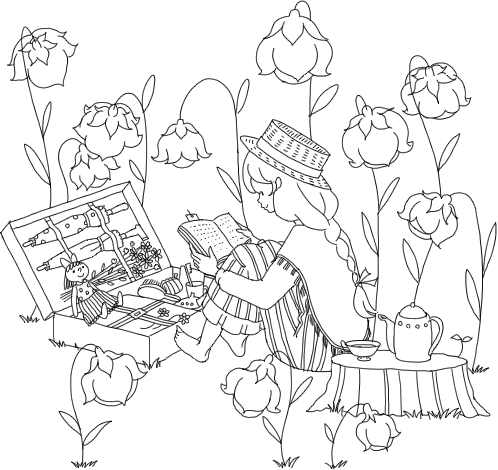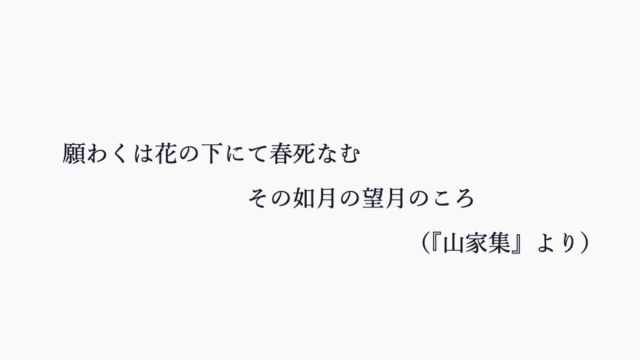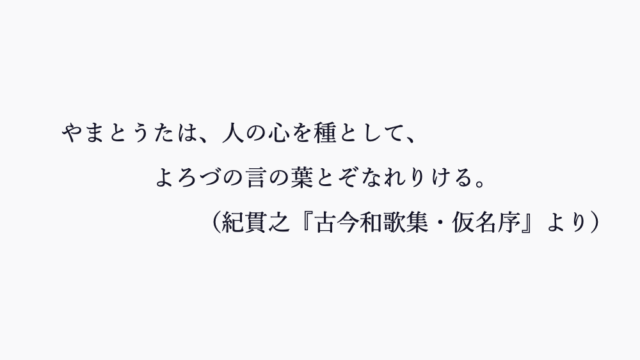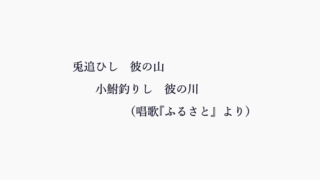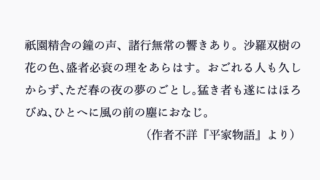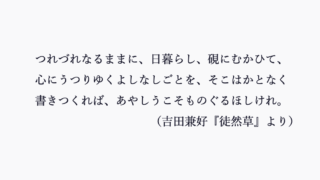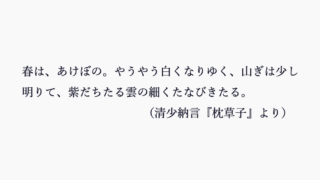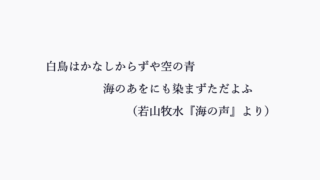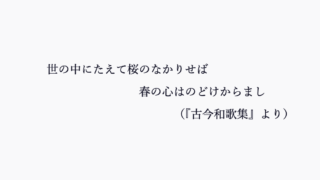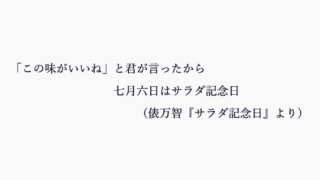徒然草の冒頭
〈原文〉
つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。
〈現代語訳〉
孤独にあるのにまかせて、一日中、心に向かい合っては消える他愛のない事柄を、とりとめもなく書きつけてみると、妙に妖しくおかしな気分になってくる。
概要と解説
 菊池容斎「吉田兼好」
菊池容斎「吉田兼好」
作者の吉田兼好は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての官人、随筆家、歌人です。
生まれた年や没年ははっきりとは分かっていませんが、1283年頃に生まれ、1352年以後に亡くなったと考えられています。
中学の教科書などでは、「吉田兼好」ではなく「兼好法師」と教わりますが、この兼好法師という呼び名は、吉田兼好が途中で出家したことに由来し、本名は卜部兼好と言います。
吉田兼好の書いた随筆『徒然草』は、清少納言の『枕草子』や鴨長明の『方丈記』と並び、日本三大随筆の一つです。
この『徒然草』の制作年は、1330年から1331年にまとめられたという説や、長年書きためた文章を1349年頃にまとめた、という説が有力です。
冒頭文の「つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」は、日本の古典のなかでも、有名な一節ではないでしょうか。
末文の「あやしうこそ物狂ほしけれ」は、現代語訳でも解釈に多少のばらつきがあるため、原文のまま、そのニュアンスを感じ取るほうがよいかもしれません。
この部分をざっくりと現代語訳に書き換えれば、「思いのままに、日がな一日心に移りゆくなんでもないことを、なにとはなしに書きつけてみれば、なんとも妖しく不可思議なことになった」といった意味合いになるでしょう。
のんびりと過ごし、思いのまま、心にうつりゆくことを、なんとなく書いてみると、妙に狂ったような不思議な高揚感に見舞われてどんどんと筆が進んでいく、という感覚でしょうか。
この「つれづれなるままに」「よしなしごとを」「書きつく」という組み合わせは、自身の卑下や謙遜を意味する表現として、過去の日本文学にも存在する定型の一つのようです。
池澤夏樹さん編集の文学全集で、『徒然草』の現代語訳を担当した思想家の内田樹さんは、吉田兼好の魅力について、「現場主義的」と指摘しています。
言葉で表現するに当たって難しいのは、手触りと匂いと味わいであり、『徒然草』は、五感のなかでも、特に読者の「触覚」と「嗅覚」を刺激することのできる文体である、と内田さんは解説しています。
ちなみに、『徒然草』の英語訳については、複数の翻訳があり、ドナルド・キーン氏による冒頭文の英語訳は、以下のような表現となっています。
What a strange, demented feeling it gives me when I realize I have spent whole days before this inkstone, with nothing better to do, jotting down at random whatever nonsensical thoughts have entered my head.
この英語訳を、再度日本語で訳してみると、この硯の前で丸一日何をするということもなく頭の中に浮かんできた無意味な考えを手当たり次第書き綴っていると、気づいたら、なんと奇妙で気が狂ったような気分になるだろう、といった意味になります。
やはり、ぼんやりと、筆に任せるままに書いていると、気づいたときには、不思議と狂ったような高揚感に包まれている、というニュアンスになるようです。
以上、吉田兼好『徒然草』の冒頭でした。