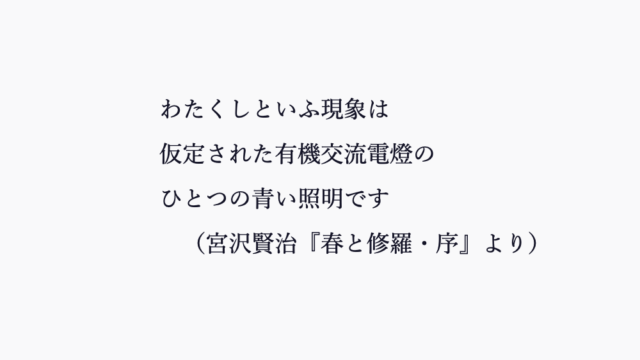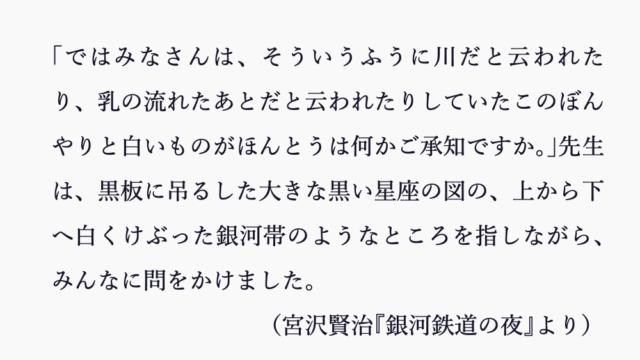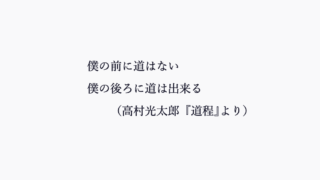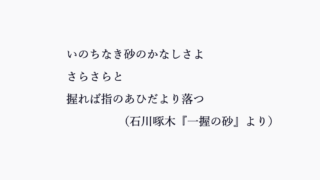『ふるさと』の歌詞全文と「うさぎおいしかのやま」の意味
唱歌である『ふるさと』は、1914年(大正3年)に、文部省唱歌の第六学年用として発表された曲です。
文部省唱歌とは、1881年以降、第二次世界大戦終了時の1945年までの文部省発行の初等音楽教科書に掲載された、文部省選定の教育用歌曲のことで、尋常小学校向けには、一学年から六学年まで全部で6冊あり、一つの学年につき、20曲ずつ、合計120曲が収録されています。
文部省唱歌と現在の音楽教科書との違いとしては、「全体が一つのコンセプトによって編纂されている」という点が挙げられます。
個々の楽曲の作者については、編纂委員会の合議によって決められたこともあり、個人の名前は伏せられ、著作権は文部省が所有し、この件については、作者に高額な報酬を払い、個人名は伏せ、作者自身も一切口外しない、といった契約を交わしていたそうです。
現在、作者の一部は判明したものの、原案の作者を特定することは難しい状況で、不明のままの曲も少なくありません。
この『ふるさと』に関しても、長らく作詞者、作曲者が不明となっていましたが、作詞家として高野辰之、作曲家に岡野貞一が同定され、1992年からは、作者名も音楽の教科書に明記されるようになります。
この歌は、歌詞を見るだけでも、音楽が脳内で流れるという人も少なくないのではないでしょうか。
以下は、『ふるさと』の歌詞全文と、現代語訳になります。
原文
兎追ひし彼の山
小鮒釣りし彼の川
夢は今もめぐりて
忘れがたき故郷
如何にいます父母
恙なしや友垣
雨に風につけても
思ひいづる故郷
志を果たして
いつの日にか帰らん
山は青き故郷
水は清き故郷
現代語訳
うさぎを追いかけた あの山よ
こぶなを釣った あの川よ
今も夢のように思い 心巡る
忘れられない ふるさとよ
父や母は どうしているでしょうか
友たちは 無事に暮らしているでしょうか
雨や風にみまわれるたびに
思い出す ふるさとよ
夢を叶え志を果たしたなら
いつの日にか 帰りたい
山の青い ふるさとへ
水の清い ふるさとへ
歌詞の冒頭、「うさぎおいし かのやま こぶなつりし かのかわ」という一節は、読むだけでも自然と曲調が想起される、とても有名な一節でしょう。
ところで、この「うさぎおいし」という部分を、「うさぎ美味しい」と錯覚してしまっている人も少なくないようです。
同志社女子大学の日本文学科教授の吉海直人さんも、『唱歌「ふるさと」について』という文章のなかで次のように書いています。
まず出だしの「うさぎ追いし」ですが、これを耳にすると「うさぎ美味しい」と聞えるようで、うさぎを食べた歌という誤解も生じています。
しかし、実際は、漢字を見ても分かるように、「うさぎおいしかのやま」とは、「兎追ひし かの山」で、「野うさぎを追いかけた あの山よ」という意味になります。
昔は、日本で野うさぎを追いかけている光景というのも日常的だったのでしょうが、今はすっかり見ることはありません。
古文であることに加え、描写される光景が、故郷として馴染みがないことも、この「うさぎおいし」の意味の勘違いが生じる要因なのかもしれません。
また、「うさぎおいし かのやま」というとき、「追っているのが誰か」という日本語特有の主語の曖昧さもあります。
たとえば、故郷と、幼少時代の自分自身の経験を重ね合わせて歌っているのであれば、「子供が、野うさぎと追いかけっこをしている」映像を浮かべるでしょう。
一方で、狩猟としてうさぎを追いかける、という解釈もあり、その場合、「大人がうさぎを追いかけているのを子供が見ている」という光景を想像できるかもしれません。
ただ、「こぶなつりし かの川」も、同じように「小鮒を釣っていた あの川よ」という意味になるので、この二つとも、主語は、子供の頃の「私」と考えられます。
うさぎおいし かの山
こぶな釣りし かの川
うさぎを追いかけていたあの山よ、小鮒を釣っていたあの川よ、と自分が子供の頃に行っていたことを思い出しているのではないでしょうか。
それでは、うさぎを追いかける「私」は、うさぎと追いかけっこをして「遊んでいた」のでしょうか。
どうも、この「うさぎおいし」とは、単純に、うさぎと追いかけっこをして「遊んでいた」様子を意味しているわけでもないようです。
かつて、野生のうさぎは害獣とされ、各地で「うさぎ追い」と呼ばれる、村人がみんなで協力してうさぎを捕まえる行事や風習があり、子供も一緒に参加したり、また、子供たちで、うさぎを追いかけにいったこともあったそうです。
産山村で3日、冬恒例のウサギ追いがあり、親子連れや地元の猟友会員ら約100人が参加した。草原で捕まえた野ウサギを「産雪」と名付けて野に戻すと、元々いた草むらに向かって雪の上を駆けていくのを見届けた。
昔ながらの行事で冬の草原に親しんでもらおうと、村が毎年開き、今年で21回目。村の人によると、それ以前は地域の小学校で実施され、さらに以前は子どもが自分たちで野に出て、ウサギを追っていたという。
この「うさぎおいし かのやま」には、単に、子供たちが追いかけっこをして遊ぶ、というだけでなく、こうした文化的背景もあったのでしょう。
その後の「夢は今も巡りて、忘れ難き故郷」とは、現代語訳で、「今も夢のように思い、心を巡る、忘れられない故郷よ」という意味になります。
一般的に知られているのは、この自分の思い出の光景を綴った、一番までかもしれません。
二番では、その故郷にいる、両親や友人たちのことを思い出します。
まず、「如何にいます父母」の「います」とは、「いる」の丁寧語ではなく、古語の尊敬語「おはす」に当たり、「無事で暮らしている」というニュアンスもある、「いらっしゃる」という意味になります。
次に、「つつがなし」とは、「病気や災難に合っていない、無事で暮らしている」という意味の言葉です。「恙」とは、病気や災難を意味します。
また、「友垣」とは、「友達」のことです。この漢字は、交わりを結ぶことを、垣根を結ぶことになぞらえたことに由来します。
その後の「雨風」というのは、苦しいことや辛いことの比喩の意味合いがあると解釈できるでしょう。
このように『ふるさと』の二番は、両親や友人は無事に暮らしているでしょうか、雨風に打たれるような辛いこと、悲しいことがあるたびに、故郷を思い出します、という意味の歌詞になります。
そして、三番では、この歌詞の主人公が、なぜ故郷から離れているのか、という理由が表現されています。
当時の若者たちは、立身出世を夢見て故郷を離れ、都会に向かいました。都会で成功し、故郷へ帰る、というのが夢でした。
志を果たし、いつか帰りたい(何も果たせず、帰れないかもしれない不安も抱えて)、といった思いが込められているのでしょう。
もちろん、歌詞の解釈は人それぞれですし、もう少しふわっと、意味を曖昧に捉えることで、時代性からも放たれ、今にも通じる普遍的な歌として聴くこともできるでしょう。

舞台はどこか
ちなみに、この故郷の舞台やモデルとなった場所というのは、一体どこなのでしょうか。
かの山や、かの川という風に、ぼかした表現がなされ、また、長年『ふるさと』の作詞者や作曲者が不明だったことから、具体的な舞台というのは明確には分かりませんでした。
それゆえに、誰もが「自分の故郷」を浮かべ、共感できた、というのもあるでしょう。
その後、制作者が同定され、実際は、作詞作曲者である高野や岡野が思い浮かべた自分たちの故郷もあったのかもしれません。
二人の故郷は、それぞれ、作詞者の高野が長野県、作曲家の岡野は鳥取県です。
高野の故郷の旧豊田村には、「かの山」とされる熊坂山や大平山などの里山があり、また班川という「かの川」も流れています。
高野の故郷、長野県中野市(旧豊田村)では「かの山」とされる熊坂山や大平山といった里山が望め、また、班川という「かの川」も流れる。
一方、作曲家の岡野の出身地鳥取県にも霊峰・大山があり、鳥取市内には江戸時代から明治時代にかけてコイやフナ、シジミが採れたという袋川が流れていた。
出典 : 「かの山」「かの川」とはどこか、「♪兎追いし」が日本人の心に響く理由と謎…誕生100年・唱歌「ふるさと」制作秘話
また、冒頭の「うさぎおいし」についても、作者自身の思い出と関連した指摘があります。
以下の文章では、作詞者の高野の地元で行われていた「うさぎ追い」の様子も具体的に描かれています。
作詞者である高野辰之は長野県出身である。
「兎追いし」という歌詞は高野の時代は実際に学校の伝統行事であり、みんなでマントを着て、手をつなぎ輪になって大声を上げながら雪の山を登る。
驚いた兎を追い込み捕まえる。兎鍋にして学校の校庭で食したとのこと。その頃は大事なタンパク源でもあった。
おそらく高野は作詞にあたって幼少のころの思い出深い学校での行事、級友と鍋を囲んで食べた兎鍋は懐かしさが溢れる出来事だったのであろう。
「小鮒釣りし」は子供のころ友達と近くの川で遊んだ楽しい思い出の一つとおもわれる。
作詞者の高野の出身地、長野県の旧豊田村でも、伝統的な狩猟である「うさぎ追い」が行われ、学校の伝統行事としてもあったとのこと。
マントを着て、手を繋いで輪になり、大声をあげながら、みんなで雪の山を登る。びっくりした野うさぎが追い込まれ、捕まる。そのうさぎを、鍋にして校庭で食べる、という風習だったようです。
こうした思い出を振り返りながら、「うさぎ追いし かの山」と書いたのでしょうか。
そう考えると、「うさぎおいし」は、「うさぎが美味しい」という意味ではなかったとしても、実際にうさぎを食べたこと自体は間違いではなさそうです。
以上、文部省唱歌『ふるさと』の歌詞全文や「うさぎおいし」の意味でした。