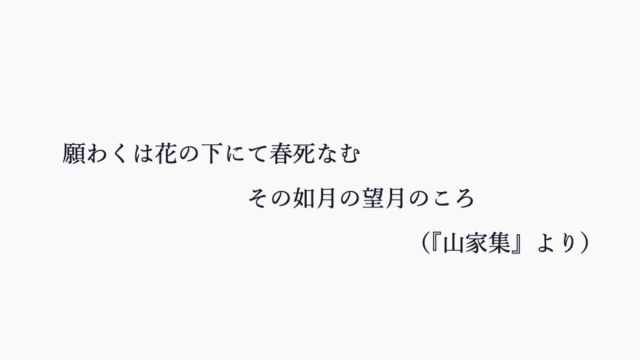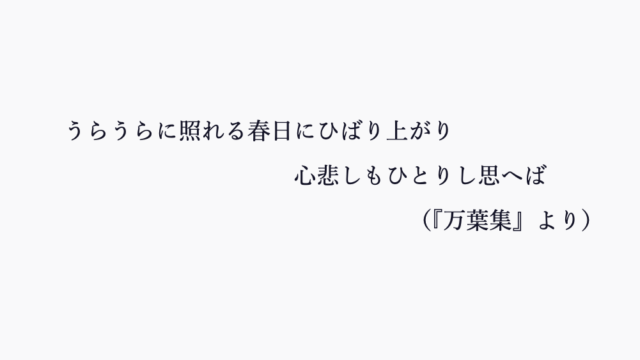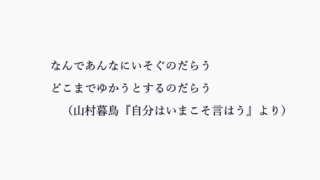いのちなき砂のかなしさよさらさらと握れば指のあひだより落つ〜意味と現代語訳〜
〈原文〉
いのちなき砂のかなしさよ
さらさらと
握れば指のあひだより落つ
〈現代語訳〉
命のない砂の儚くも悲しいことよ 握れば指のあいだからさらさらと落ちてゆく
概要と解説
作者の石川啄木は、本名石川一と言い、明治19年(1886年)、岩手県に生まれた歌人で、明治45年(1912年)に26歳で結核のため亡くなります。
中学時代に文芸誌の『明星』に掲載されている与謝野晶子らの短歌や、学校の上級生らの影響を受け、啄木は文学の道を志すようになります。しかし、カンニングや成績の悪さを理由に、17歳で盛岡中学を退学。
その後、上京し、『明星』に詩や短歌を発表。石川啄木というペンネームも、この頃から使うようになります。
石川啄木は、明治38年(1905年)、盛岡にいた頃から恋愛が続いていた堀合節子と結婚。
明治39年(1906年)、故郷の渋民村で代用教員となりますが、翌年には北海道に移り、職を転々と変えたあと、再び上京。
明治43年(1910年)、歌集『一握の砂』を発表します。
この「いのちなき砂のかなしさよ さらさらと 握れば指のあひだより落つ」という一首も、『一握の砂』に収録されています。
全体的に、平易な言葉で映像的な短歌なので、意味自体が分からない単語というのはないと思います。
命のない砂の儚い悲しさ。そして、その砂を握ったら、指のあいだからさらさらと落ちてゆく。
この指のすきまからこぼれ落ちる砂の描写については、「砂時計」のイメージと重なります。

砂時計は、砂がさらさらと落ちていく光景に、決して逆戻りすることのない時間の流れと儚さを感じさせます。
この啄木の短歌では、その落ちてゆく砂の一粒一粒が、時間の流れであるというだけでなく、ひとりひとりの人間の命という風にも解釈できるかもしれません。
いずれにせよ、こぼれ落ちていく砂の儚さに、命の儚さや諸行無常の世界を表現している作品と言えるのではないでしょうか。
この一首は第三句の「さらさらと」という表現が効果的で、はかない砂に託して己が生命を哀惜する作者の虚無的な心情が歌われており、歌集『一握の砂』の書名を暗示する秀作である。
出典 : 『石川啄木(短歌シリーズ・人と作品10)』
歌集のタイトルとなっている『一握の砂』のイメージとも大きく重なるものでしょう。
また、この「いのちなき砂のかなしさよ さらさらと 握れば指のあひだより落つ」という短歌以外に、『一握の砂』のタイトルの由来となったとされる歌に、同じ連作のなかの「頬につたふ なみだのごはず 一握の砂を示しし人を忘れず」があります。
この歌は、現代語訳すると、「頬に伝う涙を拭うことなく、一握りの砂を示してくれた人のことを忘れない」という意味になります。
一体、「一握の砂」とは何か、といったことに関しては、解釈が分かれるようです。
無数の海の砂から、一握りした砂を示す。しかも、涙を流しながら、その涙を拭うこともせずに、一握の砂を示す、ということから、たとえば、詩や短歌など、表現の比喩になっているのかもしれません。
涙を拭わずに(もっと言えば、涙の表現として)数々の短歌を示してくれた人たちのことを、石川啄木自身が、忘れない、ということでしょうか。
この「砂」が比喩として意味することとしては、言葉や短歌の他にも、様々な要素が込められているのかもしれません。
以上、石川啄木の『一握の砂』収録の歌、「いのちなき砂のかなしさよ さらさらと 握れば指のあひだより落つ」の意味と現代語訳でした。