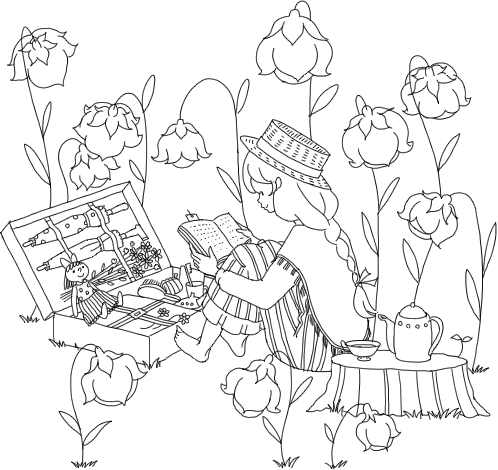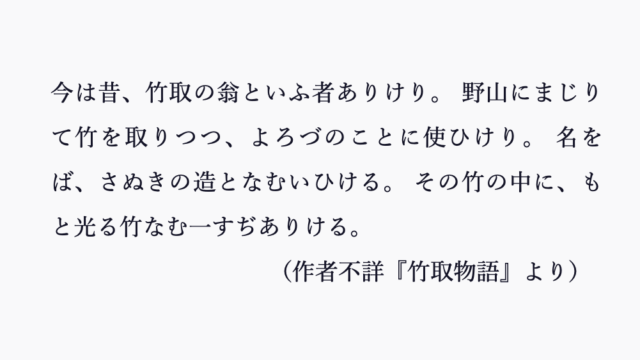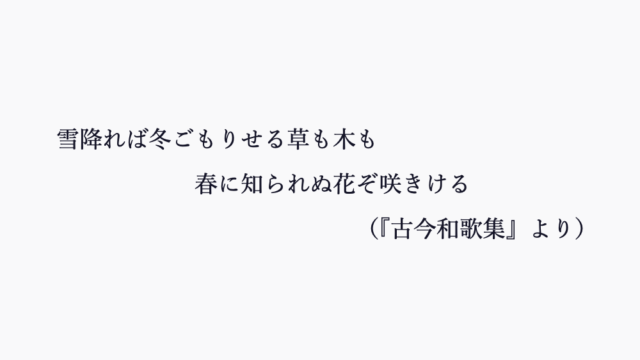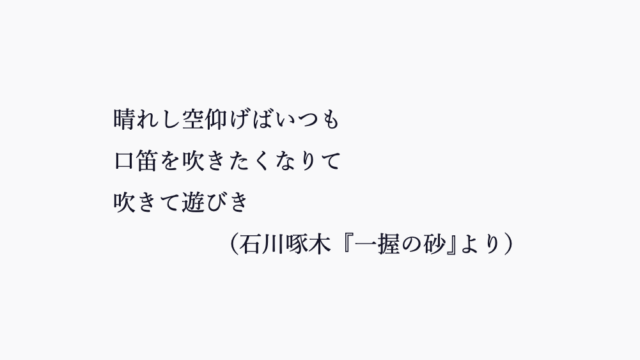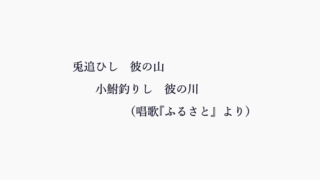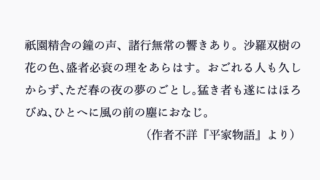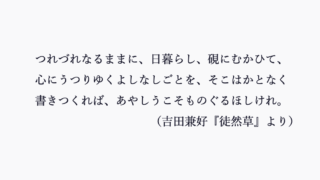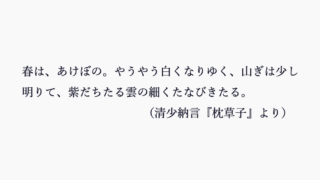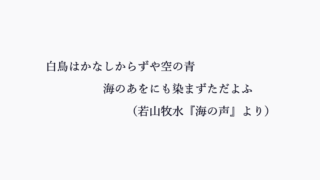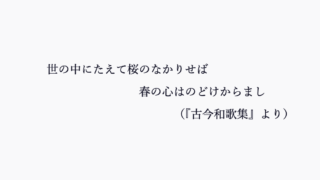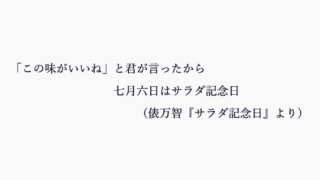西行の辞世の句〜願わくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ〜意味と現代語訳
〈原文〉
願わくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ
〈現代語訳〉
願うことなら、桜の花の咲いている下で春に死にたいものだ。(釈迦が入滅したとされている)陰暦の2月15日の満月の頃に。
概要
 西行
西行
西行法師は、1118年(元永元年)に、検非違使左衛門尉佐藤康清の子供として生まれ、本名は、佐藤義清と言います。
もともとは武士で、23歳のときに出家。西行は僧侶や放浪の歌人として知られ、『新古今和歌集』にはもっとも多い94首の作品が収められています。のちの時代では松尾芭蕉も西行のことを師として仰いでいます。
西行が出家した理由は、近しい者の急死や失恋などの説がありますが、詳しいことは分かっていません。
西行は桜を愛し、作品でも桜の歌が多く残っていますが、西行の桜を詠んだ和歌のなかで代表的な作品と言えば、辞世の句である、「願わくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」が挙げられます。
辞世の句とは、死を前にして書き残された詩的な短文であり、和歌や俳句、漢詩などの形で残されることが多く、本人が死を自覚して書いた場合だけでなく、生涯最後の短い詩文も広く辞世の句と称されることもあります。
辞世の句の文化は、主に東アジア特有のもので、特に日本の中世で詠まれることが多かったようです。
この西行の和歌は、辞世の句の歴史のなかでも有名な作品で、『山家集』に収録され、現代語訳すれば、「願うことなら、桜の咲いている下で春に死にたいものだ。(釈迦が入滅したとされている)陰暦の2月15日の満月の頃に」となります。
冒頭の「ねがわくは」とは、「願うことは。望むことは。どうか。」といった意味で、「願わくば」という形で使われることもあります。
続く「花」というのは、西行の愛した桜のことで、春、花びらが咲いては散っていく桜の下で死にたい、という想いが歌われています。
後半の句にある、「如月」は旧暦の2月で、「望月」とは満月を意味します。旧暦の2月の満月の日というのはお釈迦様の亡くなられた日であり、同じ頃に自分も死にたい、と出家者である西行は願ったのでしょう。
そして、実際に、この辞世の句にある通り、西行は、陰暦の2月16日に入滅したと言われています。享年73歳でした。
歌に詠んだ通りの西行の死は、人々に感銘を与え、語り継がれます。
西行の死因というのは不明ですが、なぜこれほどぴったりと辞世の句にあるような頃に死を迎えることができたのか、宗教学者の山折哲雄氏は、西行の死というのは自然死ではなく計画的な自決だったのではないか、と指摘しています。
近年「西行の死は自然死ではなく、計画的な自決だった」との説を唱え始めたのが山折氏だ。西行は釈迦の悟りの境地に近づくため、釈迦の命日の2月15日ごろに自分も死のうと決断した。
そのために幾日も断食・断水をし、自らの意思で絶命したと山折氏は推測する。「実際に平安・鎌倉期の高僧は死期を悟ると断食をし、安らかな自死を選んだ」と指摘する。
実際のところは分かりませんが、無常と向き合ってきた西行が自身の死に対して、より意識的に関わった可能性もあるのかもしれません。
ちなみに、西行の作品で、桜とともに無常観を詠んだ歌として、「世の中を思へばなべて散る花のわが身をさてもいづちかもせむ」があります。
これは『新古今和歌集』に収録されている和歌で、現代語訳すれば、「世の中を思うと、全てが散る花のように儚く、他ならぬ我が身もそうなのだが、それにしても我が身は一体どこへ行くのだろうか」といった意味になります。
〈原文〉
世の中を思へばなべて散る花のわが身をさてもいづちかもせむ
〈現代語訳〉
世の中を思うと、全てが散る花のよう(に儚く)、他ならぬ我が身もそうなのだが、それにしても我が身は一体どこへ行くのだろうか。
前半の「なべて」とは、「すべて」「一般に」という意味で、後半の「いづち」というのは、「いづこ」と似たような意味合いで「どこ」となります。
無常観について考え、桜を愛した西行の残した桜の歌の数は、200首以上に及んでいます。
以上、西行の辞世の句、「願わくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」の意味と現代語訳でした。