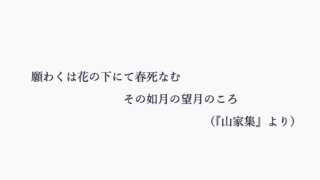いろはにほへとの全文と意味
いろは歌
いろは歌とは、「いろはにほへと ちりぬるを」で始まる、仮名を重複させずに作られた、全部で47文字の古くからある七五調の日本の韻文で、現代で言う五十音順に当たります。
全ての仮名が、一切重ならずに一字ずつ使っていることから、文字を覚える際の手習い用の文としても広く用いられるようになります(ただし、もともとは手習い用ではなかったようです)。
いろは歌が、一体いつ頃作られたのか、作者は誰なのか、なぜ作られたのかなど、はっきりした経緯は分かっていません。ただ、製作の時代としては、10世紀中頃以降と考えられています。
また、いろは歌の作者として、平安時代初期の僧である空海(弘法大師)が作ったのではないか、という話は広く知られ、平安時代に弘法大師が作ったという言い伝えは古い文献にも残っています。
しかし、現在の学説では、様々な理由から、この「空海作者説」には否定的な見解も多く、古い時代には仏教関連の書物や辞書に用いられていたことから、誰か僧侶によって書かれたものではないか、と見られています。
いろは歌の数は、47字として知られていますが、後年になると、最後に「ん」や「京」が付け加えられるようになります。
また、いろは歌が用いられる有名な遊びとして、江戸時代に広がったとされる、「いろはかるた」があります。
いろはかるたとは、全47文字と「京」 を合わせた48文字を句の頭に置いてことわざが記されているかるたで、主に正月に子供が遊びます。江戸時代中期に京都で作られ、江戸や大阪、名古屋などに広がったと言われています。
内容も、地域で違いが見られ、たとえば、「い」は、江戸が、「犬も歩けば棒に当たる」、大阪が、「一を聞いて十を知る」、京都が、「一寸先は闇」となっています。
他にも、「ほ」は、「骨折り損のくたびれ儲け(江戸)」「惚れたが因果(大阪)」「仏の顔も三度(京都)」。「ね」は、「念には念を入れよ(江戸)」「寝耳に水(大阪)」「猫に小判(京都)」など、随所に、地域による違いが見られます
全文と意味
いろは歌は、学校の教科書にも掲載され、また手習用として最初に学ぶことから、転じて、「いろは」という言葉が、「物事の基本」などを意味する場合もあります。
このいろは歌の冒頭、「いろはにほへと、ちりぬるを」という一文は、一度は耳にしたことがあると思います。
ただ、「いろはにほへと、ちりぬるを」の続き、いろは歌の全文については、知らない人や、忘れてしまったという人も少なくないのではないでしょうか。
以下は、「いろはにほへと」の続き、いろは歌の全文になります。
いろはにほへと ちりぬるを
わかよたれそ つねならむ
うゐのおくやま けふこえて
あさきゆめみし ゑひもせす
ひらがなだと、少し意味が理解しづらいかもしれません。
漢字も交えて、いろは歌の全文を見ると、多少分かりやすく、文章の意味合いやニュアンスが掴めてくるでしょう。
色は匂へど 散りぬるを
我が世誰ぞ 常ならむ
有為の奥山 今日超えて
浅き夢見し 酔ひもせず
この全文の読み方は、「いろはにおえど、ちりぬるお、わがよたれぞ、つねならん、ういのおくやま、きょうこえて、あさきゆめじ、えいもせず」です。
いろは歌のうち、現代ではほとんど見ることのない文字として、「ゐ」と「ゑ」があり、古い時代には、それぞれ「うぃ」と「うぇ」と発音されていたものの、現代仮名遣いでは、一般的に、「い」と「え」に置き換えられています。
いろは唄
いろは歌は、五十音順のように、特に意味がなく決まりごととして文字が順番に並んでいる、というわけではなく、れっきとした「意味のある詩」になっています。
それでは、いろは歌の内容を現代語訳すると、どういった意味合いになるのでしょうか。
仏教的な無常感を表現した文章として知られる「いろは歌」。以下は、全文を分かりやすく意訳した文章となります。
色は匂へど 散りぬるを
花は咲き誇っても 散ってしまうのに
我が世誰ぞ 常ならむ
誰が永遠に この世で生きられようか
有為の奥山 今日超えて
苦悩や悲しみなど色々とある現世の深い山を 越えていく
浅き夢見し 酔ひもせず
儚い夢を見たり 酔いに耽ることもしない
冒頭の「色は匂へど」ですが、昔の人にとっては、「色が匂う」というのは、「花が咲く」ことを意味し、この「花」というのは、桜のことを指します。
また、仏教用語では、「色」は存在を意味することから、あらゆるものは存在として感じられるものの、それらもいずれは散り、存在は失われる、といった意味合いだという指摘もあります。
次の「我が世」というのは、「この世」という意味で、「一体この世において、誰が永遠に生き続けられることがあろうか」と、無常観が歌われています。
その後の「有為」というのは、仏教用語で、生滅する現象世界のあらゆる事物のことを指し、「様々なことが生まれては消える深い山(越えることが難しい深い山に喩えた表現)のような世界を、今日も一つ越えて、あるいは超越して」といった意味合いになります。
最後の「浅き夢」とは、「儚い夢」を意味し、「酔いもせず」というのは、「酔いに耽ることもしない」となります。
いろは歌の全文を分かりやすく言えば、「花は美しく咲いても、たちまち散ってしまうように、この世の誰もが、生まれ、死ぬ。誰も永遠ではない、様々な因縁から生じる無常の深い山を超越し、儚い夢を見たり、酔っ払って現実から逃れない先に、悟りの道がある」ということを伝えた歌になります。
いろは歌の歌詞の解釈は諸説あるものの、基本的には、こういった仏教の無常観と絡めて考えられることの多い歌です。
ちなみに、古来、いろは歌は、仏教の経典である『涅槃経』の諸行無常偈の和訳が由来とされています。
諸行無常 是生滅法
諸行は無常なり 是れ生滅の法なり
生滅滅已 寂滅為楽
生滅し滅しおわりて 寂滅をもって楽と為す
これは、「この世の全ては移り変わり、生まれるものは必ず滅する。この生と滅を超越した先に、究極的な悟りの世界がある」という意味になり、まさにいろは歌で書かれている内容と同様の仏教的な世界観が書かれていると言えるでしょう。
以上、「いろはにほへと」で始まるいろは歌の意味や全文、現代語訳でした。