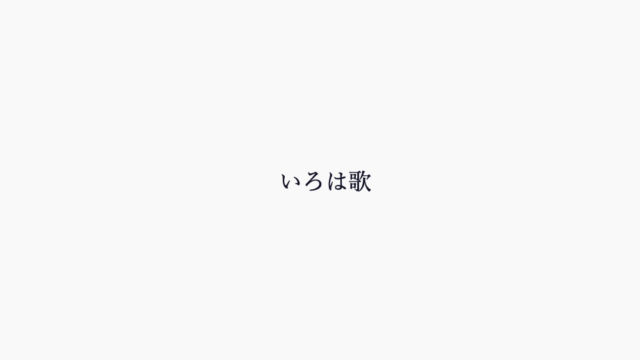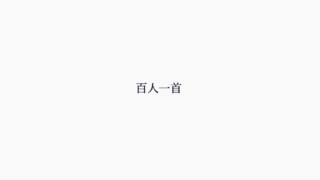弓道と弓術の違いとは
日本の弓を使った文化の一つに「弓道」があります。ほとんど同じ意味で、「弓術」という言葉が使われることもあります。
弓道に関する日本の古典的名著として、オイゲン・ヘリゲルの『日本の弓術』がありますが、この本では、「弓道」ではなく「弓術」という日本語訳がとなっています。

それでは、一体、弓道と弓術には、どんな違いがあるのでしょうか。
両者は、基本的には同じ意味ですが、歴史的に、弓術が先にあり、明治以降に、より精神的な側面も込められた「弓道」に名前が変更された、と言えるでしょう。
以下、弓道及び弓術の歴史を紹介しつつ、違いに関する詳細について紹介したいと思います。
もともと弓は、手の届かない場所を走ったり飛んだりする動物を捕食するための道具として世界中で誕生し、日本でも、石器時代の頃には使用されていたようです。
確かな記録は残っていませんが、日本での弓矢の起源は縄文時代で、狩猟と祈祷のために使われていたと考えられています。
弥生時代に入り、稲作中心の生活への変化から、土地や水源の確保のために領土争いが始まり、弓矢が武器の側面を持つようになります。
その後、中国文化との交流もあり、弓術が神事として行われるようになり、平安時代の武家の登場を経て、武家思想に繋がっていきます。
日本古代からの弓矢の威徳の思想と、中国の弓矢における「射をもって、君子の争いとなす。」という射礼思想礼から、朝廷行事としての射礼の儀が誕生。
武家時代には弓矢を通じた礼の思想がうまれ、やがて日本固有の武家思想と結びついていくのです。
武器としての弓矢という捉え方が終焉を迎えるのは、織田信長や豊臣秀吉の時代のことで、鉄砲の伝来が、大きなきっかけとなります。
この辺りから、次第に弓術は、戦闘具ではなく、心身鍛錬の道に変わっていきます。
その後、平和な時代の続いた江戸時代には、庶民の娯楽や武芸として成長します。
明治維新以降、弓術を含めた武術の存在意義が問われ、時代遅れと見なされるも、弓術存続のために、各流派が道場を開くなど、庶民への普及活動に勤しみ、弓術存続に力を入れます。
そして、1895年(明治28年)には学校教育に取り入れられ、1919年(大正8年)には、「弓術」という呼び名が「弓道」に改められることもあり、精神的な側面が強くなります(より詳細な、弓術、弓道の歴史は、全日本弓道連盟のサイトに掲載されています)。
そのため、弓術と弓道は、ほとんど違いがないという指摘もありますが、ニュアンスとしては、より心の鍛錬に特化したものと言えるかもしれません。
また、弓術というと、「古武術」の一つといった意味合いも強くなります。
古くからの武術や武芸の一種としての弓術、近現代になって精神的な側面が大きくなると弓道、といった区別でしょうか。
ちなみに、海外発祥のスポーツ競技であるアーチェリーなども含め、広い意味で弓矢を使ったもの全般を「弓術」と指す場合もあります(参照 : 全然違う! 「アーチェリー」と「弓道」の違い)。