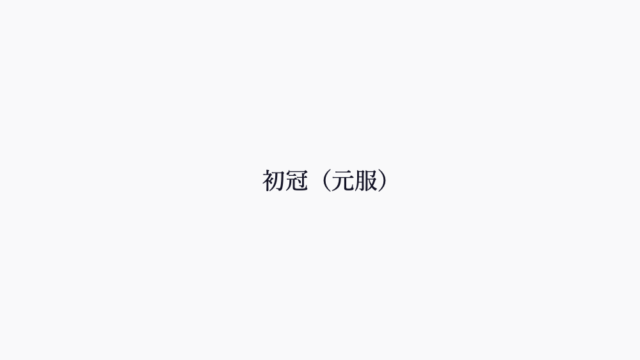あけぼのとつとめての違い
平安時代に清少納言によって書かれた『枕草子』は、鴨長明『方丈記』、吉田兼好『徒然草』とともに日本三大随筆の一つに数えられています。
この『枕草子』では、冒頭に春、夏、秋、冬、それぞれの季節の趣ある光景が柔らかな文体で描写されます。

春はあけぼの。夏は夜。秋は夕暮れ。冬はつとめて。それぞれに美しい時間帯が紹介され、そのあとに具体的な光景が描かれます。
夏と秋は、「夜」と「夕暮れ」とあり、文字通りで意味が分かりやすいものの、春の「あけぼの」と冬の「つとめて」は、日頃、日常的には、あまり使われることはないかもしれません。
春はあけぼの、というときの曙とは、夜がぼのぼのと明けていく、夜明けの始まる頃のことを指します。
一方で、つとめて、というのは、漢字で「夙めて」と書き、早朝を意味します。
あけぼのも、つとめても、ざっくり言えば、早い朝、ということになります。
ただ、あけぼのと、つとめての違いは、「あけぼの」が、「夜明けの始まり頃」の辺りを指すのに対し、「つとめて」は、夜明けからまもない「早朝」を意味する点にあります。
そのため、時間帯的に言えば、「あけぼの」のほうが早い時間帯になります。
春というのは、ああ、夜が明けていくなぁ、という時間帯が美しく、冬の場合は、夜明け後の早朝が素晴らしい、と『枕草子』には描かれています。
〈春〉
春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく、山ぎは少し明りて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。
春は、あけぼの(がよい)。だんだんに白くなっていく山際が、少し明るくなり、紫がかった雲が細くたなびいていく(その様子がよいのだ)。
〈冬〉
冬は、つとめて。雪の降りたるはいふべきにもあらず。霜のいと白きも、またさらでも、いと寒きに、火など急ぎ熾して、炭もて渡るも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も、白き灰がちになりて、わろし。
冬は、早朝(がよい)。雪の降っている朝は言うまでもない。霜のとても白いのも、またそうでなくても、たいへん寒いのに、火などを急いでつけ、炭をもって運びまわるのも、とても似つかわしい。昼になり、寒さがゆるくなってくると、火桶の火も、白い灰が多くなってよくない。
以上、「あけぼの」と「つとめて」の意味と違いでした。