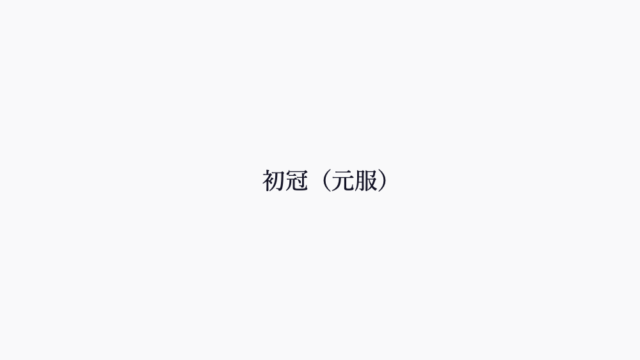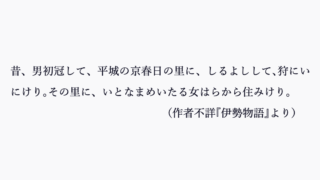徒然なるままに
徒然草の冒頭「つれづれなるままに」
吉田兼好による随筆『徒然草』は、清少納言の『枕草子』や、鴨長明の『方丈記』とともに、日本三大随筆に数えられています。
吉田兼好は、出家していることから兼好法師とも称される、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての官人、歌人、文筆家です。
この『徒然草』のはっきりした成立年はわかっていませんが、鎌倉時代後期と考えられています。
さて、吉田兼好の随筆『徒然草』の冒頭は、「つれづれなるままに」という有名な書き出しで始まります。
つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。
出典 : 吉田兼好『徒然草』
随筆の冒頭にあり、また、題名にも使われている、「徒然なるままに」という言葉は、『徒然草』を象徴する表現と言えるでしょう。

日常で使うことは皆無と言っていい「徒然なるままに」ですが、一体どういった意味なのでしょうか。
まず、「徒然」とは、「やるべき事がなく、手持ち無沙汰なさま」「することがなく、退屈なさま」「つくづくと物思いにふけること」「しんみりとして寂しいこと」「変化がなく、同じ状態が続くこと」などを意味します。
なにもやることがなく、退屈で、物思いにふけり、しんみりと寂しく、変化がなく同じような状態が続くこと。それは現代的な感覚で言えば、一人きりの静かな休日や、病床の光景といったイメージかもしれません。
徒然の使い方としては、「読書をして病床の徒然をまぎらわす」や、「徒然な舟の中は人々の雑談で持切った(島崎藤村『破戒』)のように、名詞や形容詞として用いられます。
その他、副詞表現で、「長々と、そのままずっと」という意味で使われることもあります。

こういった「徒然」の意味を踏まえ、「徒然なるままに」とは、「やるべきこともなく、手持ち無沙汰に任せて」という意味になります。
また、「徒然」には、物思いにふけったり、寂しい心持ちも意味合いとして含まれるので、「徒然なるままに」は、一人寂しくぼんやりと、なにをするのでもなく、物思いにふけりながら、その思いの流れのままに、といった意味合いも込められるでしょう。
なにもすることがなく、物悲しいような気持ちもありながら、その手持ち無沙汰に任せて、といったニュアンスでしょうか。
徒然草の冒頭の「つれづれなるままに…」は、現代語訳すると、「一人で特にすることもなく、手持ち無沙汰に任せて(徒然なるままに)一日中、硯と向かい合って心のなかに浮かんでは消えていく他愛もないことを、あてもなく書きつけていると、妙におかしな、狂ったような気持ちになってくる」という意味になります。
 海北友雪『徒然草絵巻』 17世紀
海北友雪『徒然草絵巻』 17世紀
もしかしたら、この絵巻の光景を見ていても、「徒然なるままに」という感覚が伝わってくるかもしれません。
「つれづれ」と「とぜん」
ちなみに、「徒然」という言葉の読み方として、「つれづれ」だけでなく、「とぜん」と読む場合もあります。
徒然でも、徒然でも、(厳密には多少の違いはありますが)それほど大きな意味の違いはありません(参考 : 拙著閑談(4) 「徒然(トゼン)」と「つれづれ」)。
徒然は、もともと漢語で、平安時代頃から漢詩文や日記の文章に登場します。この「とぜん」に由来した、「とぜんなか」「とぜねぇ」「とぜだ」といった方言もあります。
それぞれ微妙に形は違いますが、鹿児島や熊本、大分などの九州、青森、秋田、宮城といった東北、高知などでも使われるようです。
方言の場合も、意味は一緒で、「退屈だ、寂しい」となります。
たとえば、使い方として、秋田の方言で言えば、「お婆さんに逝かれて、とぜだ(寂しい)」「一人ぼっちで、とぜねぁ」などと言うことがあります(参照 : 一、くらしの中の方言|横手方言散歩)。
方言学が専門の小林隆教授によれば、方言として、「つれづれ」ではなく「とぜん」が広まった理由としては、「つれづれ」は、主に貴族や知識人などが使う文学用語で、民衆はほとんど使うことがなかった一方、「とぜん」は、庶民のあいだで使われ、全国に広がって方言となっていったと言います。
また、この「徒然」の類語として、「無聊」という言葉もあります。
無聊は、「退屈なこと。心が楽しまないこと。気が晴れないこと。」などを意味します。
ほとんど目にすることのない「聊」という漢字ですが、この一字では、「楽しむ、安らぐ」という意味があります。
以上、「徒然なるままに」の意味と現代語訳でした。