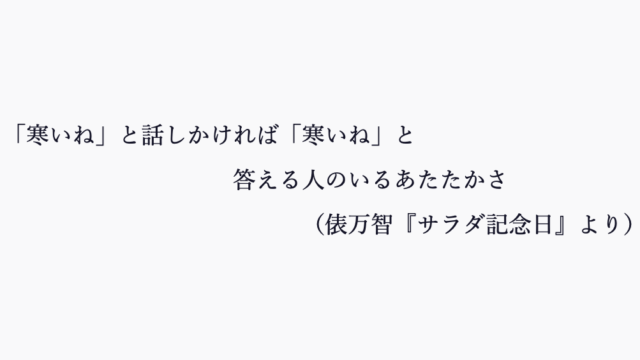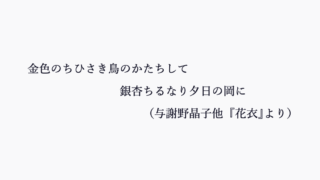晴れし空仰げばいつも口笛を吹きたくなりて吹きてあそびき〜意味と現代語訳〜
〈原文〉
晴れし空仰げばいつも
口笛を吹きたくなりて
吹きてあそびき
〈現代語訳〉
晴れている空を仰ぎ見ると、いつも口笛が吹きたくなって、口笛を吹いて遊んだものだなあ。
概要と解説
作者の石川啄木は、本名石川一と言い、1886年(明治19年)、岩手県に生まれ、27歳という若さで結核によって亡くなる夭折の歌人です。
中学時代、愛読した文芸誌の『明星』や学校の上級生らの影響から、文学の道を志すようになります。しかし、カンニングや成績の悪さを理由に、17歳で盛岡中学を退学。
文学を目指すために上京し、『明星』に詩や短歌を発表。石川啄木というペンネームも、この頃から使うようになります。
一度、故郷の岩手県盛岡に帰り、堀合節子と結婚。その後、函館、札幌、釧路など北海道を渡り歩き、再び、小説家になる夢を持って東京に上京。
この「晴れし空仰げばいつも口笛を吹きたくなりて吹きてあそびき」という短歌は、当時、東京の朝日新聞社で働いていた石川啄木が、懐かしい中学時代のことを思い出し詠んだ一首で、歌集『一握の砂』に収められています。
現代語訳すると、「晴れている空を仰ぎ見ると、いつも口笛が吹きたくなって、口笛を吹いて遊んだものだなあ。」といった意味合いになります。
故郷から遠く離れた東京で生活し、ふと空を見たら、口笛が吹きたくなり、子供の頃、空を見ながらよく口笛を吹いていたなぁ、と思い出す。そんな情景なのかもしれません。
空と口笛と少年時代、という爽やかな情景が、もう過ぎ去ってしまった遠い過去として描かれることで、いっそう哀愁も際立ちます。
たとえば、川沿いを歩いていたら、おもむろに石ころを拾って水切りがしたくなり、ああ、子供の頃よくこうして遊んでいたなぁ、と思い出すような感覚にも近いのでしょうか。
空も、川も、あの頃と地続きで、自分自身も、少年時代と繋がっている。時空を超えた、不思議な調和を感じさせます。
下の句の最後、「遊びき」の「き」は、過去を表す助動詞で、「けり」との違いとして、「き」は、自分が直接体験した過去を表します(「けり」は、「〜だったそうだ」と他人から伝え聞いた事柄を意味した過去表現になります)。
ちなみに、同じときに詠んだ短歌で、「不来方のお城のあとの草に臥て空に吸はれし十五のこころ」という歌も有名です。
これは、現代語訳すれば、「不来方城の城跡の草の上に寝転び、空を見ていたら、十五歳のときの自分の心は空に吸われるようだった」という意味の歌です。
大人になり、恋と文学に夢中だった15歳の頃を思い返しながら、草の上に寝転んで空を見ていたら、心が吸い込まれるようだったなぁ、と回想しているのでしょう。
この不来方城というのは、岩手にあるお城で、今は盛岡城跡公園となっています。通っていた学校の近くにあったようです。
園内には、宮沢賢治の詩碑や、啄木の歌碑があります。
以上、石川啄木の短歌「晴れし空仰げばいつも口笛を吹きたくなりて吹きてあそびき」の意味と現代語訳でした。