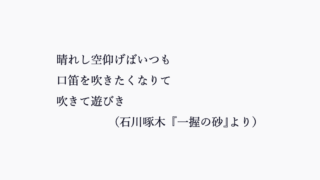祇園精舎の場所はどこ?
祇園精舎と言うと、鎌倉時代に書かれ、平家の凋落と無常観を描いた、古典文学『平家物語』の冒頭文に登場することで有名です。
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵におなじ。
出典 : 作者不詳『平家物語』
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
これは、祇園精舎に響く鐘の音は、因縁によって生じるこの世のあらゆる行いが皆、刻々と移り変わり、儚い存在だということを伝える響きである、ということを意味する一文です。
この「諸行無常の響き」と称される祇園精舎の鐘というのは、果たして一体どんな音だったのでしょうか。
なんとなく、除夜の鐘の音を連想する人もいるかもしれませんが、どうやら祇園精舎には、除夜の鐘のような鐘はなく、そもそも鐘自体あったのか、というのも諸説あり、小さな鐘はあったという話もあるものの、その辺りは定かではありません。
一説には、小型のガラス製の鐘だった、という話もあります。
また、祇園精舎という名前は聞いたことがあっても、場所に関しては知らない、という人も多いでしょう。
それでは、祇園精舎とは、一体どこにある、どんな施設なのでしょうか。
京都にも、祇園という名称の歓楽街があるので、祇園精舎も京都にあると思っている人もいるかもしれません。
しかし、実際は、祇園精舎とは、ブッダの時代にできた僧院のことで、建っていた場所は、インドの北部、現在のウッタル・プラデーシュ州シュラーヴァスティー県です。
祇園精舎は、正式名称を、祇樹給孤独園精舎と言います。
もともと、古代インドの舎衛国にあり、須達という当時の長者(富豪であり、徳を備えた者)が、仏陀に帰依した際、仏陀とその教団のために、祇園精舎を建設します。
この場所で仏陀の説法も行われ、仏教徒の聖地の一つとして考えられています。
ちなみに、江戸時代の日本人は、カンボジアのアンコールワットのことを祇園精舎と勘違いし、多数の日本人が、祇園精舎と錯覚したままアンコールワットを訪れたそうです。
一体なぜこうした場所の間違いが起きてしまったのでしょうか。
江戸時代の初頭には、東南アジアに渡る日本人も多く、カンボジアの日本町で、どうやらこれが祇園精舎らしい、という噂が立ち、日本にも伝わった、というのが勘違いの原因だったようです。
実際、アンコールワットには、江戸時代に祇園精舎と勘違いして訪れた武士の落書きが残されています。
寛永九年正月初めてここに来る/生国は日本/肥州の住人 藤原朝臣森本右近太夫一房/御堂を志し数千里の海上を渡り/一念を念じ世々娑婆浮世の思いを清めるために/ここに仏四体を奉るものなり。
この落書きを残した武士の名前は、旧松浦藩士の森本一房(生年不詳-1674年)。
彼がアンコールワットを訪れたのは1632年のことで、まだ徳川幕藩体制が整い始めて間もない頃だったために、鎖国も行われていませんでした。
森本は熱心な仏教徒でもあり、親の供養のためにも、一生に一度はカンボジアを訪れたいと願っていたようです。
以上、祇園精舎の場所でした。