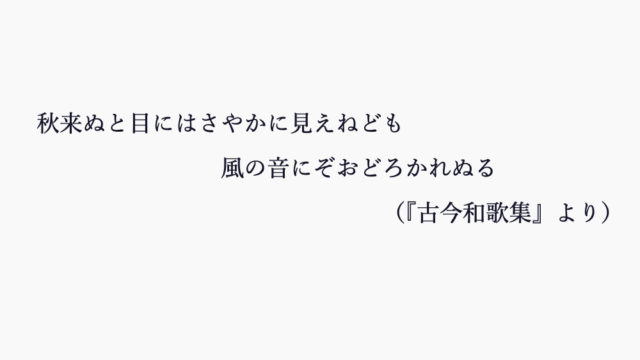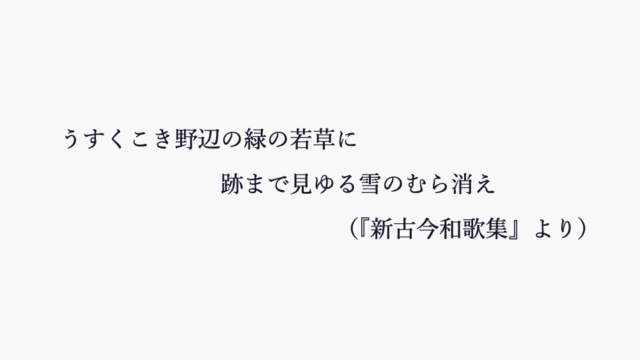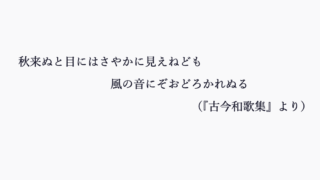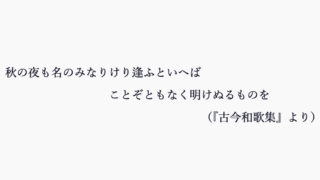袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ 紀貫之
〈原文〉
袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ
〈現代語訳〉
(昨年の夏の日に)袖を濡らしてすくった川の水が(冬のあいだに)凍っていたのを、立春の今日の風が溶かしていることだろう。
概要と解説
作者の紀貫之は、日本の日記文学の代表作である『土佐日記』の作者としても知られる、平安時代の歌人・貴族で、三十六歌仙の一人でもあります。
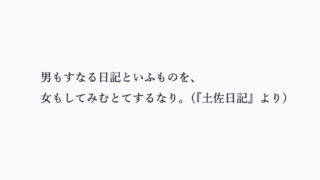
紀貫之が生まれた正確な年は分かっていませんが、貞観8年(866年)または貞観14年(872年)頃に生まれ、天慶8年(945年)に亡くなったと考えられています。
紀貫之は、日本の文学史上、歌人としてもっとも深い敬意を払われた人物の一人でもあり、選者として携わっている平安時代前期の勅撰和歌集『古今和歌集』では、「やまとうたは人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける」という冒頭で知られる、仮名序(仮名による序文)も書き記しています。
ちなみに、勅撰和歌集とは、天皇や上皇の命令によって編集された和歌集のことです。
 紀貫之(狩野探幽『三十六歌仙額』)
紀貫之(狩野探幽『三十六歌仙額』)
この「袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ」という和歌は、紀貫之の代表作の一つで、『古今和歌集』に収録されている作品です。
和歌のまえがきに当たる「詞書」がありますが、この歌の詞書には、「春立ちける日よめる」とあり、これは、「立春の日に詠んだ」という意味です。
立春とは、冬が極まって春の気配が立ち始める日を指し、新暦では、大体2月の前半頃になります。
冬の季節から、梅の花が咲き始めるなど、次第に春の兆しが見えるようになる頃で、この和歌も、その春の訪れを喜ぶような意味合いの歌と言えるでしょう。
それでは、和歌の語句の意味を細かく見ていきたいと思います。
まず、歌の冒頭、「袖ひちて」とありますが、この「ひちて」とは、「ひつ」という古語のことで、「水にぬれること、つかること」を意味し、漢字で書くと、「漬つ、沾つ」となります。
その後の「むすびし」は、「手ですくった」という意味で、「むすぶ」とは、この場合、「結ぶ」ではなく、「掬ぶ」と書きます。これは、水などを左右の手のひらを合わせて「掬う」という意味です。
下の句の「春立つけふ」とは、「春立つ今日」で、詞書にもあるように、立春の日のことです。
最後の「とくらむ」とは、「とかす」という意味です。この「〜らむ」は、推量の助動詞(「今頃〜しているだろう」)です。
昨夏のある日に、袖を濡らして手ですくった谷川の水が、冬になって凍り、その凍っている水を、立春の今日に吹く風が、溶かしていることだろう、という季節の巡りを表現し、絵としてイメージしやすい歌となっています。
袖ひちてむすびし水、すなわち、袖を濡らして水を掬う、という表現によって夏の情景が、映像的に描かれています。
その夏の水が、こほれる、という部分で、凍っている冬が浮かびます。
そして、春立つ今日の風によって川の氷が溶けていく様子が連想されることで、一つの和歌のなかで季節の移り変わる循環のイメージが想起されます。
最後に、もう一度、全体を通して分かりやすく現代語訳すれば、「袖ひちてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ」とは、「(昨年の夏の日に)袖を濡らしてすくった川の水が(冬のあいだに)凍っていたのを、立春の今日の風が溶かしていることだろう」という意味になります。
季節の変化が、ダイナミックに表現され、冬を越えて春の訪れを祝福するような、まさに立春の歌にふさわしい和歌と言えるのではないでしょうか。