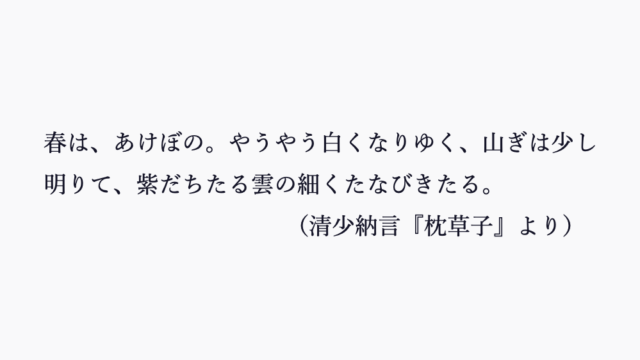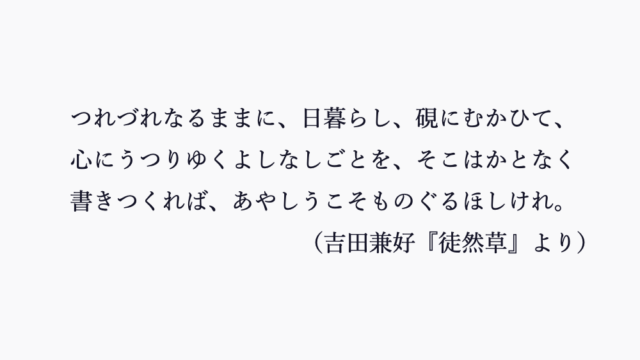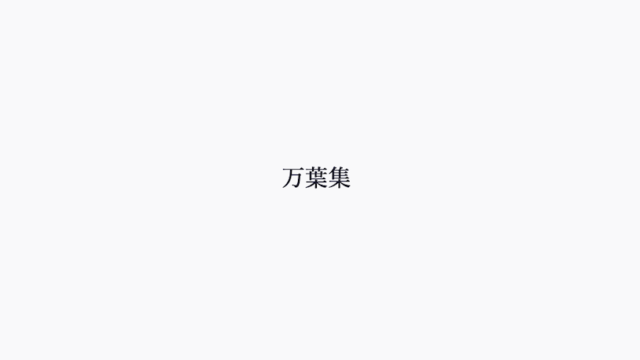紀貫之『土佐日記』の冒頭
〈原文〉
男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり。
〈現代語訳〉
男のひともするという日記というものを、女の私も試しに書いてみようと思う。
概要と解説
 菊池容斎「紀貫之」
菊池容斎「紀貫之」
これは紀貫之(827〜945)の『土佐日記』の冒頭文で、日本の古典文学のなかでも特に有名な一文です。
冒頭の現代語訳は、「男のひとが書くと聞く日記というものを、女の私も試しに書いてみようと思う」といった意味で、作者の紀貫之は、あえて女性のふりをして「男もすなる日記といふもの」を書こうと試みます。
なぜ、紀貫之はこんな手の込んだ演出をしたのでしょうか。
この『土佐日記』が書かれた平安時代中期には、日記というのは冒頭の一文にあるように男性官人による公務の記録のことであり、漢文で書かれることが一般的でした。
一方のひらがなは、当初女性によって用いられたもので、会話や和歌を描写することに長け(和歌では男性も使用しますが、日記では使いませんでした)、このひらがなの特性を活かした新しい日記文学の形に挑戦してみようという狙いが、紀貫之にあったのではないかと考えられています。
この『土佐日記』は、土佐守(現在の高知県知事に近い役職)の任期を終えた紀貫之が、京都の自宅に着くまでの55日間の旅を綴った日記文学です。
フィクションやジョークなども混じり、必ずしも実話というわけではなかったようです。

紀貫之は、京の都を離れ、土佐の国司として赴任し、5年が経ってから帰京。この旅路の様子から着想を得て、ひらがなを使った新しい境地の日記文学『土佐日記』を執筆します。
紀貫之が土佐の国司だったのは、930年から934年までの期間で、『土佐日記』の制作年も、任期を終えた934年頃だったと言われています。
そのため、『土佐日記』を書いた紀貫之の年齢も、正確には分かっていませんが、60代半ばくらいだと推定されます。
文章は、「男もすなる」の冒頭文のあと、「それの年の、十二月の二十日あまり一日の日、戌の時に門出す。そのよし、いささかものに書きつく」と続きます。
現代語訳は、「ある年の十二月二十一日午後八時頃に出発する。その旅の様子を少しばかり書きつける」。旅の日記はこうして始まります。
タイトルの『土佐日記』は、英語訳でも、そのまま「Tosa Nikki」ないしは「Tosa Diary」と言い、英語版『The Tosa Diary』も出版されています。
ちなみに、紀貫之直筆の『土佐日記』の原本は残っているのでしょうか。
残念ながら、原本に関しては残っておらず、現在残っているのは誰かが書き写した写本のようです。
ただし、『土佐日記』が珍しいのは、写本の写本といった形ではなく、紀貫之自筆の原本からの写本がある、ということです。
原本からの写本としては、藤原定家、藤原為家、松木宗綱、三条西実隆のものがあり、特に重要とされるのが、藤原定家、藤原為家の写本です。

 藤原為家版『土佐日記(土左日記)』 – 文化遺産オンライン
藤原為家版『土佐日記(土左日記)』 – 文化遺産オンライン
原本は、ある時期までは、紀貫之自筆のものが残っていたと伝わっています。
鎌倉時代までは、京都蓮華王院の宝蔵に納められ、のちに歌人尭孝のもとに、その後、足利義政に献上され、足利将軍家の所蔵となったのですが、以降の消息は分かっていません。
以上、紀貫之『土佐日記』の冒頭文でした。