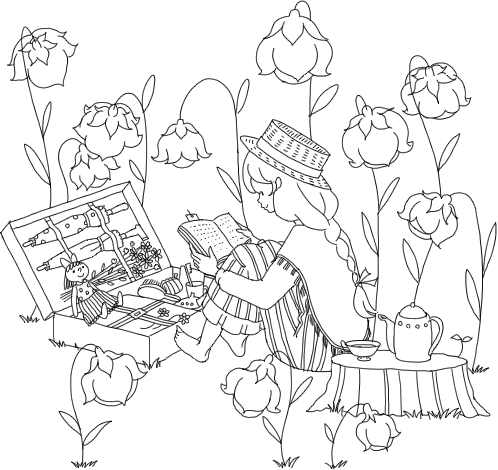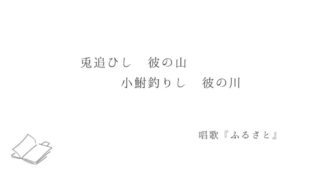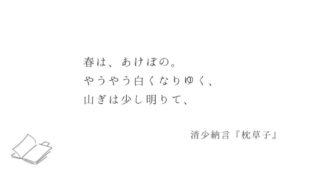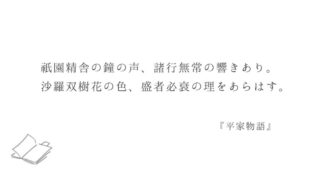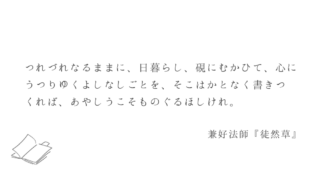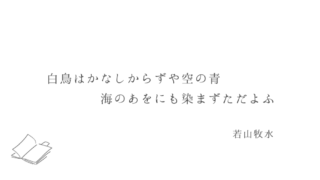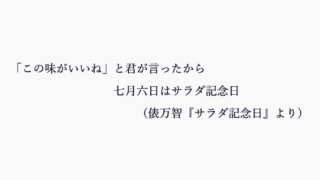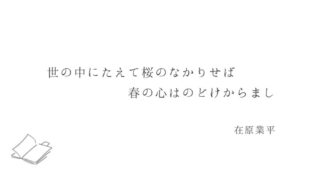夏目漱石『草枕』の冒頭
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。
概要と解説
夏目漱石の小説『草枕』は、1906年(明治39年)に発表され、特に冒頭文が有名な、漱石初期の名作として知られています。
小説の舞台は、「那古井温泉」(熊本県玉名市小天温泉がモデル)。主人公は30歳の洋画家で、山中の温泉宿に宿泊し、その宿で若奥様の那美と出会います。
彼女は、画家が今まで出会った女性のなかでもっとも美しい所作をする女性でした。あるとき、那美から自分の絵を描いて欲しいと頼まれるものの、なぜか主人公は、「足りないところがある」と断ります。
その「足りないところ」とは一体何か、というのが、『草枕』の主要テーマとなります。
この小説は、西洋近代化に対する問題意識や東洋の芸術論も語られた一冊で、ジブリの宮崎駿監督も、『草枕』を何度も繰り返し読んできた、というほど大好きな本として挙げています。
この冒頭文は、「山道を登りながらこんな風に考えた。理性ばかりでは他人と衝突するし、情に流されれば足元をすくわれる。意地を通しても窮屈だ。全く人の世の中というのは住みにくいものだ」といった意味になります。
ただし、これだけでは「この世界は嫌だな、生きていたくないな」といったずいぶんと厭世的な始まりになるものの、この冒頭文には続きがあります。
住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。
人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。
越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容て、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職が出来て、ここに画家という使命が降る。あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊い。
人の世の中というのは、どうしたって衝突もするし、わずらわしく、窮屈で、どこかへ移り住もうとしても、結局どこへ行っても住みにくい。そのことを深く悟ったときに、詩や絵が生まれる。
どこへ行っても住みづらいなら、この住みづらい世の中を、束の間でも住みやすい空間にする以外になく、その使命を担っているのが、詩人であり画家なのだ。そして、それゆえに尊いのだ、と漱石は書きます。
詩や絵にかぎらず、素敵な表現作品に出会ったり、あるいは自分でなにか表現をしているときに、「救われる」ような気持ちになることがあると思います。
それこそがまさに、この住みづらい世界を、束の間でも住みよくする、ということでしょう。