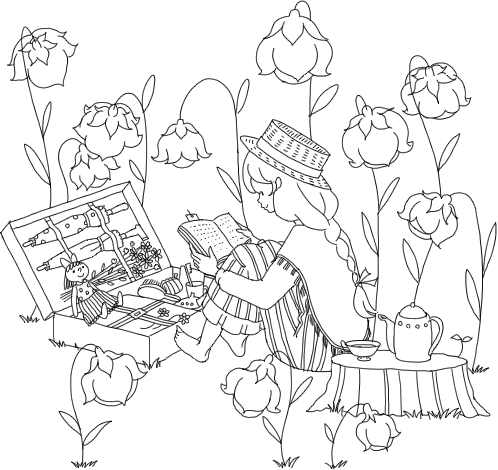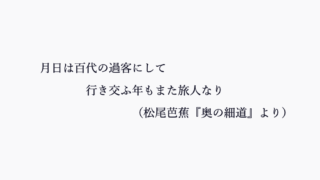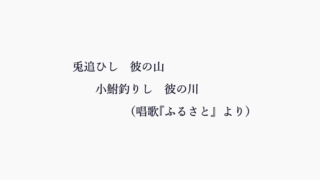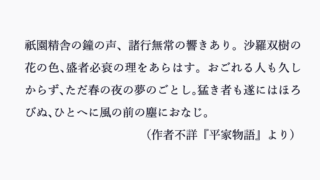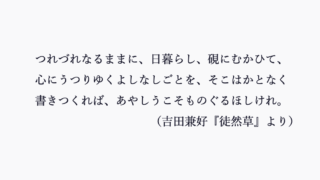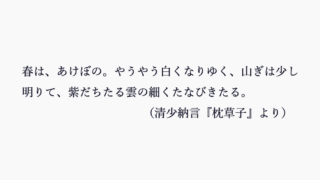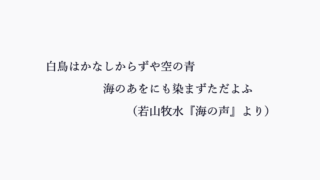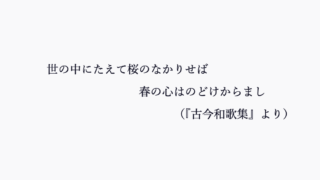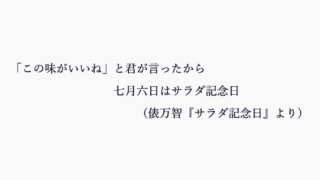松尾芭蕉〜旅に病んで夢は枯野をかけ廻る〜意味と季語、“辞世の句”か
〈原文〉
旅に病んで夢は枯野をかけ廻る
〈現代語訳(句意)〉
旅の途中で病床に伏していながら、夢のなかではなお枯野をかけめぐっている。
概要
この俳句の作者は、『おくのほそ道』で知られる、江戸時代前期の俳諧師である松尾芭蕉です。
松尾芭蕉は、寛永21年(1644年)に生まれ、元禄7年(1694)に、弟子たちのいさかいのあいだを取り持つために伊賀上野から大阪に向かった先で病床に伏し、発熱や頭痛、寒気に悩まされ、一時回復するも、ひどい下痢などで再び体調が悪化。次第に病状が重くなり、50歳で亡くなります。
死因ははっきりとはわかっていませんが、仲裁がうまくいかなかった心労がたたったとも言われています。
松尾芭蕉の代表作としては、俳句を盛り込んだ紀行文である『おくのほそ道』の他に、「古池や蛙飛び込む水の音」「夏草や兵どもが夢の跡」といった句も有名です。
また、病床のさなかに詠んだ、この「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」も、芭蕉の代表的な句としてよく取り上げられる名句の一つです。
旅の途中で病床に伏しているが、夢のなかでは、なおも枯野をかけめぐっている、という意味合いの句です。
枯野とは、草木の枯れはてた野原のことを指し、冬を表す季語です。この枯野の景色によって、病床に伏しながら、夢のなかでは枯野をかけめぐっている、という情景の物悲しさもいっそう際立ちます。
この句は、芭蕉が亡くなる4日前に詠まれたことから、松尾芭蕉の「辞世の句」として紹介されることもありますが、果たして「辞世の句」と言えるかどうか、という点は議論が残っています。
辞世の句ではない、あるいは、実質的には辞世の句のようなもの、といった扱いがされることも少なくないようです。
なぜ辞世の句か否かの議論が分かれるかと言うと、そもそも「辞世」というのが、死に臨んで遺す詩歌や句などを意味し、芭蕉本人が、死を覚悟して詠んだか、という辺りで議論が分かれ、特に着目される点として、前書きにある「病中吟」が挙げられます。
病中吟とは、病床にあって詠んだ句、という意味で、わざわざ、句に書かれている「旅に病んで」と重複しながらもつけているということは、芭蕉の意識として、あくまで病で伏しているだけで、まだ旅の途中であり、これからも旅を続けたいと思っている、辞世の句のつもりで詠んだものではなかった、ということが考えられます。
だから、松尾芭蕉にとって「生前最後の句」ではあっても、意識して詠んだ「辞世の句」ではなかったのではないか、というわけです。
ただし、病床のなかで死を間近にして詠まれ、辞世にふさわしい内容でもあることから、「辞世の句と同様のもの」といった風に捉えられることも多いようです。
作品の解釈も、微妙に分かれ、「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」という句に込めた想いとして、夢のなかではまだ枯野をかけめぐっているが、病に倒れ、もう自分は旅に出られないのだ、という悲壮感があるのか、それとも、また治って旅に出たいものだ、という未来への願いも込められていたのでしょうか。
芭蕉本人が辞世の句と意識していなかったとすれば、病を治し、まだこれからも旅を続けたいと思っていたのでしょうが、しかし、同時にこの句には、深い諦めや悲しみも感じられます。
また、枯野は、冬の枯れ果てた寂しい景色ではありますが、一方で、やがて訪れる芽吹きの春への期待も表します。
草の枯れ果ててひっそりとした冬の野。日、雨、風が寂々とわたり、荒涼とした景であるが、やがておとずれる芽吹きの季節を待つ姿でもある。
諦めと希望と、両方が入り混じった句だったのか、あるいは、必ずしも悲しみだけの死ではなく、死と命のめぐりが紡ぐ光を重ね合わせた表現だったのかもしれません。
ちなみに、松尾芭蕉は、辞世の句に関して、毎日毎日の句が辞世の句である、という信念を持っていました。
芭蕉はつねづね、今日の一句が明日の辞世という覚悟で生きていた人です。この句は辞世として作ったものではありませんが、この覚悟にてらしてみれば辞世だったでしょう。
出典 : 大岡信、谷川俊太郎編『声でたのしむ 美しい日本の詩』
特別辞世の句だとして詠まずとも、自然とそれが辞世の句になるような気持ちで日々詠んでいたのでしょう。