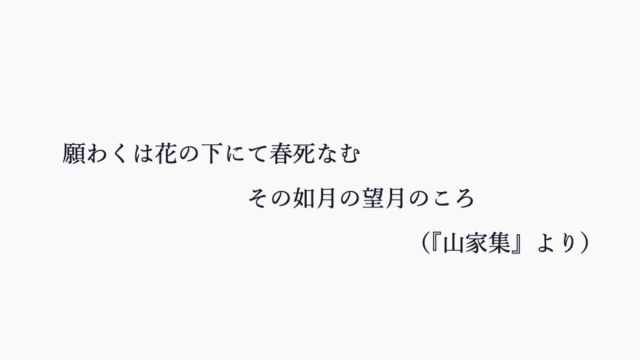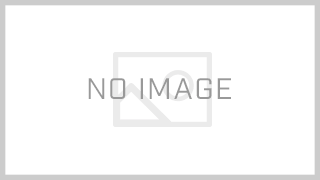奥の細道の冒頭「月日は百代の過客にして」全文
〈原文〉
月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。
〈現代語訳〉
月日は永遠の旅人であり、過ぎては訪れる年もまた旅人のようなものである。
概要と解説
松尾芭蕉『奥の細道』とは
松尾芭蕉の代表的な作品と言えば、この『奥の細道(おくのほそ道)』が挙げられます。
作者の松尾芭蕉は、江戸時代前期の俳諧師で、日本の文学史上に名高い俳諧師の一人であり、『奥の細道』は、俳句を愛する人々にとって「聖典」とさえ言われるほどの作品です。
それでは、『奥の細道』とは、一体どういった作品なのでしょうか。以下、概要や冒頭の文章をわかりやすく解説したいと思います。
まず、『奥の細道』のジャンルは、「紀行文」(より細かく言えば、「俳諧紀行文」)になります。
紀行文とは、旅の途中の体験や見聞、感想などを書いた文章のことで、『奥の細道』では、地の文の合間に、俳句が散りばめられています。
松尾芭蕉が、1689年(元禄2年)に、弟子で俳人の河合曾良と江戸の深川を出発し、奥州、北陸道を巡った際の紀行文が『奥の細道』で、旅の全行程は、距離にすると約2400キロメートル、日数は、約150日間となります。
道中は、基本的に歩き旅で、終着地は現在の岐阜県大垣市である大垣になります。
この旅の際の年齢については、松尾芭蕉が46歳、曾良は41歳です。
今の40代なら、まだまだ働き盛りの年齢で、これから旅に出る、というのも不思議ではありませんが、当時の平均寿命は現代ほどではなく、実際、松尾芭蕉は51歳、曾良は60歳で亡くなっていることから、人生の晩年における旅だったと言えるでしょう。
松尾芭蕉は、1694年に亡くなり、『奥の細道』は、芭蕉死後の1702年に出版されます。

タイトルの表記に関しては、一般的に「奥の細道」と、漢字表記で覚えている人も多いかもしれません。
ただ、現在は、松尾芭蕉の自筆の表記にならって、「おくのほそ道」というひらがなが主の表記もよく使われています。
序文の冒頭「月日は百代の過客にして」の全文と意味
さて、『奥の細道』の序文の冒頭は、「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。」という有名な一節で始まります。
現代語訳すれば、「月日は永遠の旅人であり、過ぎては訪れる年もまた、旅人のようなものである」という意味になります。
この「百代」とは、「極めて多くの年代」という意味から、「永遠」も指します。
続く「過客」とは、「通り過ぎてゆく人々、旅人」を意味する言葉で、「百代の過客」とは、「永遠の旅人」ということになります。
そのことから、「月日は百代の過客にして、行き交う年もまた旅人なり」とは、月日というのも、年というのも、時間の流れを指し、「時というのは、延々始まりと終わりを繰り返しながら、決して止まることのない、永遠の旅人のようなものだ」という意味合いになる、というわけです。
冒頭後半の「行き交ふ」を音読する際の発音については、「ゆきかう」で読まれることもあれば、学校で「ゆきこー」と教わることもあるようです。
発音の場合は、この二つですが、現代仮名遣いの読み方を考える場合は、「ゆきかう」でよいように思います。
この序文冒頭で使われる「百代の過客」という言葉は、中国の詩人の李白による、「夫れ天地は万物の逆旅(旅館)にして、光陰は百代の過各なり(そもそも天地はあらゆるものを迎え入れる旅館のようなものであり、月日の流れは永遠の旅人のようなものだ)」という、人生の儚さや移ろいやすさを綴った文章に由来すると考えられています。
この冒頭「月日は百代の過客にして」という代表的な一文含め、序文の全文と現代語訳は、以下の通りとなります。
〈原文〉
月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老いを迎ふる者は、日々旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。予も、いづれの年よりか、片雲の風に誘はれて、漂泊の思ひやまず、海浜にさすらへ、去年の秋、江上の破屋に蜘蛛の古巣を払ひて、やや年も暮れ、春立てる霞の空に、白河の関越えんと、そぞろ神のものにつきて心を狂はせ、道祖神の招きにあひて取るもの手につかず、ももひきの破れをつづり、笠の緒つけかへて、三里に灸据うるより、松島の月まづ心にかかりて、住める方は人に譲り、杉風が別墅に移るに、
草の戸も住み替はる代ぞ雛の家
表八句を庵の柱に掛け置く。
〈現代語訳〉
月日は永遠の旅人であり、過ぎては訪れる年もまた旅人のようなものである。船頭のように舟の上で一生を過ごす者や、馬子として老いを迎える者は、日々が旅であり、旅のなかに住んでいるようなものだ。昔の文人にも、旅の途中で亡くなった者は多い。
私も、いつの頃からか、ちぎれ雲が風に吹かれて漂う光景に誘われるように、あてもなく旅をしたいという思いが募ってきたことから、海辺をさすらい歩き、ようやく去年の秋に、隅田川のほとりのあばら家(深川芭蕉庵)に帰り、留守の間にできた蜘蛛の古い巣を払って住み、年の瀬を迎えた。それから新春になり、霞がかっている空を眺めていると、白河の関所(福島県)を越えようとそそる神が体についたように落ち着かなくなり、また道祖神にも旅に誘われるようで、取るものも手につかなくなった。ももひきの破れをつくろい、笠のひもをつけかえ、三里(足のツボ)に灸を据えると、早くも松島の月の姿が心に浮かび、住んでいた家は人に譲り、まずは弟子の杉風の別宅に移り住み、[次の句を詠んだ]。
草の戸も住み替はる代ぞ雛の家(こんな粗末な家も、今度代替わりすることになった。新しく家に住む家族には女児がいるそうで、殺風景な家から、雛人形が飾られるような家になるのだろう。)
この句を発句とし、表八句を庵の柱に掛けて置いた。
出典 : 松尾芭蕉『おくのほそ道』
時の流れというのは、永遠にさすらう旅人のようなもので、船頭のように舟の上で一生を過ごすようなものも、日々が旅であり、旅人のようなものだ、と芭蕉は語り、昔の文人においても、旅の途中で亡くなった人物は多い、と言います。
人生は、旅であり、結局は、その旅の途中で誰もが亡くなる、ということが言えるかもしれません。
だからこそ、その人生と重なり合う「旅」というものに惹かれるのでしょうか。
現代語訳を読むだけでも、今の我々にとっても分かりやすく理解できるような、松尾芭蕉の人生観でもある「人生は旅のようなものだ」という姿勢と、これから旅をしようという心情が伝わってくる冒頭であり、序文となっています。
また、序文冒頭の一節「月日は百代の過客にして、行き交う年もまた旅人なり」の英語訳に関しては、日本学者のドナルド・キーン氏が、次のように翻訳しています。
The months and days are the travellers of eternity. The years that come and go are also voyagers.
冒頭の一節の「the travellers of eternity」の「eternity」は、「永遠」を意味し、「voyager」は、「(特に海路を使って)遠くへ旅をする人、航海者」を指します。
続く一文に出てくる「come and go」は「行き来する」という意味で、後半の「The years that come and go are also voyagers」とは、行き交う年もまた旅人だ、という意味になります。
英語版の『奥の細道』のタイトルは、『The narrow road to Oku』です。
ちなみに、「古人も多く旅に死せるあり」というときの「古人」いうのは、芭蕉が敬愛し、人生のなかで旅を生き、旅の途上で死んでいった、杜甫、李白、西行、宗祇らを指しています。
以上、『奥の細道』の序文の冒頭「月日は百代の過客にして」の全文と意味でした。