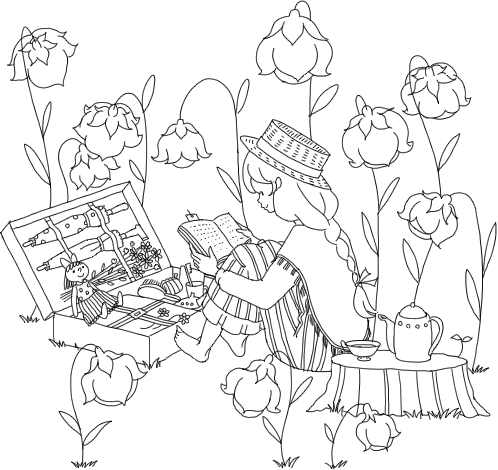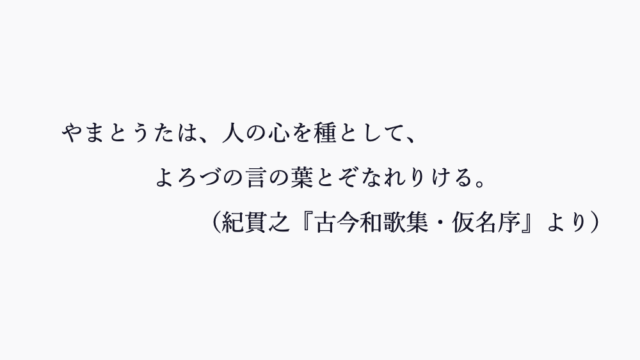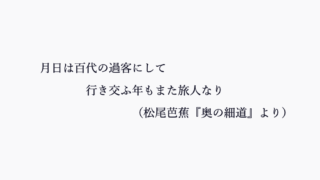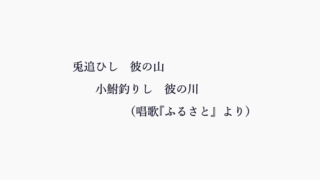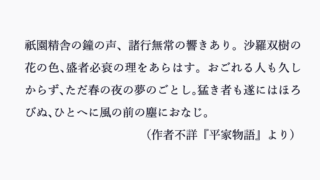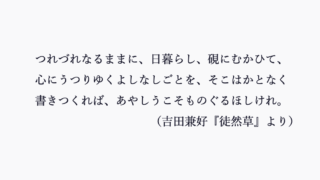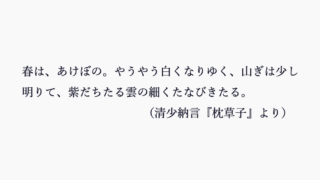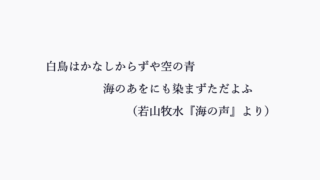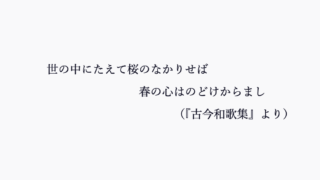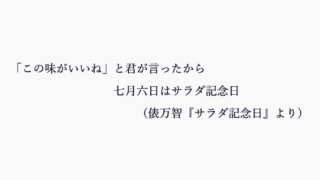松尾芭蕉〜行く春や鳥啼き魚の目は泪〜意味と季語
〈原文〉
行く春や鳥啼き魚の目は泪
〈現代語訳(句意)〉
過ぎゆく春の折に、旅立ちの別れを惜しんでいたら、鳥までも啼き、魚も目に涙を浮かべているではないか。
概要
作者の松尾芭蕉は、江戸時代前期の俳諧師で、代表作として、『おくのほそ道』があります。
おくのほそ道は、芭蕉が、晩年に弟子と行った、半年に渡る歩き旅に関する紀行文で、地の文の合間に、俳句も散りばめられています。
この「行く春や鳥啼き魚の目は泪」という句も、おくのほそ道のなかで詠まれている句で、描かれているのは、旅に出発する場面です。季節は春、特に晩春で、季語は「行く春」となります。
おくのほそ道では、序盤に、旅に出る前の情景や心境が描かれている段があり、この句も、いよいよ旅に出よう、というときの別れの悲しみや名残惜しさを詠んだ句です。
出発の日、夜明けの空は、おぼろげに霞み、有明の月の光は色褪せているものの、富士山がかすかに見えています。
上野や谷中など、江戸の桜の名所を、もう一度見ることができるのは一体いつになるだろうと、心細く、しんみりした心持ちになる芭蕉。
出発前夜には、親しくしている人たちもみんな集まり、翌朝、芭蕉の自宅がある深川から舟に乗って送ってくれ、千住(東京都の足立区)で下りると、これから長旅に出るのだと胸に込み上げるものがあり、別れを惜しんで涙を流し合いました。
そして、「行く春や鳥啼き魚の目は泪」と、過ぎ去っていくこの春に、旅の別れを惜しむ我々を囲んでいる鳥も鳴き、魚の目も涙で滲んでいるようだ、という心境になります。
この句によって旅は出発したものの、名残惜しさになかなか足は進まず、人々も道の真ん中に立ち並び、私たちの後ろ姿が見えなくなる限りは、と見送ってくれているようでした。
以下が、ちょうどその「旅立ち」の段になります。
弥生も末の七日、あけぼのの空朧々として、月は有明にて光をさまれるものから、富士の峰幽かに見えて、上野・谷中の花の梢、またいつかはと心細し。睦まじき限りは宵よりつどひて、舟に乗りて送る。千住といふ所にて舟をあがれば、前途三千里の思ひ胸にふさがりて、幻の巷に離別の涙をそそぐ。
行く春や鳥啼き魚の目は泪
これを矢立の初めとして、行く道なほ進まず。人々は途中に立ち並びて、後影の見ゆるまではと、見送るなるべし。
出典 : 松尾芭蕉『おくのほそ道』
あけぼのとは、夜明け方を指し、有明は、夜明けに空に残っている月のことです。また、巷とは、道の分かれる所、という意味です。
幻の巷とは、幻のように儚い世の中の分かれ道、という意味合いになります。
出発に当たり、これほどの悲しみが押し寄せたのは、松尾芭蕉が、この奥の細道の旅に出た年齢が46歳で、当時の平均寿命からすれば晩年に近いとも言える頃だった、ということもあったのかもしれません。
これが最後かもしれない、という思いから、いっそう、深い離別の悲しみとなったのでしょう。
この句の前、序文では、「草の戸も住替る代ぞひなの家」という句が置かれています。
これは、旅への準備の一環として、芭蕉が住んでいた家を譲り、新しく入る家族には女児がいると聞くから、雛人形も飾られることだろう、という意味の句です。
この句は、旅の前段階の話で、実際に旅が始まって最初の句は、「行く春や鳥啼き魚の目に泪」になります。
先の「旅立ち」の段で描かれているように、深川を出て、舟で千住に着いた芭蕉が、弟子たちと別れを惜しみ、旅を始めた場所というのは、隅田川に掛かる千住大橋のたもとで、その付近に現在ある、足立区立大橋公園には、おくのほそ道の矢立初の碑が建っています。
矢立てとは、携帯用の筆記道具であり、矢立ての初めで、旅の日記の書き始め、という意味合いになります。
ちなみに、この句の季節は春の終わりで、季語は「行く春」ですが、これは、奥の細道の旅の最後の句である「蛤のふたみに別れ行く秋ぞ(蛤のふたと身が別れるように、見送る人々と別れ、二見浦に出かけようとしている、晩秋という季節ゆえに別れがいっそう沁みる)」の「行く秋」と対応した構図となっています。