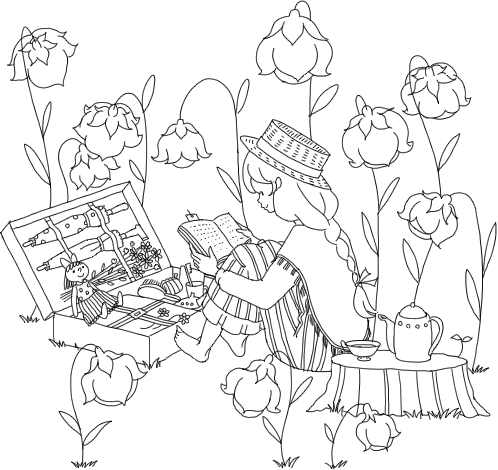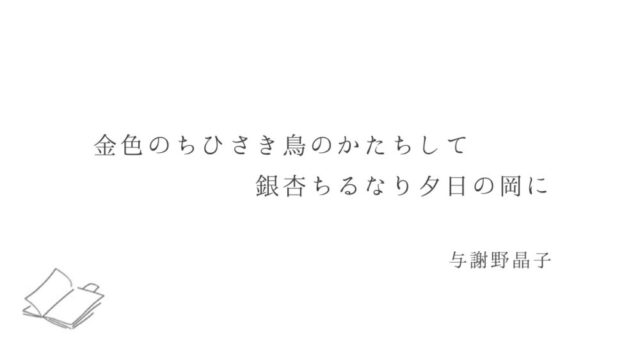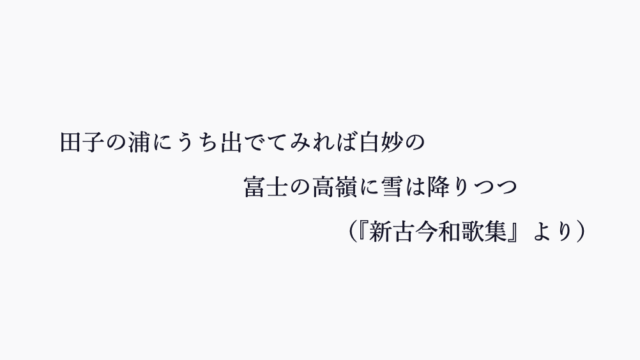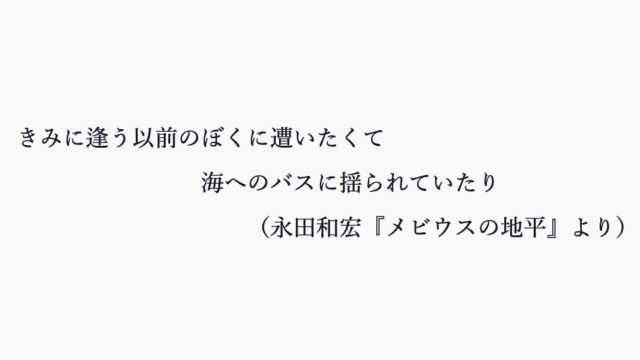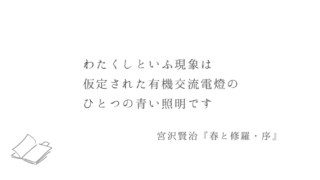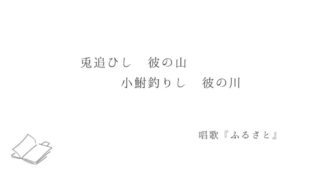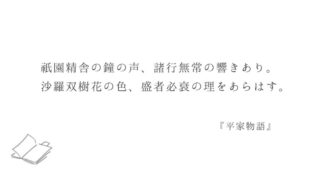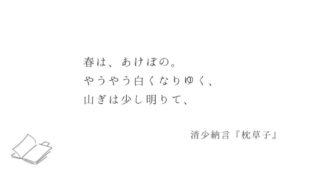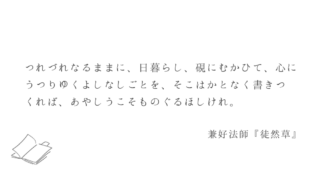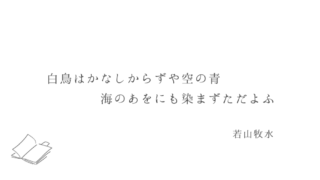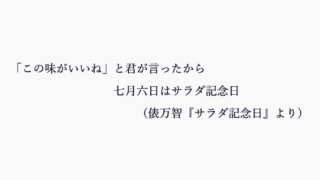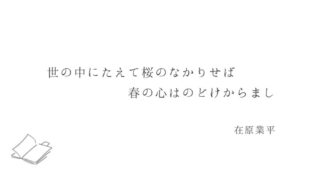村上龍『限りなく透明に近いブルー』の冒頭
飛行機の音ではなかった。耳の後ろ側を飛んでいた虫の羽音だった。
概要と解説
村上龍さんの『限りなく透明に近いブルー』は、1976年に出版された彼のデビュー作で、群像新人文学賞、芥川賞の受賞作品です。
単行本と文庫本の合計発行部数は350万部を越える大ヒットを記録します。
小説の舞台は、東京の福生市。主人公のリュウは、この街の通称「ハウス(福生市にある横田基地近くにある元米軍の住宅)」で、暴力やクスリ、米軍との交流に明け暮れ、そんな風に空虚に流れ、過ぎ去っていく頽廃的な日々が描かれた小説です。
思想家の内田樹さんは、この『限りなく透明に近いブルー』について、五感を刺激し、読者を作品世界に招き入れる文体だと言い、特に、一般的に小説の冒頭は、視覚情報で描写するのに対し、『限りなく透明に近いブルー』は、「音と匂いと手触りと舌で感じたもの」で多くが構成されている、と指摘しています。
触覚や嗅覚、味覚や聴覚に訴えかけるようなリアリティのある描写を書かれることで、ぐっと読者はその世界に引き込まれることになります。
この『限りなく透明に近いブルー』の冒頭も、「飛行機の音ではなかった。耳の後ろ側を飛んでいた虫の羽音だった」と、聴覚によって物語の世界が始まります。
確かに、「視界を一瞬横切るように小さな虫が飛んでいった」と視覚を頼った表現をするよりも、飛行機の音ではなく「耳の後ろ側を飛んでいた虫の羽音だった」とすることによって、より冒頭からいきなり没入できるかもしれません。