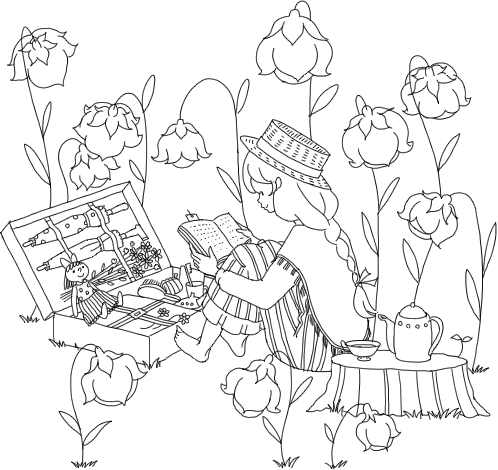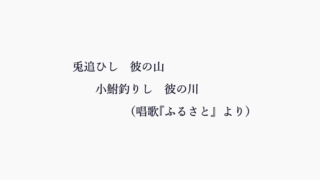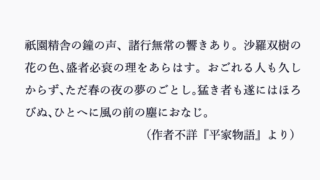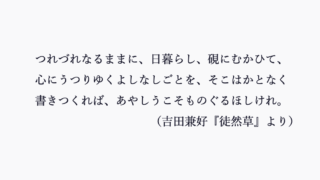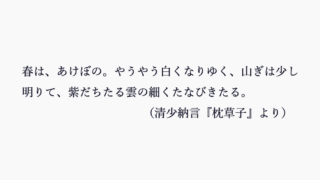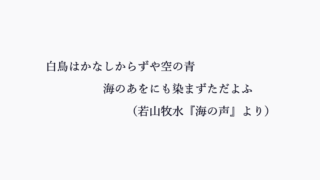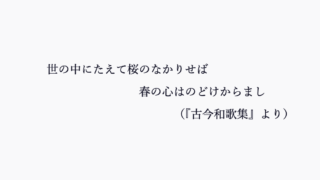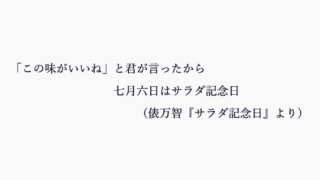坂口安吾『桜の森の満開の下』の名言
坂口安吾は、1906年(明治39年)に新潟で生まれ、1955年(昭和30年)に48歳で亡くなった小説家です。
本名は「坂口炳五」と言い、これは「丙午」年に生まれた「五男」であることに由来します。
安吾は、兄の影響で幼い頃から読書に親しむ一方、学校での成績は芳しくないものでした。
のちに『堕落論』を著したように落伍者への憧れも強く、中学での留年など、家族は安吾の態度を危惧します。
坂口安吾、というペンネームも、中学時代、勉強にやる気を持てなかった安吾に、当時の漢文の教師が、「お前に炳五などもったいない、柄は明るいという意味だが、お前は自己に暗いから、暗吾だ」と叱責したことから、のちに坂口安吾(暗をもじって安に)となります。
しかし、これと思ったものには深くのめり込む性格だった安吾。
友人らの影響から仏教への関心を強く持っており、「勉強をしない、自己に暗い暗吾」から一転、仏教や哲学については、勉強のしすぎによって神経衰弱に陥ったこともありました。
それを紛らわすためにまた別の勉強に熱中するなど、激しいエネルギーで人生に向き合い、評論や小説を書き続けます。
戦後、1947年に発表された『桜の森の満開の下』は、坂口安吾の代表作の一つとして知られる、文庫で約30ページほどの短編小説です。
ある山賊の男と、八人目の女房として奪ってきた美しい女。
二人が過ごした一年ほどの期間のなかで、唯一訪れる二回の「春」を、幻想的に、そしてグロテスクに描写した作品です。
この記事では、『桜の森の満開の下』から、名言や印象的なシーンをいくつか紹介していきたいと思います。
桜の花が咲くと人々は酒をぶらさげたり団子をたべて花の下を歩いて絶景だの春ランマンだのと浮かれて陽気になりますが、これは嘘です。
出典 : 坂口安吾『桜の森の満開の下』
作品の冒頭部分です。安吾は句読点の使い方が特徴的ですが、この冒頭の一文によって、文体の魅力に一気に引き込まれます。
山賊は始めは男を殺す気はなかったので、身ぐるみ脱がせて、いつもするようにとっとと失せろと蹴とばしてやるつもりでしたが、女が美しすぎたので、ふと、男を斬りすてていました。
出典 : 坂口安吾『桜の森の満開の下』
山賊と女が出会うシーンです。美しさのあまり、「ふと」殺人を犯す山賊の心変わりを、読者もなぜかすんなりと受け入れてしまいます。
けれども男は不安でした。どういう不安だか、なぜ、不安だか、何が、不安だか、彼には分らぬのです。女が美しすぎて、彼の魂がそれに吸いよせられていたので、胸の不安の波立ちをさして気にせずにいられただけです。
なんだか、似ているようだな、と彼は思いました。似たことが、いつか、あった、それは、と彼は考えました。アア、そうだ、あれだ。気がつくと彼はびっくりしました。
桜の森の満開の下です。あの下を通る時に似ていました。どこが、何が、どんな風に似ているのだか分りません。けれども、何か、似ていることは、たしかでした。彼にはいつもそれぐらいのことしか分らず、それから先は分らなくても気にならぬたちの男でした。
出典 : 坂口安吾『桜の森の満開の下』
女は山賊の家に着くなり、帰りを待っていた七人の女房のうち、六人を殺すよう命じます。ことが済み、われに返った山賊の男が自らの不安に気づくシーンです。
句読点の効果によって、男の思考をまざまざと感じることができます。
「桜の花が咲くから、それを見てから出掛けなければならないのだよ」
「どういうわけで」
「桜の森の下へ行ってみなければならないからだよ」
「だから、なぜ行って見なければならないのよ」
「花が咲くからだよ」
「花が咲くから、なぜさ」
「花の下は冷めたい風がはりつめているからだよ」
「花の下にかえ」
「花の下は涯がないからだよ」
「花の下がかえ」男は分らなくなってクシャクシャしました。
出典 : 坂口安吾『桜の森の満開の下』
山賊の男と美しい女の二人は、女中を連れて都へ行くことになります。今すぐに出発したい女と、恐怖を克服するため、満開の桜を一人で見にいってから出発したい山賊の男のやりとりの一部です。
彼は気がつくと、空が落ちてくることを考えていました。空が落ちてきます。彼は首をしめつけられるように苦しんでいました。それは女を殺すことでした。
出典 : 坂口安吾『桜の森の満開の下』
女が都で求めたのは「首」でした。山賊の男が、夜毎に人を殺しては、様々な身分の首を持ち帰り、女はそれで遊びます。
男は都での暮らしに疲れ、女との生き方の違いに苦悩します。
彼の呼吸はとまりました。彼の力も、彼の思念も、すべてが同時にとまりました。女の屍体の上には、すでに幾つかの桜の花びらが落ちてきました。彼は女をゆさぶりました。呼びました。抱きました。徒労でした。彼はワッと泣きふしました。たぶん彼がこの山に住みついてから、この日まで、泣いたことはなかったでしょう。そして彼が自然に我にかえったとき、彼の背には白い花びらがつもっていました。
出典 : 坂口安吾『桜の森の満開の下』
女は、一人で山へ帰ると行った男についていきます。しかし、満開の桜の下で、女の鬼の姿を見た男は、その首を絞めて殺してしまいます。
彼がその事実を目の当たりにし、悲しみをあらわにする瞬間です。
彼は女の顔の上の花びらをとってやろうとしました。彼の手が女の顔にとどこうとした時に、何か変ったことが起ったように思われました。すると、彼の手の下には降りつもった花びらばかりで、女の姿は掻き消えてただ幾つかの花びらになっていました。そして、その花びらを掻き分けようとした彼の手も彼の身体も延した時にはもはや消えていました。あとに花びらと、冷めたい虚空がはりつめているばかりでした。
出典 : 坂口安吾『桜の森の満開の下』
小説の結末のシーンです。
安吾はのちに、この小説の原体験として、東京大空襲について触れています。上野の山に死者を集め焼いた際、満開の桜が咲いていたそうです。
逃げ出したくなるような静寂がはりつめていたと安吾が表現する、その景色に思いを馳せるとき、「冷たい虚空」の風が、よりいっそう深く感られるのではないでしょうか。
以上、『桜の森の満開の下』より、印象的な言葉やシーンの紹介でした。