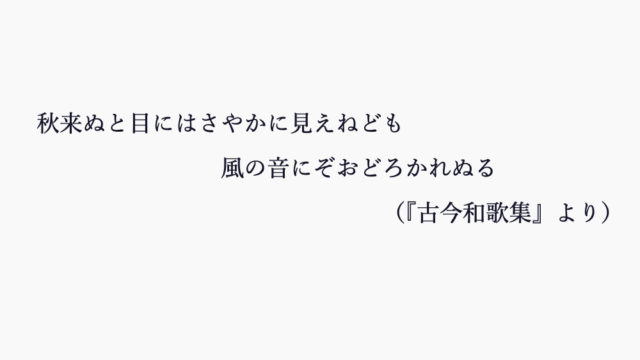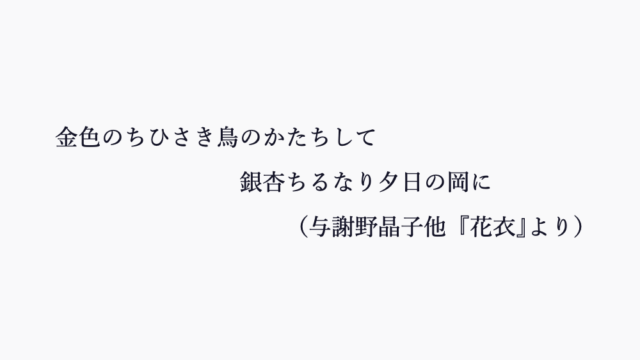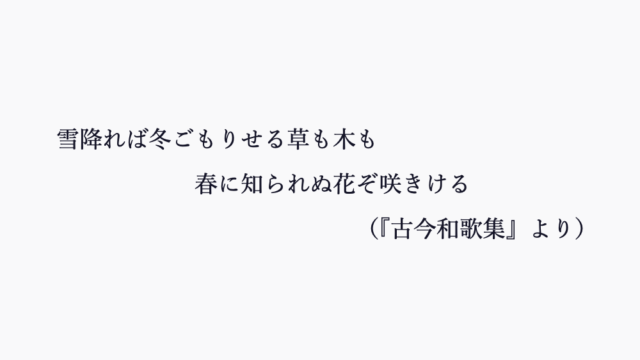ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは 在原業平
〈原文〉
ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは
〈現代語訳〉
神々の時代にさえ聞いたことがない、こんな風に竜田川一面に紅葉が散り敷かれ、流れる水を真紅に絞り染めしているなどということは。
概要
 狩野探幽『三十六歌仙額(在原業平)』
狩野探幽『三十六歌仙額(在原業平)』
作者の在原業平は、天長2年(825年)に生まれ、元慶4年(880年)に死没する、平安時代初期から前期の貴族であり歌人です。
和歌の名人の六歌仙、三十六歌仙の一人で、美男子として知られ、『伊勢物語』の主人公は、在原業平がモデルだったと考えられています。

この「ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは」という和歌は、
二条后(清和天皇の女御である藤原高子)の前で披露され、捧げられた作品で、『小倉百人一首』の他、『古今和歌集』『伊勢物語』に収録されています。
在原業平と藤原高子とされる男女が駆け落ちをする恋物語が、『伊勢物語』に収録されていることから、この二人は、かつて恋人関係にあったと言われています。
藤原高子は、当時力を持っていた藤原氏の娘で、清和天皇と結婚することが予定されていたことから、在原業平との恋愛は許されぬ恋であり、二人は駆け落ちを決意。しかし、駆け落ちは途中で失敗し、高子が連れ戻されてしまったと言われています。
さて、この歌は、実際の光景を見たのではなく、屏風を前にして詠んだものです。
秋の竜田川を、紅葉が流れていく様が描かれた屏風を前にして詠まれた和歌であり、『古今和歌集』の詞書には、「二条の后の春宮の御息所と申しける時に、御屏風に竜田川に紅葉流れたる形を描きけるを」とあります。
こんな風に、屏風に描かれた大和絵(日本の風景や、風俗を描いた絵)を主題にし、屏風絵に添えられる歌のことを、屏風歌と言います。
大和絵の多くは屏風に描かれて室内の装飾に用いられました。
絵には和歌(=屏風歌:びょうぶうた)が添えられており、その歌は能書家が清書したものでした。
屏風は絵と歌と書を同時に鑑賞できる芸術作品だったのです。
屏風歌は、平安時代に誕生したと考えられています。
この屏風歌として知られる、在原業平の「ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは」という歌。
現代語訳すると、「神々の時代にさえ聞いたことがない、こんな風に竜田川一面に紅葉が散り敷かれ、流れる水を真紅に絞り染めしているなどということは」という意味になります。
こんなに素晴らしい紅葉が敷き詰められた竜田川の様子は、神々の時代にも聞いたことはない、という風に、屏風に描かれている大和絵を前にして、半ば大げさに誇張して驚いているようにさえ伺えます。
新調した屏風絵に対し、祈りを込めるような想いで歌われたのではないか、という指摘もあり、祈りゆえに、いっそう誇張した表現になったのかもしれません。
それでは、和歌に出てくる語句などの意味に関して、順番に追って解説したいと思います。
冒頭の「ちはやぶる」とは、「神」にかかる枕詞で、「ちはやふる」とも言います。勢いの激しい様子を意味し、漢字では「千早振る」と書きます。
近年でも、『ちはやふる』というタイトルの競技かるたを題材にした漫画が有名で、この言葉を聞いたことがある、という人も多いのではないでしょうか。
この言葉に関しては、「ちはやぶる」か、「ちはやふる」か、どっちが正しいのか、濁っていることで違いはあるのか、といった疑問が湧くかもしれませんが、基本的に両者に違いはありません。
古くから、清濁が併存していたようです。
文法的にどっちが正しいという判定はできません。どっちも間違いではないというのが正解だからです。古く『万葉集』で枕詞として用いられているのですが、その漢字が統一されておらず、「千磐・破」「千早・振」「知波夜・布流」などさまざまに表記されています。そのうち「破る」は濁音ですが、「布流」は清音です。要するに『万葉集』の時点で、清濁両用が並存していたのです。もともと枕詞には意味不明のものも多いので、その方が納得できます。
それが平安時代以降、次第に清音の方に傾いていきました。室町時代の「日甫辞書」に「チワヤフル」とあるので、その頃清音で読まれていたことがわかります。それが江戸時代にも継承されたことで、落語は清音を踏襲しているのでしょう。ですから百人一首においても、清音で読まれていた時代はかなり長かったことになります。
ところが近代の『万葉集』研究の中で、勢いの強い・勇猛な意味を有する「ちはやぶ・いちはやぶ」が語源と考えられたことで、「破る」の方が選び取られ、濁って読む方が主流になったようです。最近の辞書など清音には一切ふれず、「ちはやぶる」だけで済ませているものも少なくありません。競技かるたの読みは、そういった時代背景の中で濁音になっているのではないでしょうか。
この「ちはやぶる」は、動詞形として、「千早ぶ」という言葉があります。千早ぶとは、「勢い激しく振る舞う、強暴になる」という意味です。
次の「神代」というのは、遠い昔、不思議なことが起こり得た神話時代のことを指し、「神代もきかず」とは、「神々の時代にも聞いたことがない」といった意味合いになります。
不思議なことがたくさん起こったであろう、神々の時代でさえも、聞いたことがないようなことが起こっている、ということです。
そのあとに続く、地名である「竜田川」とは、大和国(現在の奈良県)の生駒郡を流れる川のことで、紅葉の名所として知られています。
動画 : 竜田川の紅葉
紅葉の色を表現した、「からくれなゐ(からくれない)」とは、漢字で書くと「唐(韓)紅」と表記します。
唐紅は、「唐や韓の国など、大陸由来の紅」という意味です。
その頃の日本の染料では出せないような「真紅」を指します。屏風に描かれた、竜田川を流れる紅葉は、それほどまでに鮮やかで真っ赤な色だったのでしょう。
最後の「水くくるとは」の「くくる」というのは、絞り染めの技法で、「くくり染め」にすることを言います。
川を布に見立て、紅葉が散り敷かれる様を、くくり染めに喩えています。
布を部分的に、つまんで糸でくくって染め残しをつくり、いろいろの模様を染めること。また、そのように染めたもの。絞り染。くくしぞめ。くくし。
言わば、「水くくるとは」で、「川の水をくくり染めにしてしまうとは」という意味になります。
これは、竜田川を人間に見立てて主語にするという形で、擬人法を用いています。また、「神代もきかず」というのが「とは」に繋がることから倒置法も使われています。
この在原業平の「ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなゐに水くくるとは」という色鮮やかな和歌は、百人一首のなかでも有名な作品の一つです。