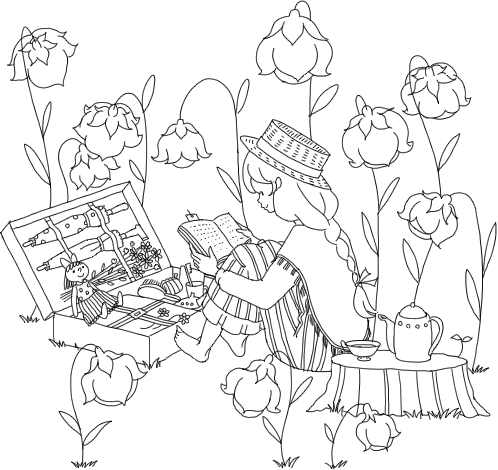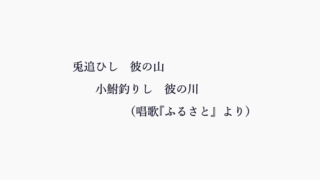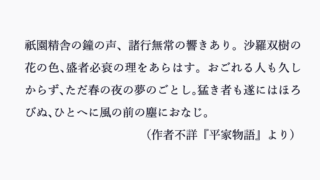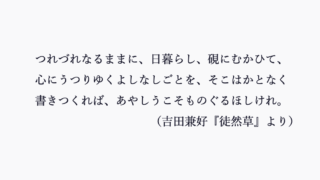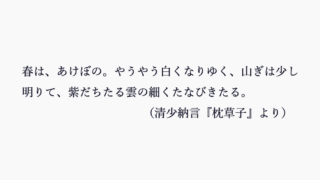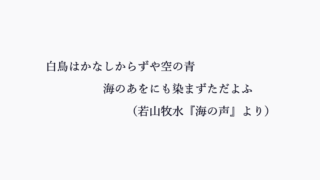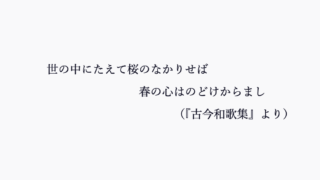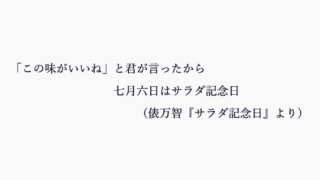福岡伸一「動的平衡」をわかりやすく解説
福岡伸一さんは、1959年生まれで、青山学院大学の教授を務める生物学者(専攻は分子生物学)です。
代表作としては、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞した、2007年刊行の『生物と無生物のあいだ』があります。
この著作も含め、福岡伸一さんが生命について述べる際に提示する概念に、「動的平衡」という考え方があります。
それでは、動的平衡とは、一体どういった考え方なのでしょうか。
この概念についてわかりやすく解説する際、福岡伸一さんは、「食べ物」を比喩として説明します。
我々人類も含め、生き物が食べ物を体内に取り入れるとき、「体が機械であり、食べ物が、その機械を動かすためのガソリン、エネルギーである」という仕組みが、一般的に思い浮かべるイメージではないでしょうか。
しかし、実際はそうではない、と福岡さんは指摘します。
ユダヤ人生物学者ルドルフ・シェーンハイマーの研究によれば、ねずみに識別可能な実験用の食物を与えた際、ねずみの体重は変化しなかったものの、食物のアミノ酸がねずみの体内に散らばっていた、とのこと。
要するに、食べ物が燃やされ、エネルギーとなり、燃えかすが排出される、というのではなく、「食べ物そのものが体になっていた」ということです。
シェーンハイマーは最初、当時の科学の常識通り、食べ物は燃やされてエネルギーを生み、燃えかすは二酸化炭素や汗や糞、尿になって体外に排泄されると考えていました。しかし、実験結果は、その予想を鮮やかに裏切ります。
赤い分子は、例えば尻尾の先、あるいは目、ヒゲ、耳、心臓、骨、肝臓というふうに瞬く間に全身に散らばり、それぞれの場所に溶け込んでしまったのです。
一方で、体重は変化していないということは、もともとあった組織が分解され、外に抜け、食事で摂取したものと置き換わっている、ということになります。
ねずみは、半年で体のタンパク質の半分ほどが入れ替わっていました。
人間の体も、一年も経てば、脳も心臓も骨も、分子レベルでは新たに置き換わっているそうです。
しかし、入れ替わっているにもかかわらず、「私」はそのまま保たれています。
すっかり「私」を構成するものは入れ替わっているのに、「私」は、私のまま続いている状態を、「動的な流れのなかで、平衡状態を保っている」、すなわち「動的平衡」と呼びます。
そして、福岡伸一さんは、「生命とは動的平衡にある流れである」と生命を定義付けします。
私達生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい『淀み』でしかない。しかもそれは高速で入れ替わっている。この流れ自体が『生きている』ということであり、常に分子を外部から与えないと、出て行く分子との収支が合わなくなる。
出典 : 福岡伸一『生物と無生物のあいだ』
この動的平衡という考え方は、鎌倉時代の随筆である鴨長明の『方丈記』に出てくる無常感とも通じるものがあるのではないでしょうか。

川の流れは、絶えることなく日々移り変わりながら、同時に「川」はいつまでも保たれている。
動的平衡は、古くからの日本人の考え方とも、よく馴染む概念なのかもしれません。
動画 : 動的平衡
この動画は、デザイナーの佐藤卓さんや中村勇吾さんらが製作した、「動的平衡」の概念をよりわかりやすく映像化したアニメーションです。
世界と自分に、はっきりとした境界線があるわけではなく、流れのなかで立ち現れ、またゆっくりと世界に溶けていく様が描かれています。
もう一度、この動画を見ながら、福岡さんの言葉を振り返ってみると、より「動的平衡」の理解が深まるでしょう。
生命体というのは、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい「淀み」で、しかもそれは高速で入れ替わっている。
この「流れ」自体が、生きている、ということであり、この「流れ」の部分こそが、生命体とロボットの大きな違いと言えるかもしれません。
生命体は、日々流れ、移り変わり、周囲の環境と共存しながら生きている。
一方のロボットは、世界から独立し、ある意味では不変なものとして存在する。
そんな風に考えると、生命とは「動的平衡にある流れである」とする定義も、しっくりくるのではないでしょうか。
体を構成している分子は私たちの所有物ではなく、実は「環境」のものです。つまり、分子のレベルで私たち生物は地球上のあらゆる生物、無生物とつながっているわけです。
こうした発想のもととなった戦前の研究者のシェーンハイマー(あらゆる褒賞から見放されたまま、1941年に43歳で謎の自殺)を、福岡さんは「20世紀最高の生物学者」と称しています。
以上、生物学者の福岡伸一さんが提示する「動的平衡」の解説でした。