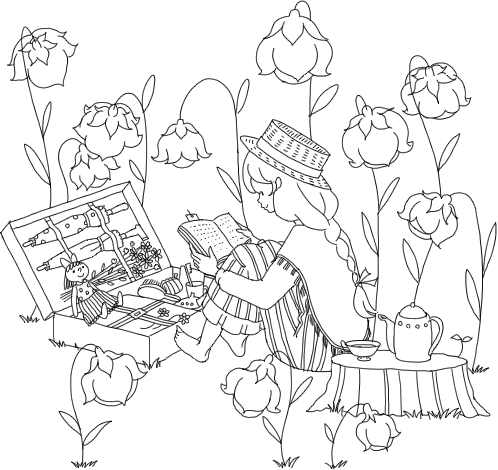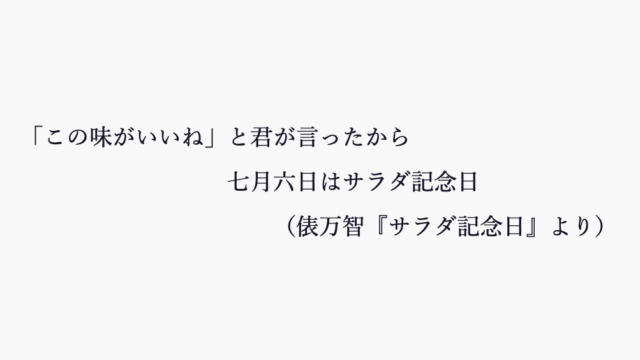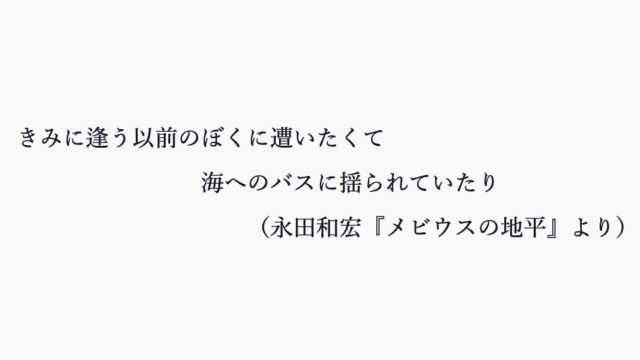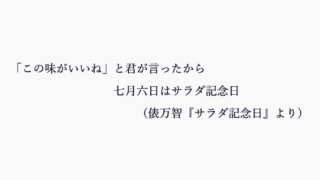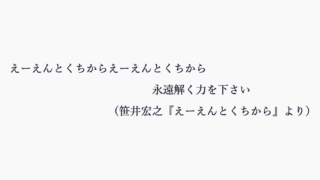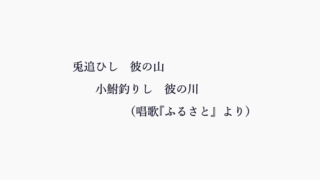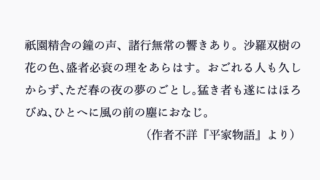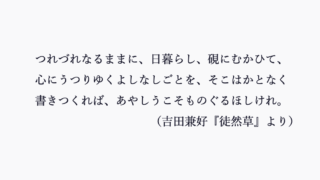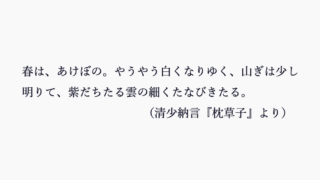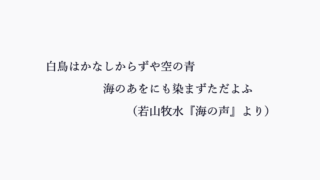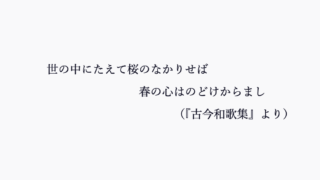島木赤彦〜隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり〜意味と解説
〈原文〉
隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり
〈現代語訳〉
隣の部屋で本を読んでいる子供たちの声を聞くと、その声が心に沁みて、ああもっと生きたいなあと、しみじみ思う。
解説
島木赤彦は、明治9年(1876年)、長野県に生まれ、大正15年(1926年)に49歳で亡くなるアララギ派の歌人です。
島木赤彦という名前はペンネームで、本名は久保田俊彦と言い、小学校の教師や校長を務めながら詩や短歌を投稿、その後、短歌雑誌『アララギ』を編集します。
短歌雑誌「アララギ」に拠る一派。万葉調と写生を主張し、大正、昭和、平成を通じて近代短歌の発展に貢献した。
歌集には、『馬鈴薯の花』『氷魚』『柿蔭集』などがあり、その他、歌論集や万葉集研究も残しています。
この「隣室に書よむ子らの声きけば心に沁みて生きたかりけり」という短歌は、作者晩年の作品が収録され、死後に刊行された『柿蔭集』に入っている歌です。
島木赤彦は、大正15年(1926年)1月に胃がんの診断を受け、郷里の長野で療養していました。この歌は、死の一ヶ月前に詠まれた「恙ありて」という連作のなかの一首です。
作中の「書」とは、本を意味し、この場合は教科書を指します。病で横になっているとき、隣の部屋から教科書を読んでいる子供たちの声が聞こえてくる。
その声が、深く心に沁みて、ああ、もっと生きたい、としみじみ思う、死期を悟った父親の気持ちが込められた歌です。