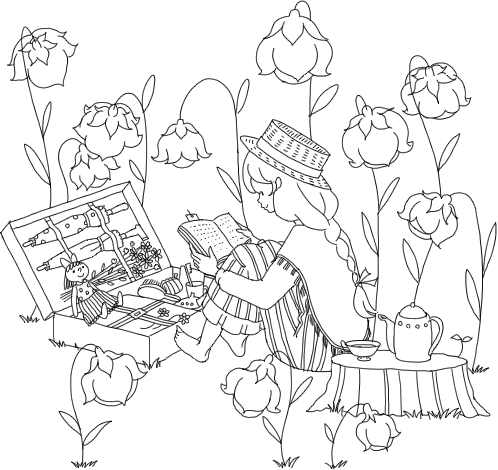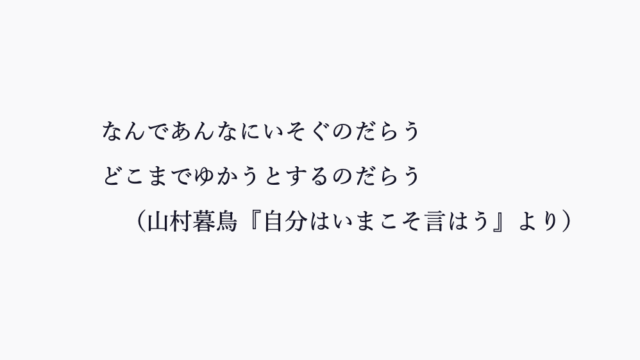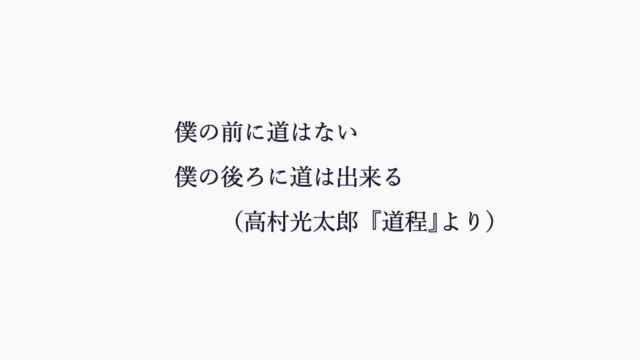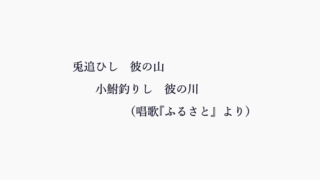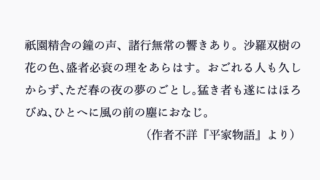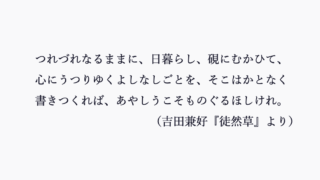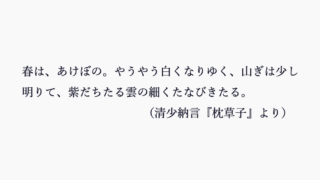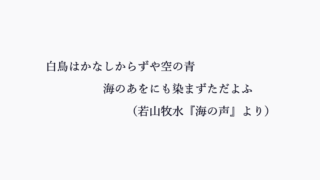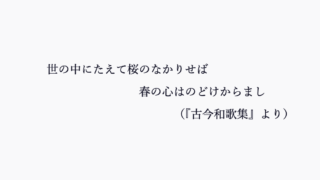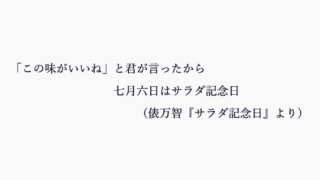長田弘『世界は一冊の本』
長田弘さんは、1939年に福島県で生まれ、2015年に亡くなった、日本の詩人です。
早稲田大学文学部に入学し、大学在学中に詩を書き始め、詩の雑誌の編集にも携わります。
長田弘さんのデビュー作は、1965年に出版された詩集『我ら新鮮な旅人』で、デビュー以降、詩集だけでなくエッセイ集なども出版し、詩人として長く活躍することになります。
長田弘さんの詩の特徴としては、平易な言葉が使われ、凛とした散文のような要素もあり、読みやすい文章になっています。また、その読みやすさによって詩の世界に招き入れながら、読み終わる頃には、この世界を違った形で見せてくれる、ある意味、旅のような魅力があります。
中学生や高校生でも読みやすい表現で、普段あまり詩を読んだことがない人や、詩に苦手意識のある人でも、詩集をあげたいと思ったときに、長田弘さんの詩集はおすすめの書籍だと思います。
長田弘さんの詩に関する本で、たとえば、死別の悲しみに寄り添ってくれる一冊として、『詩ふたつ』というタイトルの詩画集があります。
 長田弘『詩ふたつ』
長田弘『詩ふたつ』
この本は、長田弘さんの『花を持って、会いにゆく』『人生は森の中の一日』という二つの詩と、19世紀後半から20世紀にかけてのオーストリアの画家グスタフ・クリムトの絵が、絶妙に調和した詩画集です。
長田弘の「絆」の詩篇に、クリムトの樹木と花々。人生のなかでときに訪れる悲しみに、静かにそっと寄り添う、とてもやさしくあたたかい詩画集です。
この詩も、使っている言葉や文章自体は分かりやすい表現でありながら、喪失の深い悲しみに優しく寄り添ってくれる、心に沁みる詩篇となっています。
これは、童話のような世界観も広がる、『人生は森の中の一日』という詩の一部です。
やがて とある日
黙って森を出てゆくもののように
わたしたちは逝くだろうわたしたちが死んで
わたしたちの森の木が
天を突くほど 大きくなったら大きくなった木の下で会おう
わたしは新鮮なイチゴを持ってゆく
きみは悲しみをもたずにきてくれその時 ふりかえって
人生は森の中の一日のようだったと
言えたら わたしはうれしい出典 : 長田弘『詩ふたつ』
決して難解な言い回しはせずとも、この世界や人間の深い場所まで触れる表現になっています。
それから、長田弘さんの代表作の一つに、「本を読もう」という一見シンプルなメッセージで始まる、『世界は一冊の本』という詩があります。
本を読もう、というだけだと、なんだかまるで読書キャンペーンのようですが、長田弘さんの詩は、その後に続く展開によって、「本を読む」という言葉の世界がどんどんと広がっていきます。
詩の朗読を趣味にしている人もいるかもしれませんが、この詩は、朗読にもおすすめの作品だと思います。
以下は、長田弘さんの『世界は一冊の本』という詩の全文になります。
世界は一冊の本
本を読もう。
もっと本を読もう。
もっともっと本を読もう。書かれた文字だけが本ではない。
日の光り、星の瞬き、鳥の声、
川の音だって、本なのだ。ブナの林の静けさも、
ハナミズキの白い花々も、
おおきな孤独なケヤキの木も、本だ。本でもないものはない。
世界というのは開かれた本で、
その本は見えない言葉で書かれている。ウルムチ、メッシナ、トンブクトゥ、
地図のうえの一点でしかない
遥かな国々の遥かな街々も、本だ。そこに住む人びとの本が、街だ。
自由な雑踏が、本だ。
夜の窓の明かりの一つ一つが、本だ。シカゴの先物市場の数字も、本だ。
ネフド砂漠の砂あらしも、本だ。
マヤの雨の神の閉じた二つの眼も、本だ。人生という本を、人は胸に抱いている。
一個の人間は一冊の本なのだ。
記憶をなくした老人の表情も、本だ。草原、雲、そして風。
黙って死んでゆくガゼルもヌーも、本だ。
権威をもたない尊厳が、すべてだ。200億光年のなかの小さな星。
どんなことでもない。生きるとは、
考えることができるということだ。本を読もう。
もっと本を読もう。
もっともっと本を読もう。出典 : 長田弘『世界は一冊の本』
本という空間を、決して紙の書物に閉じ込めるのではなく、この世界の広さや細部の美しさにまで広げていきます。
その「本」である世界の美しさは、日の光や星の瞬き、鳥の鳴き声、木々や花々など、自然の豊かさだけではありません。
普段は馴染みのない海外の街(ウルムチ、メッシナ、トンブクトゥ)、そして、その街の雑踏や夜の灯りも本で、シカゴの先物取引の数字も、砂漠も、マヤの雨の神さまも、一人の人間も、記憶をなくした老人の表情も本です。
これは、この世界を生きるということが、本を読んでいくようなものであり、また次々に新しい本を読むことでもあり、自分も誰かにとっての一冊の本である、という捉え方もできるでしょう。
そして、そのとき、社会的に価値があるから良い本だ、ということもなく、ただ、その一冊の本として、世界も自分も目の前の風景も尊い、ということを、意味として含んでいるのかもしれません。
詩のなかでは、「200億光年のなかの小さな星」という一節も登場します。
谷川俊太郎さんの『二十億光年の孤独』というのは、この詩が書かれた1950年頃に考えられていた宇宙の直径に由来するタイトルですが、「200億光年」という数字も、詩が発表された頃に言われていた宇宙の広さを表しているのかもしれません。
この宇宙のなかの小さな星、そのなかで生きる。
生きるということは、考えるということで、それはすなわち、この世界の一つ一つをよく観察し、体験する。出会い、別れる。その喜びや悲しみや美しさも含めて、人生で出会う無数の本を大切に、もっともっと読んでいこう、ということなのでしょう。
生きていく、という、ともすれば何気なく過ぎ去っていく行為を、彩りのあるものに見せてくれる詩です。