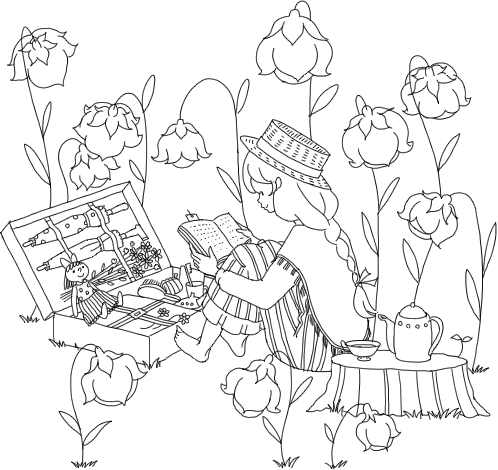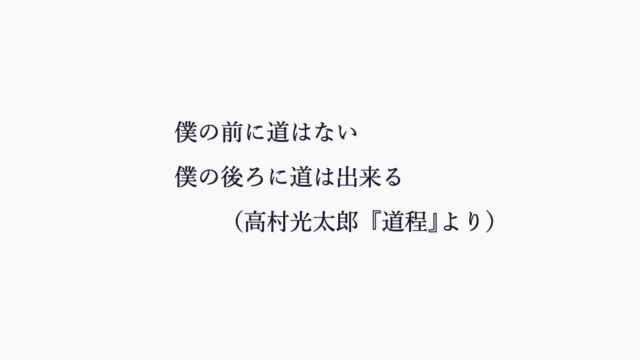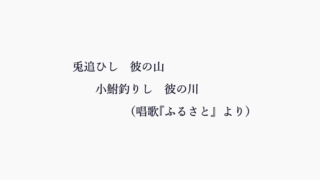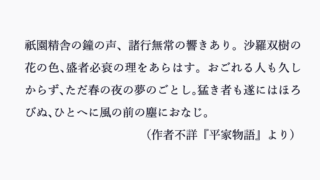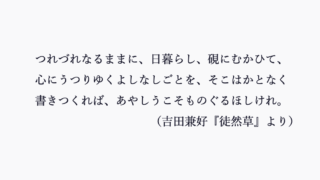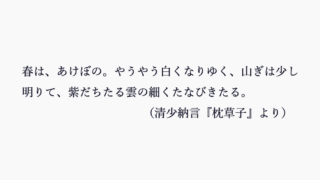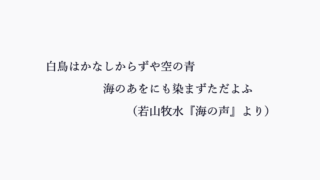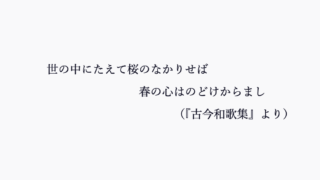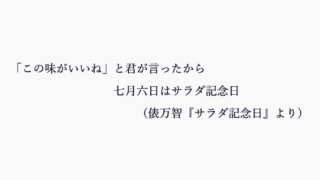谷川俊太郎『二十億光年の孤独』 意味と解説
詩人、谷川俊太郎
現代日本のもっとも有名な詩人の一人として、谷川俊太郎さんが挙げられます。
文学や詩に興味がない人でも、一度は名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。
谷川俊太郎さんは、1931年に東京で生まれ、1948年から詩作を開始。谷川さんの作品は、英語やフランス語、中国語など数多くの言語に翻訳され、世界中に読者を持っています。
詩だけでなく、絵本作家や翻訳家の面もあり、エッセイも含めて、たくさんの著作を残しています。谷川さんの翻訳としては、絵本で言えば、レオ・レオニ作の『スイミー』や『フレデリック』などが挙げられます。
また、「空をこえて ラララ 星のかなた」で始まる『鉄腕アトム』の主題歌の歌詞も、谷川さんが書くなど、幅広い分野で執筆活動を行なっています。
その谷川俊太郎さんの処女作が、1952年、21歳のときに出版された、『二十億光年の孤独』です。
この『二十億光年の孤独』というのは、詩集のタイトルであるとともに、同名の作品も掲載されています。
詩集には、谷川俊太郎さんが、17歳のときから書いてきた詩が収録され、詩集の序文には、法政大学の総長でもあった哲学者の父の友人であった、詩人の三好達治が文章を寄せています。
もともと、高校卒業後、大学進学はせずに、趣味の模型飛行機作りとラジオの組み立てと詩作に没頭していた折に、父親から、将来はどうするつもりかと問われた谷川さん。書きためていた詩のノートを見せると、その作品に父親は衝撃を受け、友人の三好達治にそのノートを送ります。
結果、三好達治の推薦で、谷川さんの詩が文芸雑誌に掲載されることとなります。
そういった縁があり、デビュー作である、『二十億光年の孤独』の序文も、三好達治が書いたのでしょう。
この『二十億光年の孤独』という詩は、教科書にも掲載され、また、基本的には歌詞も同じ合唱曲にもなるなど、多くの人に知られる谷川俊太郎さんの代表作の一つです。
以下は、『二十億光年の孤独』の詩の本文とともに、作品の意味や内容の解説になります。
『二十億光年の孤独』とは
そもそも、この『二十億光年の孤独』という詩は、隠喩のような言葉が並び、意味や解釈に悩むかもしれません。
決して分かりやすく読める詩ではなく、意味を理解しようと思うと、なかなか難しい作品だと思います。
まず、『二十億光年の孤独』の全文を紹介します。
二十億光年の孤独
人類は小さな球の上で
眠り起きそして働き
ときどき火星に仲間を欲しがったりする火星人は小さな球の上で
何をしてるか 僕は知らない
(或いは ネリリし キルルし ハララしているか)
しかしときどき地球に仲間を欲しがったりする
それはまったくたしかなことだ万有引力とは
ひき合う孤独の力である宇宙はひずんでいる
それ故みんなはもとめ合う宇宙はどんどん膨らんでゆく
それ故みんなは不安である二十億光年の孤独に
僕は思わずくしゃみをした出典 :谷川俊太郎『二十億光年の孤独』
冒頭、人類は小さな球の上で、眠り、起き、働く、という日常が描かれます。この小さな球というのは、地球のことでしょう。
地球は人間から見たら大きいものの、「小さな」と表現していることから、この詩の視点が宇宙規模である、ということが分かります。
地球でさえも、小さく、孤独にぽつんと存在している星で、人類は、その地球の上で、生活を営み、また、ときどき火星に仲間を欲しがったりする、と書きます。
このときの「火星」というのは、本当の火星というだけでなく、もしかしたら、自分の理解し得ない「他者」のことを意味しているのかもしれません。
それから、続く、火星の描写では、火星もまた小さな球であり、火星人がなにをしているか、僕は知らない、とあります。
火星という、地球とは別の星には、自分が全く知らない世界が広がっています。
そして、この『二十億光年の孤独』のなかでも特に印象的なフレーズとして、「ネリリし、キルルし、ハララしている」という表現が出てきます。
この「ネリリ」や「キルル」や「ハララ」というのは、一体どういった意味でしょうか。
これは、自分の理解し得ない言葉である「火星語」を表現したもので、詩の冒頭にある地球の様子の描写と比較すると、「ネリリ」が「寝る」、「キルル」が「起きる」、「ハララ」が「働く」と対になっているのでしょう。
確かなことは分からないものの、地球人が行うような、寝て、起きて、働く、ということと同じことが、火星でも起こっているのだろうか、という意味合いなのかもしれません。
しかし、そんな風に、何をしているか分からない、火星に住んでいる人でも、これだけは「たしかなこと」として、「ときどき地球に仲間を欲しがったりする」という点を挙げます。
地球人が、ときどき火星に仲間を欲しがるように、火星人も、ときどき地球に仲間を欲しがる。
すなわち、地球の上に住んでいる人も、火星の上に住んでいる人も、孤独であることは変わらず、ときどき仲間を欲しがるんだ、ということです。
これは、先ほども触れたように、それぞれの星というものが「私」と「誰か」の比喩である、という視点で捉えてみてもいいかもしれません。
この宇宙のなかで、地球という孤独で小さな星と、隣にある、火星という孤独で小さな星。厳密には、お互いの気持ちは分からず、言葉も正しくは通じない。どこまで行っても、「かもしれない」という程度にしか分からない。それでも、「ときどき仲間を欲しがったりする」ことだけは確かなのだ、と。
それから、万有引力は、ひき合う孤独の力だ、という一節が入ります。
万有引力とは、ニュートンによる、「物体は互いに引きつけあう力が働いている」という考え方で、この万有引力を、谷川俊太郎さんは、孤独ゆえに引き合う、という形で詩的に表現します。
宇宙がひずんでいる、というのは、アインシュタインの相対性理論から出た言葉で、宇宙の原理としての万有引力やひずみによって、人々は孤独になり、それゆえに引き合い、求め合うものなのだ、ということでしょうか。
谷川俊太郎さんは、この世界というのは、人が孤独になり、そして、それゆえに引き寄せ合う、求め合う、そういう構造になっている、ということを表現したかったのかもしれません。
また、宇宙はどんどん膨らんでいる、それゆえに不安だ、と書きます。1929年に、アメリカの天文学者のハッブルの研究により、宇宙が膨張している、ということが言われるようになります。
宇宙が膨張しているゆえに、人々は徐々に孤独感が増し、それゆえにいっそう不安になっていく、ということを表現しているのでしょう。
谷川俊太郎さんが、この『二十億光年の孤独』を書いた当時の天文学では、宇宙の直径は、20億光年と言われていたようです。1光年というのは、秒速30万キロメートルで飛ぶ光が、1年で進む距離という意味です。
20億光年というのは、光の速度で20億年かかることを意味し、文字通り天文学的な長さで、この『二十億光年の孤独』という詩のタイトルも、その宇宙の直径である20億光年という数字が由来になっています。
それほどの途方もない世界や孤独の深さ、すなわち、「二十億光年の孤独」のことを考えながら、最後に、「僕は思わずくしゃみをした」という形で、ある種、気の抜けたような言葉によって詩が終わります。
この「くしゃみ」という表現も、印象的な面白い言葉の使い方です。
詩の最後に持ってきた「くしゃみ」は、作品を受け取るにあたって、どんな効果をもたらすのでしょうか。
宇宙規模の描写と、どんどんと孤独になっていくような、この世界で、「くしゃみ」というのは、極めて現実的で身体的な事象であり、日常的な生理作用でもあります。
そのため、読んでいても、「くしゃみ」によって、ふと我に帰ったように、自分のもとに引き戻される効果が生まれます。
この「くしゃみ」を、どのように解釈するかは人それぞれでしょうが、「今ここ」に戻ってきたような安心感もあれば、この宇宙全体の、ただ一人の自分ということの孤独性を、より際立たせる表現になっているとも言えるかもしれません。
谷川俊太郎さん本人は、小学生の「なぜ、くしゃみなの?」という質問に、「宇宙は大きい。くしゃみは小さい。その対比が面白いと思ったんです。」と回答しています。
全ての理由を語っているわけではないかもしれませんが、膨張していく宇宙や、孤独感に入り込んだ世界から、唐突に夢から覚めるような、宇宙よりも地球よりも、さらに小さな、「くしゃみ」という個人の身体の日常的な出来事、という対比が描きたかったというのは、大きな理由としてあるのでしょう。
加えて、誰かが自分の噂話をしているとくしゃみが出る、といった話がありますが、このくしゃみも、噂をしている誰かがいる、という意味で、孤独ではない面も仄めかしているのかもしれません。
また、「孤独」というと、絶望的な重々しさを孕んでいるテーマですが、谷川さんの詩は、「ネリリ」や「キルル」や「ハララ」という表現にせよ、くしゃみにせよ、あまり悲壮感がありません。
詩人が、詩によって孤独を表現するとなると、もっと悲しみや、季節の風物に思いを込める、といったこともあるでしょう。
しかし、『二十億光年の孤独』では、この「孤独」というものに対し、谷川さん自身がそれほど深刻に捉えず、あまり私情も挟まずに、少し遠めから、澄んだ眼差しで眺めている、といった特徴が見られます。
宇宙のことについて知っていくにつれ、なるほど、それゆえに人間は孤独なのか、孤独感を覚えるのか、繋がりたくなるのか、ということを詩的な眼差しで解析している、といった冷静な俯瞰の眼差しが、作品の独特な魅力に繋がっていると言えるかもしれません。
以上、谷川俊太郎さんの代表作『二十億光年の孤独』の意味と解説でした。