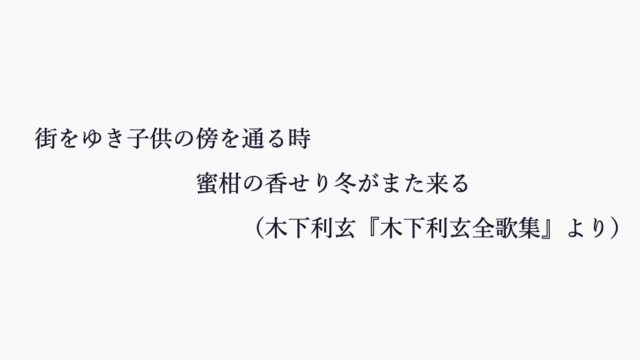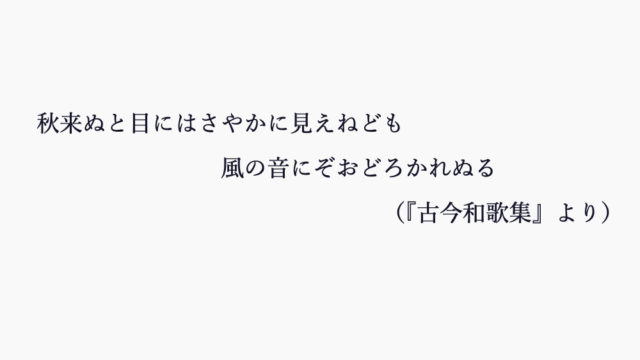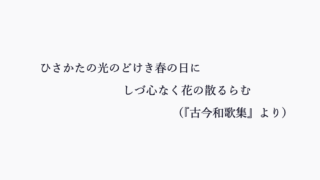春過ぎて夏来たるらし白妙の衣干したり天の香具山〜意味と現代語訳〜
〈原文〉
春過ぎて夏来たるらし白妙の衣干したり天の香具山
〈現代語訳〉
春が過ぎ、夏が来たようです。(夏の青葉に包まれた)天の香具山のあたりに、白い衣が干されていますね。
概要と解説
奈良時代末期に成立したと見られる日本最古の和歌集『万葉集』の歌で、作者の持統天皇は、大化の改新を行なった天智天皇(中大兄皇子)の第二皇女です。
天智天皇が亡くなった後、672年に、皇位継承をめぐって生じた、大海人皇子(のちの天武天皇)と、天智天皇の子の大友皇子のあいだの内乱「壬申の乱」で、夫の軍に従って、ともに戦い、天武天皇が即位すると、皇后となります。
そして、夫の死後、自ら即位し、持統天皇は女帝となります。
このとき、持統天皇は、皇室史上3人目の女帝でした(史上最初の女帝は、推古天皇です)。
持統天皇は、645年(大化元年)頃に生まれ、703年(大宝2年)に亡くなったとされ、『万葉集』では、長歌二首、短歌四首を残している万葉歌人でもあります。
その持統天皇の和歌として代表的な作品が、「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣干したり天の香具山」です。
持統天皇即位後に遷都した藤原京から、東南の方角にある香久山を眺め見て詠んだ歌です(参照 : 香具山|かしわら探訪ナビ)。
現代語訳すると、「春が過ぎ、夏が来たようです。(夏の青葉に包まれた)天の香具山のあたりに、白い衣が干されていますね。」という意味合いの歌になります。
以下、和歌の部分部分を追っていきたいと思います。
まず、最初の「春過ぎて夏来たるらし」というのは、「いつの間にか春が過ぎ、夏が来たようだ」という意味になります。
春が過ぎ、夏至が今まさに訪れる、ちょうど季節としては春から夏のあいだにかけての頃でしょうか。ああ、もう夏が来るなぁ、という頃です。
次の「白妙」とは、カジノキやコウゾの皮の繊維で織った白い布を意味します。
この「白妙の衣干したり」から、白い布の衣を干している様子が伺えます。
この布は、神事のときに着る白い布と考えられ、夏になると干す習わしがあったようです。
持統天皇の御製で万葉集の中でもよく知られる歌。白妙の衣は、神事に関する白い衣のことと思われ、神聖な香具山の風物により季節の移り変わりを詠んだ歌とされる。
春から夏にかけての季節の移り変わりを、干されている白い衣の光景によって表現したのでしょう。
最後の「天の香具山」とは、奈良県橿原市にある山で、「大和三山」の一つです。
大和三山(香久山、畝傍山、耳成山)のなかで、香具山は、もっとも神聖視されている山で、「天の」とつくのは、「天から降りてきた山」と言われることに由来します。
古代から「天」という尊称が付くほど三山のうち最も神聖視された。天から山が二つに分かれて落ち、一つが伊予国(愛媛県)「天山」となり一つが大和国「天加具山」になったと『伊予国風土記』逸文に記されている。
また『阿波国風土記』逸文では「アマノモト(またはアマノリト)山」という大きな山が阿波国(徳島県)に落ち、それが砕けて大和に降りつき天香具山と呼ばれたと記されている、とされる。
天の香久山は、標高152. 4メートルと、それほど高くはありません。
天から降ってきたという伝説だけでなく、天の岩戸の神話の舞台にもなっています(参照 : 天の岩戸と七本竹|奈良のむかしばなし)。
また、甘橿明神という神さまが存在し、人間の言動の真偽を確かめるために、香具山で神水に濡らした衣を干した、という伝承もあります。
他にも、畝傍山を女性に見立て、耳成山と香具山が奪い合ったという話も残っているそうです。
香具山は、先ほども触れたように、神聖な山として「天の」という言葉が冠につけられ、神事用の衣を干すのにふさわしい場所とされていたようです。
そのため、干されている「白妙の衣」とは、神事のときに着る斎衣と考えられていますが、その他、季節の変わり目の衣替え説や、初夏に咲く卯の花の比喩といった説などもあります。
いずれにせよ、持統天皇は、藤原京から香具山を眺め、夏になると干されるというこの白い衣の並んでいる光景を眺めながら、夏の訪れを思ったのでしょう。
ちなみに、『新古今和歌集』では、「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣干したり天の香具山」ではなく、「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山」という形で残っています。
この「来にけらし」とは、「けるらし」の縮まった形で、同じように「夏が来たらしい」という推測の意味になります。
ほとんど意味に違いはありませんが、「来にけらし」のほうが、優美な表現となっています。
もう一つ、「干したり」と「干すてふ」では、「干したり」のほうが、実際に目にしているだろう干されている情景を描き、より写実的になります。これが「干すてふ」となると、伝聞の意味合いになります。
百人一首では、後者の「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山」が収録されています。
また、季節の推移を詠むという意味だけでなく、四季が滞りなく巡るということは、すなわち、季節を支配する天皇の政治がうまくいっている、ということの証でもあったようです。
こうした点からも、この歌は、ただの季節の訪れというだけでなく、天皇の為政者としての姿を描いたものでもあり、だからこそ、百人一首でも、一番最初の天智天皇の次に持ってこられたのでしょう。
以上、持統天皇の和歌「春過ぎて夏来たるらし白妙の衣干したり天の香具山」の意味と現代語訳でした。