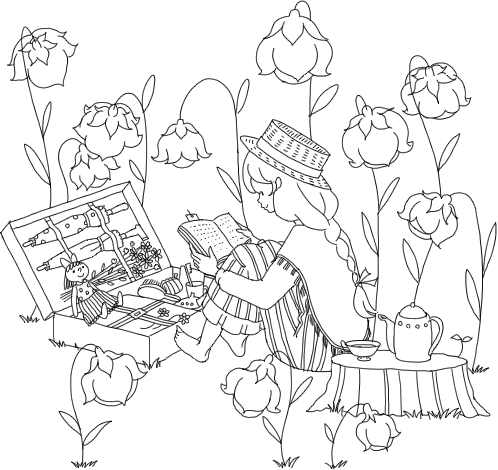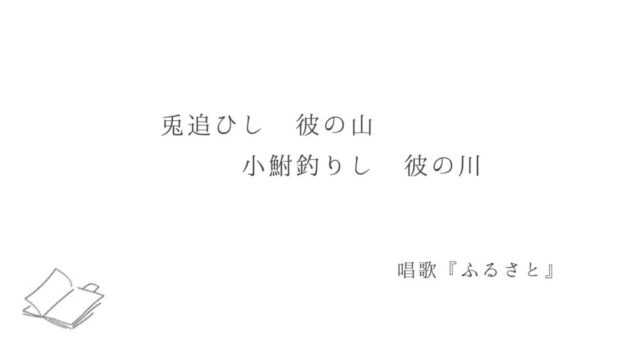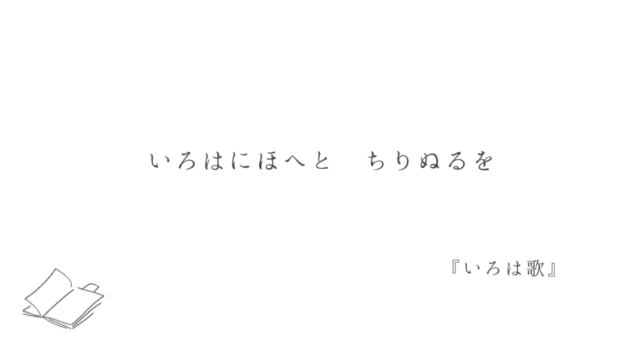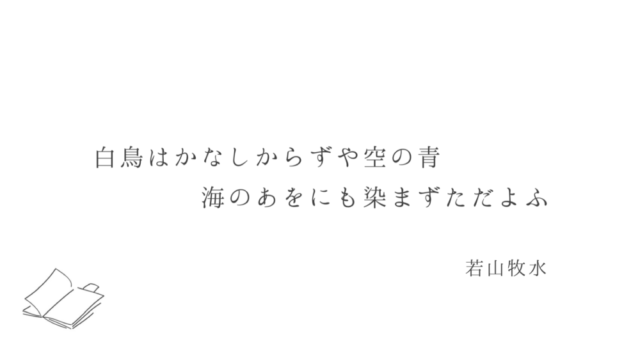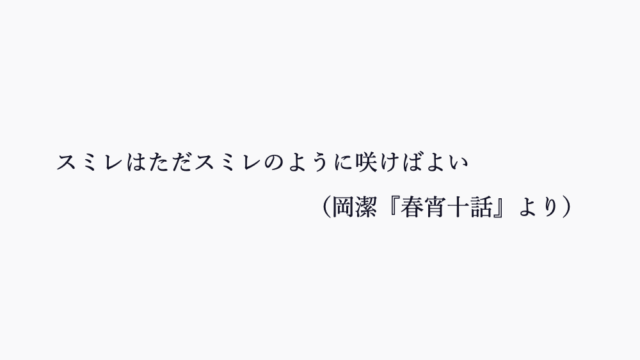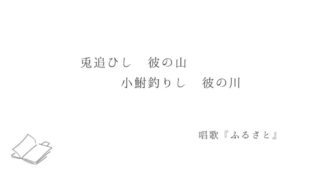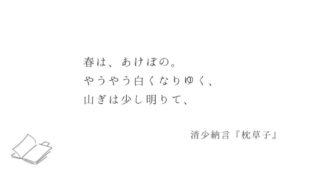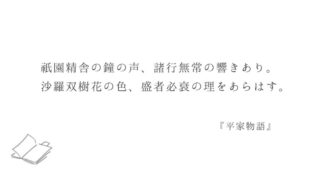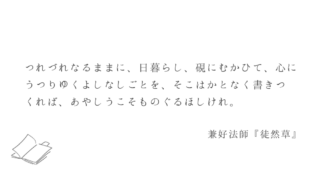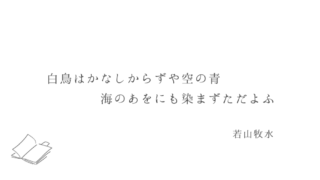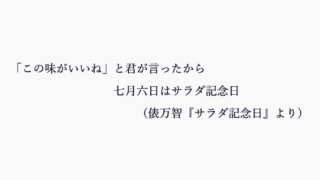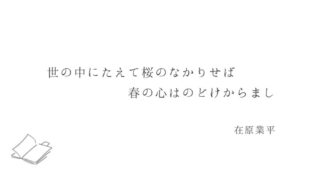レイチェル・カーソンの名言
レイチェル・カーソンとは
レイチェル・カーソンは、1907年にアメリカのペンシルベニア州に生まれ、晩年の1960年代に、環境問題を告発したことで有名な生物学者です。
農薬に使用されている化学物質の危険性を取り上げた、レイチェル・カーソンの代表作『沈黙の春』は、アメリカで多くの人に読まれ、世界中で環境問題を考えるきっかけを与えた一冊となります。
幼少期は文学少女で、もともと作家を目指していたレイチェル・カーソンは、大学時代に受けた生物学の授業で、生物学に魅せられ、科学者を志して大学院に進みます。
その後、アメリカ連邦漁業局・魚類野性生物局の公務員として勤務。海洋生物学に関わり、海に関連する著作を出版。
その後、1962年、癌の宣告を受けながら執筆し、発表された作品が、『沈黙の春』です。
この本の発表によって、レイチェル・カーソンは、業界団体から激しいバッシングを受けます。しかし、彼女の言葉は、環境保護運動の大きな起点となります。
動画 : 映画『レイチェル・カーソンの感性の森』予告編
レイチェル・カーソンの本では、『沈黙の春』が代表作として知られていますが、もう一つ、彼女の残した有名な言葉に「センス・オブ・ワンダー」というフレーズがあり、同名のタイトルの『センス・オブ・ワンダー』というエッセイ集が、彼女の遺作として、死後、友人たちの手によって出版されます。
レイチェル・カーソンは、毎年夏の数ヶ月を、姪の息子である幼いロジャーと一緒にメーン州の美しい海岸や森で過ごし、星空や鳥の鳴き声、風の音に耳を澄ませます。
そして、そのときの情景や、ロジャーの反応を詩的に綴った短いエッセイ集が、『センス オブ ワンダー』です。
この「センス・オブ・ワンダー」とは、「神秘さや不思議さに目を見張る感性」を意味します。
彼女は、自然に対し、その神秘さや不思議さに驚き、感動する感性=センス・オブ・ワンダーこそが、子供たちにとっても、また、大人にとっても尊い、心の拠り所になると考えたのです。
以下、『センス・オブ・ワンダー』と『沈黙の春』より、個人的に好きだなと思った「名言」を紹介したいと思います。
『センス・オブ・ワンダー』の名言
まず、自然との向き合い方や子育てにも通じることの多い、レイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』から選んだ名言になります。
もしもわたしが、すべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力をもっているとしたら、世界中の子どもに、生涯消えることのない「センス・オブ・ワンダー = 神秘さや不思議さに目を見はる感性」を授けてほしいとたのむでしょう。
出典 : レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』
自然界には、様々な驚きがあり、その驚きを発見し、神秘や不思議さを受け取る感性が、センス・オブ・ワンダーです。
この感性を持つことによって、大人になったら見舞われる倦怠や幻滅などへの、将来に渡る「解毒剤」になるとレイチェル・カーソンは言います。
子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激にみちあふれています。残念なことに、わたしたちの多くは大人になるまえに澄みきった洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直感力を鈍らせ、あるときはまったく失ってしまいます。
出典 : レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』
子供たちの世界の美しさは、いずれ大人になると失われてしまうかもしれません。
しかし、だからこそ、なおさら、子供の頃を、自然への感受性を養う期間にしてほしい、と伝えたいのでしょう。
そんなレイチェル・カーソンの想いは、次に紹介する、少し長めの文章でも現れています。
「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。
子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生みだす種子だとしたら、さまざまな情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。
幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。
そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実をうのみにさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることのほうがどんなにたいせつであるかわかりません。
出典 : レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』
重要なのは、「知る」ことよりも、「感じる」ことだと彼女は言います。
この感受性が、その後、「知っていく」ことへの土壌となる。それゆえに、子供の頃は、こうした感受性の土壌を耕すことが大切なのでしょう。
この土壌なしでは、知っていくことは単なる頭で覚えるだけになってしまうということなのだと思います。
自然のいちばん繊細な手仕事は、小さなもののなかに見られます。雪の結晶のひとひらを虫めがねでのぞいたことのある人なら、だれでも知っているでしょう。
出典 : レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』
自然界には、驚くような美しさも溢れていますが、小さなもののなかに見られる繊細さには、いっそう驚嘆します。
その代表的なものとして、レイチェル・カーソンは、雪の結晶を挙げています。
草花でも、蝶々でも、その一つ一つが極めて繊細で、周りには多くの奇跡が溢れていることを知ります。
地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学的であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう。
出典 : レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』
自然への「センス・オブ・ワンダー」を持っていたら、大人になり、本当に孤独なときであっても、ふと外を見て、いつも寄り添ってくれる存在に気づくことができるでしょう。
以上が、レイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』の名言です。
『沈黙の春』の名言
続いて、代表作の『沈黙の春』から選出した名言も紹介します。『沈黙の春』では、より自然との繋がりや環境問題と密接に繋がっている言葉になります。
生物が土壌を形成したばかりでなく、信じられないくらいたくさんのさまざまな生物が、すみついている。もしも、そうでなければ、土は不毛となり死にはててしまう。無数の生物がうごめいていればこそ、大地はいつも緑の衣でおおわれている。
出典 : レイチェル・カーソン『沈黙の春』
土壌というのは、ただの機械ではなく、その場所に棲む無数の生物たちのうごめきによって保たれ、生きたものとなっています。
ただ、単体で存在しているわけではなく、様々な生き物たちによって調和していることで健全性が保たれていると言えるでしょう。
自然の均衡とは、不変の状態ではない。流動的で、時と場合に応じて有為転変していく。人間もまたその一部で、そのおかげをこうむることもあるが、また逆に──それも大抵人間が差し出がましいことをするために、手痛い目にあうときもある。
出典 : レイチェル・カーソン『沈黙の春』
この言葉は、分子生物学者の福岡伸一さんの「動的平衡」という考え方に通じるものがあるでしょう。
自然界は、決して不変なものではなく、移り変わりながら、全体としてある種のバランスを保っている。その一部に人間もいる。
このバランス(調和と言ってもいいかもしれません)を、人間の手によって差し出がましく崩そうとすることで、結果的に痛い目に遭うことがあるとレイチェル・カーソンは言います。

人間のからだの神秘にみちた動きに少しでも目を向けてみれば、原因と結果が単純につながっていて、原因から結果へと直接たどれることは滅多にないのがわかる。原因と結果は、空間的にも時間的にもかけはなれている。
出典 : レイチェル・カーソン『沈黙の春』
自然だけでなく、体もまた自然の一部であり、その神秘性に目を向ければ、「こうなったから、ああなった」と単純に原因と結果が繋がっているとは言えません。
古くからの様々な原因が蓄積し、たとえば「病」のようなものが結果として生じることもあり、その場合、明確に「原因」を辿ることは難しくなります。
悲しみ一つ取っても、悲しみの「きっかけ」は最近の何々と言えても、ほんとうの深い部分の原因は簡単には言い切れないのではないでしょうか。
そんな風に、この世の多くのことが、単純な因果関係では結べない、と言えるかもしれません。
植物は、錯綜した生命の網の目の一つで、草木と土、草木同士、草木と動物とのあいだには、それぞれ切っても切りはなせないつながりがある。
出典 : レイチェル・カーソン『沈黙の春』
自然界は、草木も、動物も、それぞれが繋がり、関係性のなかで、一つの調和を保っています。
この調和を、むやみやたらに壊すことで、手痛いしっぺ返しが来ることを、レイチェル・カーソンは繰り返し指摘します。
その考え方自体は、決して今も古びたものではないでしょう。
以上、レイチェル・カーソンの『センス・オブ・ワンダー』と『沈黙の春』の名言でした。