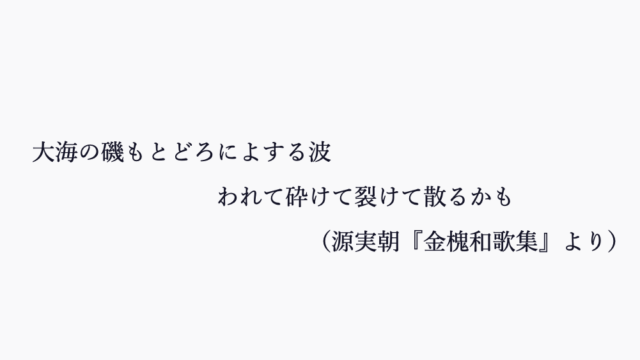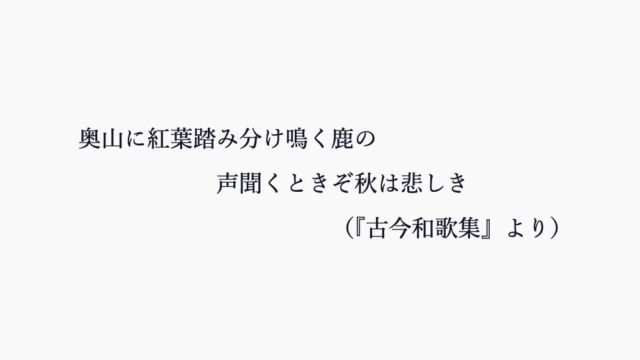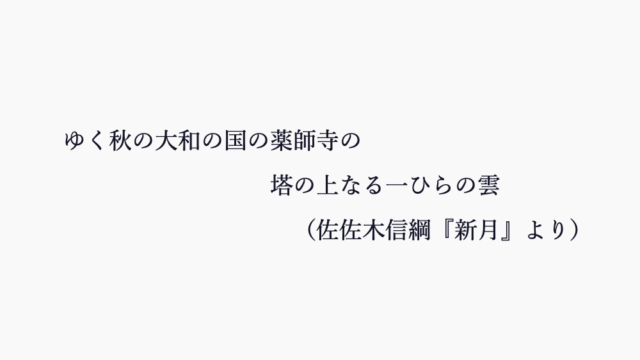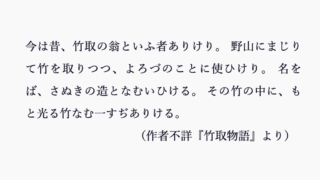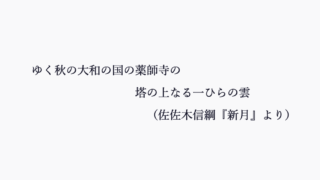ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聞きにゆく〜意味と現代語訳〜
〈原文〉
ふるさとの訛なつかし
停車場の人ごみの中に
そを聞きにゆく
〈現代語訳〉
故郷の訛りが懐かしい、停車場の人ごみのなかに、その訛りを聞きにゆく
概要と解説
作者の石川啄木は、本名石川一と言い、明治19年(1886年)、岩手県に生まれた夭折の歌人です。
中学時代、文芸誌の『明星』に掲載されている与謝野晶子らの短歌や、学校の上級生らの影響から、文学の道を志すようになります。しかし、カンニングや成績の悪さを理由に、17歳で盛岡中学を退学。
その後、上京し、『明星』に詩や短歌を発表。石川啄木というペンネームも、この頃から使うようになります。
石川啄木は、1905年、盛岡にいた頃から恋愛が続いていた堀合節子と結婚。
1906年、故郷の渋民村で代用教員となるも、翌年には北海道に移り、職を転々と変えたあと、再び上京。1910年、歌集『一握の砂』を発表します。
この「ふるさとの訛なつかし/停車場の人ごみの中に/そを聞きにゆく」という短歌も、『一握の砂』に入っている、石川啄木の望郷の思いを詠んだ代表作です。
停車場とは、駅を意味し、懐かしい故郷の訛りである東北弁を求め、駅の人ごみのなかにそれ(「そ」は「それ」を意味します)を聞きにゆく、という歌です。
この歌で描かれる「停車場」というのは、東北の人も多く利用する、東京の上野駅だと一般的には考えられています。
上野駅には、東北から上京してきた人、帰郷する人たちがいることから、ここへ行けば、故郷の方言を聞くことができる、ということでしょう。
ふるさとというのは、この短歌の場合、啄木の出身地である岩手県を指しているのかもしれませんが、読み手によって、それぞれの故郷が想像できるでしょう。
故郷から、東京に出てくると、孤独な思いにさいなまれ、当時は今のような通信手段も発展していませんから、その孤独さはいっそう大きかったのではないでしょうか。
そのとき、地元の言葉を話す訛りが懐かしく、訛りが溢れる停車場に向かう、という心情が描かれています。
ちなみに、この石川啄木の作品に影響を受けた短歌として、同じく東北地方である青森出身の詩人、寺山修司の「ふるさとの訛なくせし友といてモカ珈琲はかくまでにがし」があります。
この歌は、現代語訳すれば、「ふるさとの訛りのなくなった友だちといて、モカコーヒーを飲むとこんなにも苦い」といった意味になります。
寺山修司が、大学入学で上京したあとに詠んだ歌で、ふるさとの訛りをもう使わず、言ってみれば都会に染まった友人と、「モカ珈琲」を飲む。
この「モカ珈琲」とすることで、背伸びのニュアンスも込められ、その居心地の悪さや辛さ、不愉快さ、心淋しさ、といったものが、「にがし」という形で表現されているのでしょう。
石川啄木は、1886年生まれで、1912年に26歳で亡くなる一方、寺山修司は、1935年生まれで、1983年に47歳で亡くなる、といった時代の違いも、両者の歌の差に反映されているのかもしれません。
ちなみに、上野駅の15番線ホーム付近には、この石川啄木の歌の歌碑もあります。
以上、石川啄木の「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聞きにゆく」の意味と解説でした。