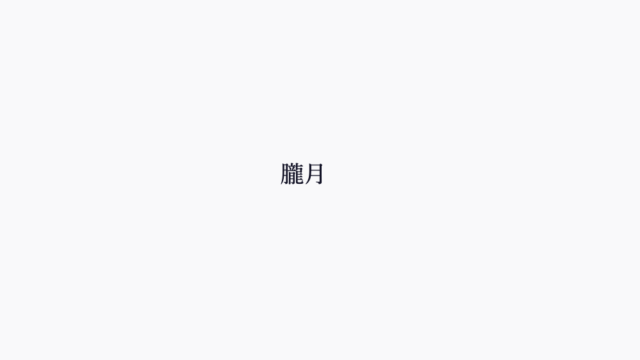「敵に塩を送る」の意味と由来
日本の故事ことわざに、「敵に塩を送る」という有名な言葉があります。
一見すると、「敵に塩を送る」という光景が具体的にイメージできず、意味が分からないかもしれません。
この「敵に塩を送る」とは、「敵の弱みにつけこまず、逆にその苦境から救うこと」を意味します。
それでは、一体なぜ敵に塩を送ることが、こうした意味を生むようになったのでしょうか。
この言葉は、戦国時代、上杉謙信と武田信玄のあいだに起こったとされる逸話に由来します。
 上杉謙信の肖像画
上杉謙信の肖像画
現在の山梨県である甲斐を中心に治めていた戦国武将の武田信玄は、領地が山に囲まれ、海に面していません。しかし、塩は人の命でもあるので、塩を手に入れる際には、東海地方から取り入れていました。
ところが、東海方面への進出を企てた武田信玄は、駿河国及び相模国との甲相駿三国同盟を破棄します。
この動きに対し、東海地方を領地とする今川氏真が、縁故関係にあった相模の北条氏康と相談し、武田領への塩の販売を禁止します。
塩が手に入らないことは死活問題、困った武田信玄に対し、敵対関係にあった越後(現在の新潟)の上杉謙信から手紙が届きます。
上杉謙信曰く、「争う所は弓箭に在りて、米塩に在らず(我々の争いは、武力の争いであって、米や塩の争いではない)」とのこと。
弱みに付け込んで姑息な手を使うべきではないと考えた上杉謙信は、商人たちに命じ、「公正な価格」で武田信玄の領地に塩を販売させることにします。
武田信玄も、上杉謙信に感謝の意を表し、一振りの太刀を送ります。この太刀は「塩留めの太刀」と呼ばれ、東京国立博物館に現存しています。
この戦国時代の二人の武将の「塩」にまつわる逸話に由来し、「敵に塩を送る」ということわざに繋がっていきます。
現在では、「敵に塩を送る結果となった」「敵に塩を送ることにならないか」など、「苦しんでいる相手を救うようなことはしないほうがいい」という意味合いで使われることも多い言葉です。
ところで、この「敵に塩を送る」の由来となった逸話は嘘ではないか、という声もあります。
ただ、それはあくまで「無償で送った」という話ではなく、「適正な価格で販売した」「流通を止めなかった」という話が真実ということのようです。
塩送りの逸話は、江戸時代の近世から明治昭和の近代まで、どれも一貫して次の内容のようにされている。
「今川氏真と北条氏康が、武田信玄へ塩の輸出を禁止した。武田領の甲斐・信濃・上野の民衆は、これでとても困窮した。事態を聞いた謙信は、長年の宿敵である信玄に『わたしは弓矢で戦うことこそ本分だと思うので、塩留めには参加しない。だから、いくらでも越後から輸入するといい。わたしからは、決して高値にしないよう商人に厳命しておく』と手紙を送った。これを聞いた信玄とその重臣たちは『味方に欲しい大将よ』と感嘆した」
一読してわかるように、謙信は無償で塩を大量に送ってはいないのだ。また逆に高値で売りつけたりもしてもいない。それどころか、定価を改めさせないとも伝えている。そして、この決して値段を変えさせないという謙信のスタンスは、どの編纂史料でも一致している。
ただし、この逸話が出てくるのは100年以上経ったあとの『謙信公御年譜』であり、この文献は脚色も多いことから、確かに史料には存在するものの、「敵に塩を送る」という話も必ずしも史実とは言えない、という話が通説となっています。
以上のように、敵に塩を送る、という言葉は、日本の故事に由来することわざなので、同じ表現の英語はありません。
もし、英語に翻訳する場合は、「help an enemy in difficulty」や「show humanity to an enemy」などが意味合いとして適切です。
ちなみに、これは余談ですが、響きの似たことわざに、「傷口に塩を塗る」という言葉もありますが、「敵に塩を送る」とは全く意味が違います。
傷口に塩を塗るとは、傷口に塩を塗ると染みていっそう痛みが強くなることに由来し、「悪いことの上に、さらに災難や悪いことが重なること」を意味します。
他に、傷口に塩を塗ると似た意味のことわざとして、「泣きっ面に蜂」や「弱り目に祟り目」などもありますが、「傷口に塩を塗る」が能動的な言葉であるのに対し、こちらは受動的な意味合いと言えるでしょう。