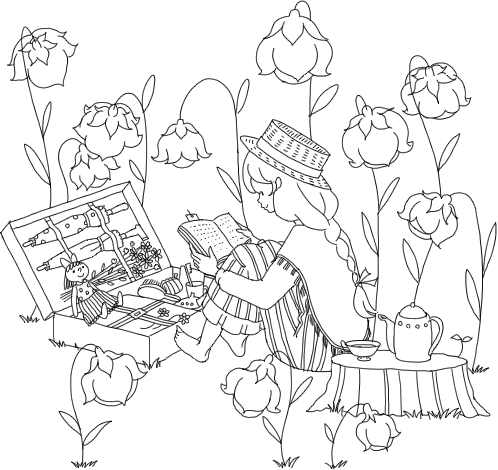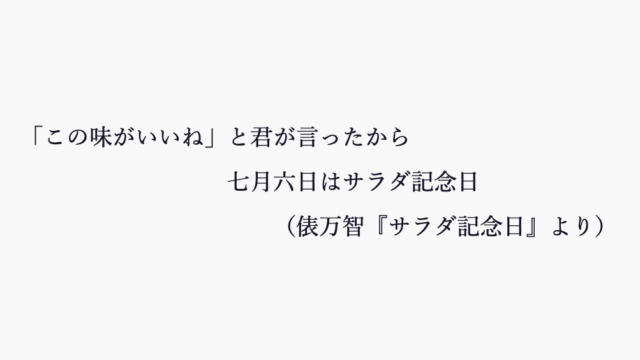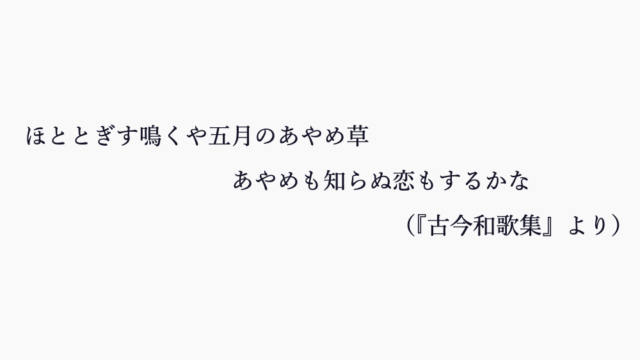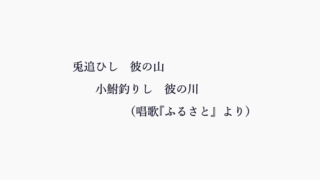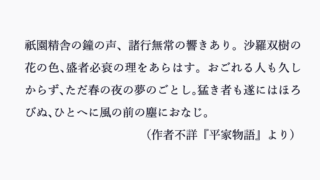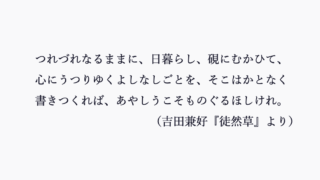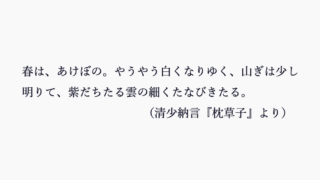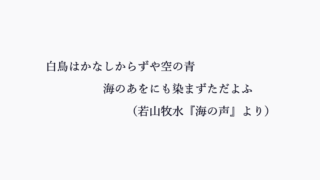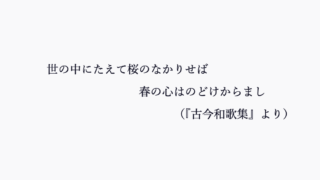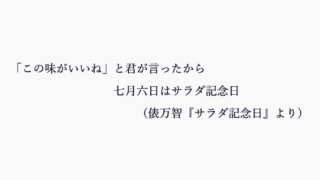わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕べかも〜意味と現代語訳〜
〈原文〉
わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕べかも
〈現代語訳〉
私の家の小さな竹の茂みに吹いている風の今にも消えそうなほどかすかな(竹の葉の擦れ合う)音が聞こえる、夕方であることよ。
概要
 画像 : 大伴家持(狩野探幽『三十六歌仙額』)
画像 : 大伴家持(狩野探幽『三十六歌仙額』)
作者の大伴家持は、万葉後期を代表する奈良時代の公卿、歌人です。大納言の大伴旅人の子供で、三十六歌仙の一人です。
大伴家持が生まれたのは718年(養老2年)と言われ、大伴氏の跡取りとして必要な教養を学びます。家持は、758年(天平宝字2年)、現在の鳥取県東部の因幡国の国守に赴任します。国守とは、その地の政務全般を統括する長官を指します。
国守に赴任した翌年の元日、後に『万葉集』の最後を飾ることとなる、「新しき年の始の初春の今日降る雪のいや重け吉事」という和歌を詠みます。
没年は785年で、家持は68歳でした。
その大伴家持の最大の業績と考えられているのが、現存する最古の歌集である『万葉集』の編纂です。
家持が編纂に関わったとされる理由として、『万葉集』に含まれる家持の歌の数の多さが挙げられます。
一体、何首の家持の歌が、『万葉集』に入っていたのでしょうか。その数は、長歌、短歌を合わせて473首で、『万葉集』の歌数が全部で4516首なので、全体の1割以上が家持の歌ということになります。これは万葉歌人のなかでも一位の数です。
大伴家持は、まさに『万葉集』における代表的な歌人の一人と言えるでしょう。
その家持の和歌のなかで「春愁三首」「絶唱三首」として知られている三首のうちの一首が、先に挙げた、『万葉集』収録の歌、「わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕べかも」です。
この「春愁」というのは、「春の日に、なんとなく気がふさぎ、物憂げな気持ちになること」を意味します。
春愁三首は、この「わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕べかも」に加え、「春の野に霞たなびきうら悲しこの夕かげにうぐひす鳴くも」「うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば」の三首になります。
・わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕べかも
・春の野に霞たなびきうら悲しこの夕かげにうぐひす鳴くも
・うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば
ただし、春愁三首が大伴家持の代表作として評価されるようになったのは、家持の死後1000年以上の時を経た、大正時代になってからのことでした。
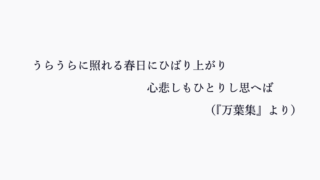
さて、この「わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕べかも」という春の物憂げで少し寂しげな情景を詠んだ歌は、現代語訳すると、「私の家の小さな竹の茂みに吹いている風の今にも消えそうなほどかすかな(竹の葉の擦れ合う)音の聞こえる、この夕方であることよ。」となります。
冒頭の「宿」というのは、「家」のことを指し、「いささ」とは、「少しばかりの」という意味です。現代でも、いささか、といった使い方をします。
最後の「かも」は、詠嘆の終助詞で、「〜だなぁ」「〜ことよ」という意味になります。
我が家の庭に少しばかりの群がって生えている竹があり、その竹に吹く風の音(これは風とともに、その風によって、さらさらと音を立てて揺れている竹の葉の擦れ合う音のことでしょう)が聞こえる、夕方であることよ、と情景を歌います。
このときの「音」というのは、どういった音だったのでしょうか。
直後に、「かそけき」とあります。これは漢字で表記すると「幽けき」で、「かそけし」の連体形であり、「今にも消えてしまいそうなほど、薄く、淡く、ほのかなさま」を意味します。
春の夕暮れどき、庭から聞こえてくる、ささやかな、今にも消えてしまいそうな、風に揺れて擦れ合う竹の葉の音。
言葉のリズムとしても、「わが宿のいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕べかも」と「の」が続き、風が吹き抜けていくような表現となっていて、夕暮れどき、葉擦れの音が静かに響いてくる様が、しみじみと伝わってきます。