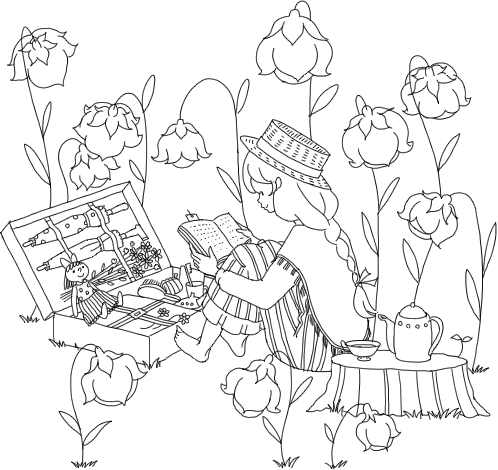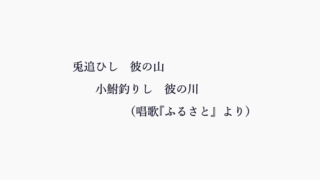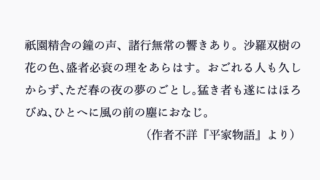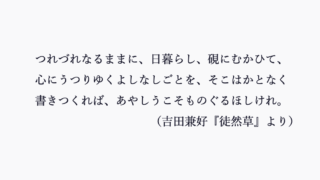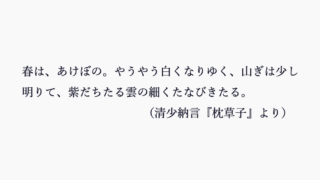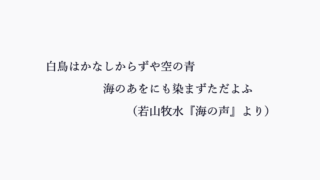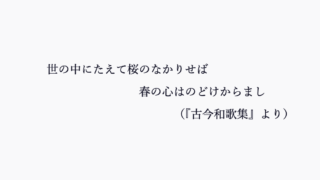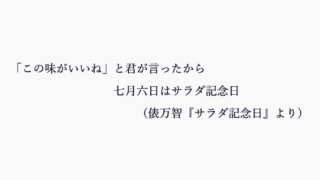モネ『印象・日の出』

クロード・モネ『ベレー帽の自画像』 1886年
クロード・モネは、印象派を代表するフランスの画家で、1840年にパリで生まれ、1926年に86歳で亡くなります。
パリで生まれたモネは、5年後、両親と兄とともにノルマンディー地方の港町ル・アーヴルに移り住み、少年時代のほとんどを、この地で過ごします。
海辺の散歩が好きだったモネは、学生時代、勉強は苦手だったものの絵が上手で、15歳の頃には、カリカチュア(風刺画)を描き、その絵を地元の文房具兼額縁屋さんに置いてもらっては小遣い稼ぎをします。
また、18歳の頃には、ひと回り以上年上の地元の風景画家ブーダンと出会い、戸外の油絵制作を教わります。
印象派やモネの絵画の主な特徴の一つとして、戸外制作による光がありますが、モネに戸外制作の素晴らしさを教えたのが、このブーダンでした。

まだ戸外で制作することが珍しかった時代、ブーダンは、1840年代にチューブ入り絵の具が開発された影響もあり、戸外制作を行う画家として、北フランスの海辺の風景を描き続けた画家で、偶然出会った、まだ若いモネを戸外に連れ出し、油彩画を勧めることになります。
モネにとっては、このブーダンの影響はとても大きく、最初の師として、晩年になっても、「自分が画家になれたのも、ブーダンのおかげだ」と語っています。
 ウジェーヌ・ブーダン『ベルクの海岸』 1878年
ウジェーヌ・ブーダン『ベルクの海岸』 1878年
大人になり、サロンという伝統的な価値観からははみ出した存在として、「印象派」という独立した、後々、美術史に残る芸術的流派の中心人物となったモネ。
まさに、印象派のなかでも、もっとも印象派らしい画家の一人が、クロード・モネと言えるでしょう。
数多くの印象派の絵画の名作を残し、特に『睡蓮』や『積みわら』の連作、そして、「印象派」という名前の由来となった『印象・日の出」などが、モネの代表作として知られています。
 クロード・モネ『印象・日の出』 1872年
クロード・モネ『印象・日の出』 1872年
この『印象・日の出』は、1872年に制作された絵画で、サイズは48cm×63cm。1874年に開催され、のちに「第一回印象派展」と呼ばれることになるグループ展に出品された、印象派の発端と言える作品でもあります。
タイトルは、英語では、(原題はフランス語)『Impression, Sunrise』となります(もともとは『日の出』のみだったものの、展覧会前に、地味さを指摘され、「印象」を付け足します)。
モネは、1872年に、故郷であるフランス北西部のル・アーブルを訪れた際、ル・アーブル港を描いた作品づくりを開始します。
ル・アーブル港の「夜明け」や「昼」「暗闇」など、違った時間帯や場所から描き、この『印象・日の出』も、モネのル・アーブル港の風景を描いたシリーズの一つです。
霞みがかった港の風景と、ぼんやりと浮かんでいる赤い日の出。手前には、人や舟の小さな影も描かれています。
フランスは、1970年 – 71年の普仏戦争の敗戦からの復興のさなかであり、また産業革命によって新しい時代へ移り変わっていく象徴として、この港と日の出の光景を描いたのではないか、と指摘する解説もあります。
印象派と言えば、今でこそ、美術の世界では欠かせない誰もが知っている存在となっていますが、当初は、若い少数の画家たちによる異端の活動で、伝統的な価値観を重んじる人たちから、激しく批判されます。
グループ展でモネの『印象・日の出』を見た、批評家のルイ・ルロワは、このグループ展に関する皮肉混じりの批判の文章を新聞紙『ル・シャリヴァリ』に投稿し、その記事のタイトルを、「The Exhibition of the Impressionists(印象主義の展覧会)」とします。
ルイ・ルロワは、ジョゼフ・ヴァンサン(架空と思われるアカデミズムの画家)とグループ展に訪れ、その感想を語り合う、という体で、この展覧会や出品作品を論評します。
その一幕として、『印象・日の出』を評したシーンが、次の文章内で描かれています。
「ああ、彼だ、彼!」ヴァンサンは、98番の作品の前で叫んだ。「彼がいた。ヴァンサン父さんのお気に入り! あのキャンバスは何を描いたものかね? カタログを見てくれ。」
「『印象・日の出』です。」
「『印象』、そうだと思った。私は印象を受けたので、作品に何かの印象があるに違いないと思っていたところだった……何という自由さ、何というお手軽な出来栄え! 出来かけの壁紙の方があの海景画より仕上がっている。」
当時の美的な価値観からすると、モネの絵を筆頭に、この展示会の画家たちの絵は、しっかりと完成されていない、未完成な絵だとされます。
印象を、さらっと描いただけのスケッチのようなもの、という捉え方でした。
そして、このときに使った未熟さや雑さを『印象・日の出』というタイトルと絡めて皮肉った、「印象」という批判的な言葉が世間に広まり、その後、評価が高まっていくにつれ、「印象派」「印象主義」という新しい芸術運動の旗印となっていきます。
そのため、この作品が、「印象派」の由来となった、と言われることとなります。