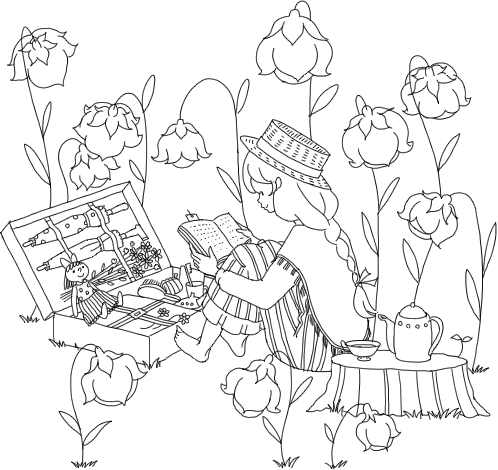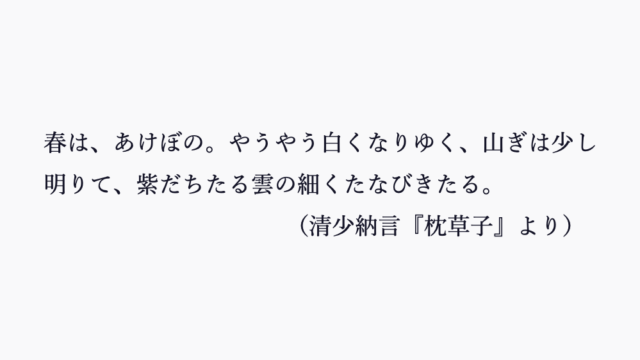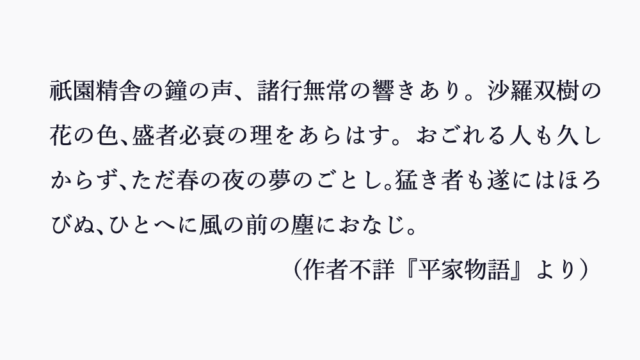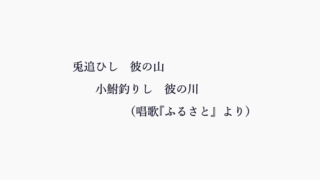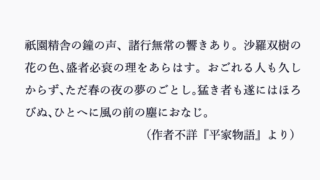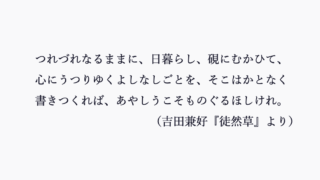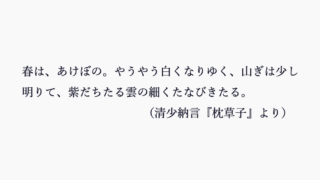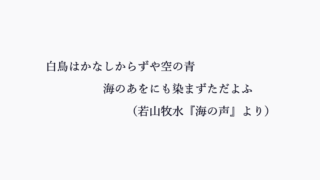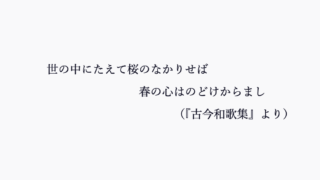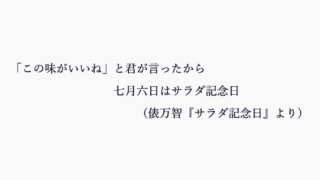百人一首の現代語訳一覧
百人一首とは
 百人一首とは、一般的に『小倉百人一首』と呼ばれ、飛鳥時代から鎌倉時代までの百人の歌人の和歌を、藤原定家という鎌倉時代の歌人が、一人につき一首ずつ選んでまとめたものです。
百人一首とは、一般的に『小倉百人一首』と呼ばれ、飛鳥時代から鎌倉時代までの百人の歌人の和歌を、藤原定家という鎌倉時代の歌人が、一人につき一首ずつ選んでまとめたものです。
鎌倉時代初期、公家で優れた歌人でもあった藤原定家は、京都小倉山の山荘で百人一首を編纂します。
この場所の名前に由来し、『小倉百人一首』と呼ばれるようになります。
百人一首が成立した正確な年代は不明ですが、13世紀前半だと推定されています。
成立当初、『小倉百人一首』に一定の呼び名はなく、「小倉山荘色紙和歌」「嵯峨山荘色紙和歌」「小倉色紙」などと呼ばれ、その後、小倉百人一首という呼び名が定着します。
もともと、親戚の宇都宮頼綱から、嵯峨中院の山荘の障子に貼る「色紙和歌」の執筆を依頼され、定家が各人一首の和歌を選んで書いたことから、この色紙和歌が、百人一首の起源と考えられています。
また、百人一首とほぼ同じ構成で、藤原定家の秀歌撰として『百人秀歌』もあります。
百人一首と百人秀歌は、内容はほぼ一緒で、97首の歌が一致していますが、多少選ばれた歌人や配列に違いが見られます。
どちらが先に作られ、元になっているかという点については、両方の説があり、現在も定まっていません。
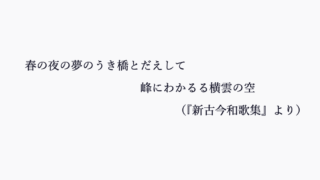
百人一首は、その後、かるたとしても普及し、広く庶民に浸透していきます。
お正月の風物詩や、学校の行事などで、百人一首のかるたで遊んだという人も少なくないのではないでしょうか。
もともと「貝合わせ」というハマグリの殻を使った遊びが平安時代にあり、その後、宮廷の人々のあいだで、貝に歌や絵を描いて遊ぶ「歌貝」が生まれます。
歌貝とは、ハマグリの貝殻の両片に、一首の和歌の上の句と下の句を分けて書き、かるたのようにして取り合う遊びです。
百人一首かるたの起源として、日本に古くからあるこの「貝合わせ」や「歌貝」に加え、戦国時代にスペインやポルトガルなどヨーロッパ文化が流入し、伝わったカードゲーム(carta : ポルトガル語で、四角い紙でできたものを意味する)も挙げられ、両者が融合して、いわゆる百人一首のかるたに繋がっていきます(参照 : 百人一首や花札など、かるたってどうやってできたの?)。
かるた取りが広がったのは江戸時代の頃、百人一首の歌かるたも、江戸時代から明治にかけ、庶民のあいだで広がり、浸透していきます。
以下、小倉百人一首の和歌より、原文や現代語訳、用語の意味や簡単な解説の一覧(前半の五十首)を紹介したいと思います。

原文一覧のあとに、現代語訳や意味の解説を掲載しています。
現代語訳は、歌の雰囲気が分かりやすいように、多少意訳となっています。頭の数字が和歌番号で、その後が、作者名と、生没年です。
1.秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ (天智天皇)
2.春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 (持統天皇)
3.あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む (柿本人麻呂)
4.田子の浦に うち出でて見れば 白妙の 富士の高嶺に 雪はふりつつ (山部赤人)
5.奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき (猿丸大夫)
6.かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける (中納言家持)
7.天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも (安倍仲麿)
8.わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり (喜撰法師)
9.花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに (小野小町)
10.これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも あふ坂の関 (蟬丸)
11.わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ あまのつり舟 (参議篁)
12.天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ (僧正遍昭)
13.つくばねの 峰より落つる みなの川 こひぞつもりて 淵となりぬる (陽成院)
14.陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに (河原左大臣)
15.君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ (光孝天皇)
16.立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む (中納言行平)
17.ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは (在原業平朝臣)
18.住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路 人めよくらむ (藤原敏行朝臣)
19.難波潟 みじかき葦の ふしの間も あはでこの世を 過ぐしてよとや (伊勢)
20.わびぬれば 今はた同じ 難波なる みをつくしても あはむとぞ思ふ (元良親王)
21.今こむと 言ひしばかりに 長月の 有明の月を 待ちいでつるかな (素性法師)
22.吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐といふらむ (文屋康秀)
23.月みれば 千々に物こそ 悲しけれ 我が身ひとつの 秋にはあらねど (大江千里)
24.このたびは ぬさもとりあへず 手向山 紅葉のにしき 神のまにまに (菅家)
25.名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな (三条右大臣)
26.小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ (貞信公)
27.みかの原 わきて流るる いづみ川 いつみきとてか 恋しかるらむ (中納言兼輔)
28.山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人めも草も かれぬと思へば (源宗于朝臣)
29.心あてに 折らばや折らむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花 (凡河内躬恒)
30.ありあけの つれなく見えし 別れより 暁ばかり 憂きものはなし (壬生忠岑)
31.朝ぼらけ ありあけの月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪 (坂上是則)
32.山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ 紅葉なりけり (春道列樹)
33.ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ (紀友則)
34.誰をかも 知る人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに (藤原興風)
35.人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香に匂ひける (紀貫之)
36.夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月やどるらむ (清原深養父)
37.白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける (文屋朝康)
38.忘らるる 身をば思はず 誓ひてし 人のいのちの 惜しくもあるかな (右近)
39.浅茅生の 小野の篠原 しのぶれど あまりてなどか 人の恋しき (参議等)
40.しのぶれど 色に出でにけり わが恋は 物や思ふと 人の問ふまで (平兼盛)
41.恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひ初めしか (壬生忠見)
42.契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは (清原元輔)
43.あひ見ての のちの心に くらぶれば 昔は物を 思はざりけり (権中納言敦忠)
44.あふことの たえてしなくは なかなかに 人をも身をも 恨みざらまし (中納言朝忠)
45.あはれとも いふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな (謙徳公)
46.由良のとを 渡る舟人 かぢを絶え ゆくへも知らぬ 恋の道かな (曾禰好忠)
47.八重むぐら しげれる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋は来にけり (恵慶法師)
48.風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ くだけて物を 思ふころかな (源重之)
49.みかきもり 衛士のたく火の 夜は燃え 昼は消えつつ 物をこそ思へ (大中臣能宣)
50.君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな (藤原義孝)
51.かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしも知らじな もゆる思ひを (藤原実方朝臣)
52.明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな (藤原道信朝臣)
53.嘆きつつ ひとり寝る夜の 明くるまは いかに久しき ものとかは知る (右大将道綱母)
54.忘れじの 行く末までは かたければ 今日をかぎりの 命ともがな (儀同三司母)
55.滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ (大納言公任)
56.あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな (和泉式部)
57.めぐりあひて 見しやそれとも 分かぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな (紫式部)
58.ありま山 ゐなの笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする (大弐三位)
59.やすらはで 寝なましものを さ夜更けて かたぶくまでの 月を見しかな (赤染衛門)
60.大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず 天の橋立 (小式部内侍)
61.いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな (伊勢大輔)
62.夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ (清少納言)
63.今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを 人づてならで 言ふよしもがな (左京大夫道雅)
64.朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木 (権中納言定頼)
65.恨みわび ほさぬ袖だに あるものを 恋にくちなむ 名こそ惜しけれ (相模)
66.もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに 知る人もなし (前大僧正行尊)
67.春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ (周防内侍)
68.心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな (三条院)
69.あらし吹く み室の山の もみぢ葉は 竜田の川の 錦なりけり (能因法師)
70.さびしさに 宿をたち出でて ながむれば いづこも同じ 秋の夕暮れ (良暹法師)
71.夕されば 門田の稲葉 おとづれて 葦のまろやに 秋風ぞ吹く (大納言経信)
72.音にきく たかしの浜の あだ波は かけじや袖の ぬれもこそすれ (祐子内親王家紀伊)
73.高砂の をのへの桜 咲きにけり 外山のかすみ 立たずもあらなむ (前中納言匡房)
74.憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを (源俊頼朝臣)
75.契りおきし させもが露を いのちにて あはれ今年の 秋もいぬめり (藤原基俊)
76.わたの原 こぎ出でてみれば 久方の 雲ゐにまがふ 冲つ白波 (法性寺入道前関白太政大臣)
77.瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ (崇徳院)
78.淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に 幾夜ねざめぬ 須磨の関守 (源兼昌)
79.秋風に たなびく雲の たえ間より もれ出づる月の かげのさやけさ (左京大夫顕輔)
80.長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れてけさは 物をこそ思へ (待賢門院堀河)
81.ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただありあけの 月ぞ残れる (後徳大寺左大臣)
82.思ひわび さてもいのちは あるものを 憂きにたへぬは 涙なりけり (道因法師)
83.世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる (皇太后宮大夫俊成)
84.ながらへば またこのごろや しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき (藤原清輔朝臣)
85.夜もすがら 物思ふころは 明けやらで 閨のひまさへ つれなかりけり (俊恵法師)
86.嘆けとて 月やは物を 思はする かこち顔なる わが涙かな (西行法師)
87.村雨の 露もまだひぬ まきの葉に 霧立ちのぼる 秋の夕暮れ (寂蓮法師)
88.難波江の 葦のかりねの ひとよゆゑ みをつくしてや 恋ひわたるべき (皇嘉門院別当)
89.玉のをよ たえなばたえね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする (式子内親王)
90.見せばやな 雄島のあまの 袖だにも 濡れにぞ濡れし 色は変はらず (殷富門院大輔)
91.きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに 衣かたしき ひとりかも寝む (後京極摂政前太政大臣)
92.わが袖は 潮干に見えぬ 沖の石の 人こそ知らね 乾くまもなし (二条院讃岐)
93.世の中は つねにもがもな 渚こぐ あまの小舟の 綱手かなしも (鎌倉右大臣)
94.み吉野の 山の秋風 さ夜ふけて ふるさと寒く 衣うつなり (参議雅経)
95.おほけなく うき世の民に おほふかな わが立つ杣に すみぞめの袖 (前大僧正慈円)
96.花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり (入道前太政大臣)
97.こぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くやもしほの 身もこがれつつ (権中納言定家)
98.風そよぐ ならの小川の 夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりける (従二位家隆)
99.人もをし 人も恨めし あぢきなく 世を思ふゆゑに 物思ふ身は (後鳥羽院)
100.百敷や ふるき軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり (順徳院)
百人一首の現代語訳
001 天智天皇 626〜671

〈原文〉
秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ
〈現代語訳〉
秋の田の傍にある粗末な仮小屋は、苫葺き屋根の目が粗いので、私の着物の袖は、隙間から漏れる冷たい夜露で濡らしてしまっているよ。
用語の意味
かりほ : 田を見守るための粗末な小屋 苫 : 菅・茅などで編んだ、こものようなもの。小屋や舟を覆って雨露をしのぐのに用いる 衣手 : 衣服の袖、転じて着物全体の意もある
百人一首の冒頭は、飛鳥時代の天皇である天智天皇の歌。収穫物を鳥獣から守るために、秋の田のそばの仮小屋に泊まり、その屋根の目が粗く、漏れる夜露で着物の袖が濡れている様子を描いた貧しい農民の苦労の歌です。
この歌は、正確には天智天皇の作品ではないと考えられ、『万葉集』の作者不明の歌が元歌となり、改変されて伝わり、天智天皇が農民を思いやって詠じた歌とされるようになります。
002 持統天皇 645〜702

〈原文〉
春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山
〈現代語訳〉
春が過ぎ去り、いつのまにか夏が来てしまったようだ。 香具山には、あんなにたくさんの真っ白な着物が干されているのだから。
用語の意味
けらし : けるらしの略、〜らしい、〜たようだ 白妙の 衣に掛かる言葉、楮や麻で織った白い衣のこと ほすてふ : 干すという 天の香具山 : 奈良県の山、大和三山の一つ
春が過ぎ、夏になると香具山で干されるという白い衣。その衣を眺めながら、ああ、夏が来たようだ、と思う、持統天皇が詠んだとされる歌です。奈良にある香具山には、天から降ってきたという伝説があり、神聖視されていることから、「天の」とつきます。
003 柿本人麻呂 生没年不詳(飛鳥・奈良時代)

〈原文〉
あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む
〈現代語訳〉
夜になると雄と雌が谷を隔てて別々に寝る山鳥の長く垂れ下がった尾のように、こんなにも長い長い夜を、私もまた、ひとり寂しく寝るのだろうか。
用語の意味
あしびき : 山鳥へ掛かる枕詞、古代には「あしひきの」だったが、後に「あしびきの」と濁らせるようになる 山鳥 : キジ科の鳥、独り寝を象徴する鳥として恋の歌によく詠まれた鳥 しだり尾 : 長く垂れ下がった尾羽
生没年不詳の万葉歌人である柿本人麻呂作とされる和歌で、夜になると、一羽一羽が谷を隔てて眠る山鳥のように、寂しく一人で眠ること。またその夜が、山鳥の尾っぽのように長い「秋の夜長」を詠んだ歌です。
004 山部赤人 生没年不詳(飛鳥・奈良時代)

〈原文〉
田子の浦にうち出でてみれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ
〈現代語訳〉
田子の浦の海岸に出てみると、雪をかぶった真っ白な富士の高嶺に雪が降っているよ。
用語の意味
田子の浦 : 静岡の蒲原の吹上の浜あたり 白妙の : 富士に掛かる枕詞 うち出でて : 視界の遮られた場所から、ひらけた場所に出て 降りつつ : 反復、継続を意味し、降り続けている、という様子を表す
作者の山部赤人は生没年不詳の奈良時代の歌人です。自然を詠んだ歌に優れ、歌聖と称されています。田子の浦というのは、現在の静岡県東部にある浜で、その浜から見える白い布のような雪をかぶった富士山の情景が描かれています。
005 猿丸大夫 生没年不詳(飛鳥・奈良時代)

〈原文〉
奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声聞くときぞ秋は悲しき
〈現代語訳〉
人里離れた奥深い山のなかで、地面に散り敷かれた紅葉を踏み分け、恋しい相手を求めて鳴く鹿の声を聞くとき、秋はなんとも物悲しく感じるものだ。
用語の意味
奥山 : 人里離れた山の奥 紅葉踏み分け ; 踏み分けている主語が、作者なのか鹿なのかは解釈が分かれる
歌の作者は、『古今和歌集』では、よみ人知らずだったものの、その後、猿丸大夫作とされるようになる、秋の悲しみを詠んだ歌です。秋は鹿にとって求愛の季節で、晩秋には、雄鹿が、雌鹿を求めて切なく鳴くとされ、人里離れた山奥で、敷き詰められた紅葉を踏み分け、鹿が鳴いているという哀愁の漂う光景が描かれています。猿丸大夫は、実在したかどうかも不明で、伝説上の歌人と考えられています。
006 中納言家持 718頃〜785

〈原文〉
鵲の渡せる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける
〈現代語訳〉
カササギが架け渡したという天の川の橋に散らばる、霜のように白く冴え冴えした星々を見ていると、夜もずいぶん更けたなぁと感じる。
用語の意味
鵲の渡せる橋 : 織姫と彦星が七夕の日に逢えるように、たくさんの鵲が翼を連ねて天の川に橋を作ったという伝説に由来 置く霜の白き : 霜は、散らばる星々を喩えたもの、霜が地上に降りることを、霜が置く、と表現する
作者は、奈良時代の公卿、歌人の大伴家持です。大納言、大伴旅人の子で、三十六歌仙の一人です。「かささぎの渡せる橋」とは、天の川のことです。夜空を見上げ、天の川に散らばっている霜のように冴え冴えとした星を見ていると、夜がすっかり更けたんだなぁ、と感じられる情景や心境を詠んだ歌です。
007 阿倍仲麿 701〜770

〈原文〉
天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも
〈現代語訳〉
大空を振り仰いで見ると、美しい月が見える、あの月は故郷の春日の三笠の山に出ていた月と同じ月だろうか。
用語の意味
天の原 : 大空 ふりさけ見れば : 漢字で書くと「振り放け」、振り放見るとは、振り仰いで遠くを眺めること
作者の阿倍仲麻呂は、奈良時代の遣唐使です。唐では官人として玄宗皇帝に仕えます。帰国の際、船が難破し、唐に戻り、結局最後まで日本に帰国することなく当地で生涯を終えます。この歌は、帰国する前に、仲麻呂のために海辺で宴が催され、夜空に浮かぶ美しい月を見ながら詠んだとされます。故郷の月を懐かしく思いながら、詠んだ歌なのかもしれません。ただ、帰国が叶わなかった仲麻呂の歌がなぜ伝わったのかは不明で、一説には、平安時代に別の誰かが詠んだ歌が、仲麻呂作として伝わったという話もあります。小倉百人一首では、「阿倍仲麿」と表記されます。
008 喜撰法師 生没年不詳(平安時代前期)

〈原文〉
わが庵は都の辰巳しかぞすむ世をうぢ山と人はいふなり
〈現代語訳〉
私の庵は都の東南にあり、このように心静かに住んでいる。それなのに、世間の人たちは、私が世を憂きものと思って宇治の山に住んでいると言っているそうだ。
用語の意味
辰巳 : 東南、宇治は京の都の東南にある しか : このように うぢ山 :「憂じ」と「宇治」の掛詞
作者の喜撰は、生没年不詳の平安時代初期の歌人で、六歌仙の一人です。法師とは、僧の総称です。もともと現在の京都である山城国に生まれ、出家したあとに、醍醐山、のち宇治山に隠れ、仙人となり、雲に乗って姿を消したと伝えられています。確かな伝記が残っていないことから、伝説的な歌人となっています。ただし、『古今集』の仮名序で、宇治山の僧喜撰とあり、9世紀中頃に生き、宇治山に隠棲していたことは確かだと考えられています。百人一首のこの和歌も、宇治山に隠棲していることについて、世間はあれこれと言っているようだ、という浮世離れした雰囲気が伝わってきます。宇治山は、この歌の影響で、喜撰山と呼ばれるようになります。
009 小野小町 生没年不詳(平安時代前期)

〈原文〉
花の色はうつりにけりないたづらに我身世にふるながめせし間に
〈現代語訳〉
美しかった花の色もすっかり色褪せてしまったなぁ、むなしく、降り続く長雨をぼんやりと眺めて物思いにふけっているうちに(私もまたこの世で年をとってしまった)。
用語の意味
花の色 : 様々な春の花の色、桜と解釈されることも多い うつりにけりな : 「うつる」は、花の色のことなので、色褪せる、衰えるといった意味、「な」は、感動の助動詞 いたづらに : むなしく、むだに ふる : 雨が「降る」と「古る(年月が経つ、年をとる)」の掛詞 ながめ :「長雨」と「眺め」の掛詞、眺めとは、ぼんやりと物思いにふけって眺めている状態
作者の小野小町は、六歌仙、三十六歌仙の一人で、生没年不詳(平安時代前期と考えられる)の女流歌人です。絶世の美女として言い伝えられ、出身については、現在の秋田県湯沢市小野という説がありますが、その他にも諸説あり、詳しいことは分かっていません。この歌は、長雨のために花の美しさにじゅうぶん浸れなかったという想いと同時に、ぼんやりと嘆きながら過ごしているうちに、美しかった自分の姿も年老いてしまった、という後悔の念や無常観が歌われています。
010 蝉丸 生没年不詳(平安時代前期)

〈原文〉
これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関
〈現代語訳〉
これだよ、これが、あの有名な、東国へ旅立っていく人も都へ帰る人も、ここで別れては、知っている人も知らない人も、またここで出会うという逢坂の関だよ。
用語の意味
これやこの :「や」は詠嘆の間投助詞、「この」は、あの有名な、という意味 逢坂の関 : 奈良時代に置かれた関所で、山城国(京都)と近江国(滋賀)との境に位置
作者の蝉丸は、生没年不詳で、平安時代前期の歌人です。盲目の琵琶の名手として様々な説話も残っていますが、詳細は分かっていません。蝉丸という名前は、蝉歌(蝉のような声を発する歌)の名手だったことに由来するという話もあります。また、蝉丸が僧であったかどうかも不明ですが、百人一首かるたでは、頭巾をかぶった僧の姿で描かれることも少なくありません。この和歌の出典となっている『後撰集』の詞書には、「逢ふ坂の関に庵室をつくりて住み侍りけるに、行き交ふ人を見て」とあり、逢坂の関のほとりに隠棲していたことが読み取れます。逢坂の関は、旅人たちが行き交う交通の要所で、この出会いと別れの場所を、俗世を眺める傍観者の位置から、無常観も込めて詠んだ歌と考えられます。蝉丸は、のちに神格化され、音楽や芸能の神さまとして祀られた神社もあります。
011 参議篁 802〜852

〈原文〉
わたのはら八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよ海人の釣り 船
〈現代語訳〉
大海原の多くの島々を目指して漕ぎ出していったと、都に残してきた人に告げてくれないか、漁師の釣り船よ。
用語の意味
わたのはら : 大海原 八十島 :「八十」は「多くの」という意味 かけて : 目指して 人 : 京都にいる人(家族や知人)
作者の参議篁は、本名を小野篁と言い、平安時代前期の漢詩人、歌人です。遣隋使として有名な小野妹子の子孫です。838年に遣唐副使となった際、出発に関するトラブルによる抗議のために篁は乗船を拒否、『西道謡』という風刺の詩をつくって批判します。詩の中身は散逸し、残っていませんが、この行為が嵯峨天皇の逆鱗に触れ、位階を剥奪、隠岐島に流されることになります。百人一首に選ばれているこの歌は、隠岐島に流されるときの船出の際に詠んだ歌です。『古今和歌集』では、詞書に、「隠岐国に流されけるときに、舟に乗りて出で立つとて、京なる人のもとに遣はしける」とあり、これは現代語訳すれば、「隠岐に流されたときに、舟に乗って出立する際、京にいる人のもとに送った」歌という意味です。流刑にあった篁は、二年ほどで赦免され、帰京し、活躍します。
012 僧正遍昭 816〜890

〈原文〉
天つ風雲の通ひ路吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ
〈現代語訳〉
空を吹く風よ、雲のなかにあるという天に通じる道を吹いて閉ざしておくれ、天に帰っていく乙女たちの姿を、もうしばらくここに留めておきたいのだよ。
用語の意味
天つ風 : 空を吹く風 雲の通ひ路 : 雲の切れ間から天上に通じる道 乙女 : 五節の舞姫のこと
作者の遍昭は、平安時代前期の僧であり、六歌仙の一人でもある歌人です。俗名は、良岑宗貞といいます。僧正とは、僧官の最上位を意味します。この歌は、遍昭が出家する前に、仁明天皇に仕えていた際、五節の舞の舞姫を天女に見立て詠んだ歌です。同じく仁明天皇に仕えていたとされる小野小町とは交流がありました。
013 陽成院 869〜949

〈原文〉
筑波嶺の峰より落つるみなの川恋ぞ積もりて淵となりぬる
〈現代語訳〉
筑波山の峰から流れ落ちる水無川の水が、積もり積もってやがては深い淵をつくるように、あなたへの恋心も積もり、今では淵のように深い想いとなった。
筑波嶺 : 筑波山のこと 峰 : 頂上、ひときわ高くなった所 みなの川 : 水無川、男女川とも書く、筑波山から桜川に注ぐ河川 淵 : 水の深いところ、川などのよどんだ所
作者の陽成院とは、陽成天皇のことです。この歌は、陽成天皇が若くして退位後に、父清和天皇のいとこにあたる綏子内親王に捧げた恋歌です。山から流れ落ちる水が深い川となるように、恋心も積もっていくことを比喩的に詠んだ歌です。この恋は成就し、二人は結婚します。
014 河原左大臣 822〜895

〈原文〉
陸奥のしのぶもぢずり誰ゆゑに乱れそめにし我ならなくに
〈現代語訳〉
奥州のしのぶ摺りの乱れ模様のように、いったい誰のために私の心も思い乱れ始めているのでしょう、私のせいではないのに(きっとあなたのせいですよ)。
用語の意味
陸奥 : 今の青森、岩手、宮城、福島と秋田の一部 しのぶもぢずり : シノブの茎や葉の色素を布にすりつけて表したねじれたような模様。また、そのすり模様の衣服。かつて陸奥国が産地だったと言われる 乱れそめにし :「そめ」は、「初め」と「染め」の掛詞で、「乱れ」とともに、「しのぶもぢずり」の縁語 我ならなくに : 私のせいではないのに、暗に「あなたのせいよ」と匂わせている
作者の河原左大臣とは、源融のことで、平安時代初期から前期にかけての貴族です。百人一首で河原左大臣と称されているのは、左大臣であったことと、河原院を造営したことに由来します。しのぶ(もじ)摺りという乱れ模様に摺った布に、自分の恋心を重ねた歌です。乱れ模様であることから、よく恋の心の乱れとして詠まれることの多い題材でもあります。この時代、しのぶもじ摺りは、東北地方の名産として宮廷に献上されていたと言われています。
015 光孝天皇 830〜887

〈原文〉
君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ
〈現代語訳〉
あなたのために春の野に出て若菜を摘んでいる、私の袖にちらちらと雪が降りかかっていることよ。
用語の意味
若菜 : 早春に萌え出る若草の総称、春の七草が有名 衣手 : 着物の袖
作者の光孝天皇は、第58代天皇で、文芸を愛し、温厚で謙虚な性格だったことから、信頼も厚く、聖代の天皇として後世仰がれることとなります。歌の季節は早春で、『古今和歌集』の詞書によれば、光孝天皇が皇太子時代に、誰かのために若菜を摘んで贈ったときの歌とあります。あなたのために若菜を摘んでいるときに、ちらちらと雪が降りかかっていた情景が描かれています。この相手というのは、恋人でなのか、あるいは、親交の深かった藤原基経なのか、と考えられています。
016 中納言行平 818〜893

〈原文〉
立ち別れいなばの山の峰に生ふるまつとし聞かば今帰り来む
〈現代語訳〉
あなたがたと別れ、因幡国へ行くけれども、稲葉山の峰に生えている松のように、私を待っていると聞いたなら、すぐにでも帰ってきましょう。
用語の意味
いなばの山 : 因幡(現在の鳥取の東半部)にある稲葉山のこと、往なば(行ってしまったなら)の掛詞 まつ :「松」と「待つ」の掛詞
作者の中納言行平こと在原行平とは、平安時代初期から前期の公卿で歌人です。百人一首で取り上げられているこの歌は、855年(斉衡2年)に因幡守となり、現在の鳥取県の因幡国に赴任するに当たり、京都を離れる際に見送りに来てくれた人々に贈った歌と考えられています。行平の異母弟に、同じく百人一首に歌が選ばれている在原業平がいます。
017 在原業平朝臣 825〜880
 狩野探幽『三十六歌仙額(在原業平)』
狩野探幽『三十六歌仙額(在原業平)』
〈原文〉
ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは
〈現代語訳〉
神々の時代にさえ聞いたことがない、こんな風に竜田川一面に紅葉が散り敷かれ、流れる水を真紅に絞り染めしているなどということは。
用語の意味
ちはやぶる :「神」にかかる枕詞 神代 : 神々が支配していたとされる、神武天皇即位以前の時代 竜田川 : 大和国(奈良県)の生駒郡を流れる川 からくれなゐ : 濃い紅色、唐や韓の国から渡来した紅という意味 水くくる : 水を絞り染め(くくり染め)にする、川面を布にたとえ、紅葉が散り敷かれている様を表現している
作者の在原業平は、天長2年(825年)に生まれ、元慶4年(880年)に死没する、平安時代初期から前期の貴族、歌人です。六歌仙、三十六歌仙の一人で、美男子としても知られ、『伊勢物語』の主人公は、業平がモデルだったと考えられています。この歌は、秋の竜田川を紅葉が流れていく様が描かれた屏風を前にして詠んだもので、『古今和歌集』の詞書に、「二条の后の春宮の御息所と申しける時に、御屏風に竜田川に紅葉流れたる形を描きけるを」とあります。これほど素晴らしく紅葉が敷き詰められた竜田川の光景は、神々の時代にも聞いたことはない、と屏風に描かれている大和絵を前に、半ば誇張したように驚きとともに表現します。

018 藤原敏行朝臣 〜901(または907)
〈原文〉
住の江の岸に寄る波よるさへや夢の通ひ路人目よくらむ
〈現代語訳〉
住の江の岸には波が寄るというのに、昼だけでなく夜の夢のなかの私のもとへと向かう通い路でさえ、あなたは人目をはばかって会ってはくれないのだろうか。
用語の意味
住の江 : 摂津国住吉(大阪府大阪市住吉区)の海岸 夢の通ひ路 : 夢のなかで恋人に会いに行く道 よるさへや :(昼ならまだしも)夜さえも 人目よくらむ : 人の目を避けるのだろう、「よく」は避ける、「らむ」は推量の助動詞
作者の藤原敏行は、平安時代前期の貴族、歌人、書家で、三十六歌仙の一人です。百人一首に選ばれたこの歌は、宇多天皇の母班子女王主催の歌合での一首です。平安時代の貴族たちにとって、夢に恋する人が多く出てくるほど、相手は自分のことが好きなのだと解釈され、この歌では、現実だけでなく夢のなかでも出てきてくれない、会いにきてくれない、という恋の不安を詠まれています。藤原敏行の歌では、「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる」という一首も有名です。
019 伊勢 生没年不詳
 狩野探幽『三十六歌仙額(伊勢)』
狩野探幽『三十六歌仙額(伊勢)』
〈原文〉
難波潟短かき葦のふしの間も逢はでこの世を過ぐしてよとや
〈現代語訳〉
難波潟の入り江に生えている葦の、短い節と節の間のようなほんの短い時間でさえお会いできないで、この世を過ごしていけとおっしゃるのでしょうか。
用語の意味
難波潟 : 大阪湾の入江部分 短き葦のふしの間 :「短かき」は、「ふしの間」にかかる 過ぐしてよとや : 一生を過ごしてしまえよとあなたはおっしゃるのでしょうか、という意味
作者の伊勢は、平安時代の女性歌人で、三十六歌仙の一人です。この恋愛にまつわる歌は、『伊勢集』の詞書によれば、心変わりしてつれなくなった恋人からの手紙に対する返歌です。このときの恋の相手については正確にはわかっていませんが、伊勢の最初の恋人で、身分違いの恋愛でもあった藤原仲平という説があります。葦の節と節のあいだのような短い時間さえ会えずに、この世を過ごしていけとおっしゃるのですか、と会えない恨みや想いが詰まった歌となっています。
020 元良親王 890〜943
〈原文〉
わびぬれば今はた同じ難波なる身をつくしても逢はむとぞ思ふ
〈現代語訳〉
これほどに辛く思い悩んでいるのなら、今はもはや破滅したも同然のこと。いっそ、あの難波の澪標のように、この身を滅ぼしてでもあなたに逢いたいと思う。
用語の意味
わびぬれば :「侘ぶ」は、思い悩む、つらく思う 今はた同じ :「はた」とは、「やはり同じ」という意味 難波なる : 難波にある、今の大阪 身をつくし :「澪標」は、船に水脈を知らせるために立てた標識のことで、破滅することを意味する「身を尽くし」との掛詞
作者の元良親王とは、平安時代前期から中期にかけての皇族、歌人で、陽成天皇の息子です。百人一首に選ばれているこの歌は、許されない相手との恋が世間に知られたあとに、相手に贈った歌です。大阪湾に立っている澪標(船に水脈を知らせるための標識)と「身を尽くし」を掛け、身を滅ぼしてもいいから逢いたいという想いを詠んでいます。
021 素性法師 生没年不詳(平安時代前期)
〈原文〉
今来むと言ひしばかりに長月の有明の月を待ち出でつるかな
〈現代語訳〉
あなたが、「今すぐに行きましょう」とおっしゃったので、九月の長い夜を待っていたのに、とうとう有明の月の出を待ち明かしてしまいましたよ。
用語の意味
長月 : 陰暦の九月 言ひしばかりに : 言ったばかり 有明の月 : 陰暦二十日以降の月のこと、夜明けまで空に残っている 待ち出でつるかな :「待ち出づ」は「待っていて出会う」という意味、「つる」は完了の助動詞、「かな」は詠嘆の終助詞
022 文屋康秀 生没年不詳(平安時代前期)
〈原文〉
吹くからに秋の草木のしをるればむべ山風をあらしといふらむ
〈現代語訳〉
山から秋風が吹き下ろすと、たちまち秋の草や木が萎れるので、なるほど、だから山風のことを「荒らし」、すなわち「嵐」というのだろう。
用語の意味
〜からに :「〜やいなや」「〜とすぐに」 むべ : なるほど
023 大江千里 生没年不詳
〈原文〉
月見れば千々に物こそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど
〈現代語訳〉
秋の月を眺めていると、様々に物事が悲しく感じられる、私一人のために訪れた秋ではないのだけれども。
用語の意味
千々に : あれこれと、様々に わが身ひとつの : 私一人だけの
024 菅家 845〜903
〈原文〉
このたびは幣も取りあへず手向山紅葉の錦神のまにまに
〈現代語訳〉
この度の旅は急なことだったので、捧げる幣を用意しておりません。手向山の神様よ、この山の錦のような美しい紅葉を幣として捧げますので、どうかお心のままにお受け取り下さい。
用語の意味
このたび :「この度」と「この旅」の掛詞 幣 : 神に祈るときに捧げ、また祓いに使う、紙や麻などを切って垂らしたもの、贈り物 取りあへず : 用意する暇がなく 手向山 : 神に手向けると、手向山(山城国から大和国へ向かう途中の奈良山)を掛けている 神のまにまに : 神の御心のままに
025 三条右大臣 873〜932
〈原文〉
名にし負はば逢坂山のさねかづら人に知られでくるよしもがな
〈現代語訳〉
逢坂山の小寝葛が、「逢う」「さ寝」というその名の通りであるなら、逢坂山のさねかずらを手繰り寄せるように、誰にも知られずあなたのもとを訪ねて行く手立てがあればいいのに。
用語の意味
名にし負はば : 〜という名前を持つ 逢坂山 : 山城国(現在の京都)と近江国(現在の滋賀)のあいだにある山、関所があった。「逢ふ」との掛詞 さねかづら : つる性の植物、男女が一緒に寝る「小寝」との掛詞 知られで : 知られないで もがな : 〜したい、〜であればよい
026 貞信公 880〜949
〈原文〉
小倉山峰のもみぢ葉心あらば今ひとたびのみゆき待たなむ
〈現代語訳〉
小倉山の峰の美しい紅葉の葉よ、もしお前に哀れむ心があるならば、もう一度天皇の行幸があるので、散るのを急がずに待っていてくれないか。
用語の意味
小倉山 : 京都市右京区嵯峨にある紅葉の美しい名所、大堰川を隔てた対岸に嵐山があり、麓に定家の別荘、「小倉山荘」があった 心あらば : 人間の情があるならば みゆき : 天皇が御所から外出すること、「行幸」と書き、上皇、法皇、女院の場合は区別して「御幸」と書く 待たなむ :「〜なむ」は願望を表す終助詞
027 中納言兼輔 877〜933
 狩野尚信『三十六歌仙額(藤原兼輔)』
狩野尚信『三十六歌仙額(藤原兼輔)』
〈原文〉
みかの原わきて流るるいづみ川いつ見きとてか恋しかるらむ
〈現代語訳〉
みかの原から湧き出て、かき分けるようにして流れる泉川、その「いつ」という言葉ではないが、いつ逢ったといって、(一度も逢ったことがないのに)こんなにも恋しくなってしまうのだろうか。
用語の意味
みかの原 : 京都府相楽郡を流れる木津川の北側の一部、「瓶原」と書く わきて :「湧きて」と「分きて」の掛詞、「湧き」は、流るるとともに「川」の縁語 いづみ川 : 現在の木津川 いつ見きとてか : 「き」は過去の助動詞、「か」は疑問の係助詞、「いつ逢ったというのだろうか」、「見る」は古語で男女が関係を結ぶことも意味する 恋しかるらむ : 「らむ」は推量の助動詞
028 源宗于朝臣 〜939
〈原文〉
山里は冬ぞ寂しさまさりける人目も草もかれぬと思へば
〈現代語訳〉
山里は、冬こそとりわけ寂しさがつのるものだ、人も訪れることがなくなり、草も枯れてしまうのだと思うと。
用語の意味
山里は : 係助詞の「は」は、他との区別を強調、「(都ではなく)山里は」 まさりける :「まさる」は「増す」「つのる」という意味 かれぬ : 「かれ」は、「離れ」と「枯れ」が掛かる
029 凡河内躬恒 生没年不詳
〈原文〉
心あてに折らばや折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花
〈現代語訳〉
もし折るならば当てずっぽうに折ってみようか、真っ白な初霜が降り、霜と白菊の花と見分けがつかなくなっているのだから。
用語の意味
心あてに : 心をこめて、当てずっぽうに、など 折らばや折らむ : もし折るというなら折ってみようか 置きまどはせる : 初霜が降り(置き)、紛らわしくさせる
030 壬生忠岑 平安時代中期
〈原文〉
有明のつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし
〈現代語訳〉
有明の月は冷淡に見え、あなたもその有明の月のようにそっけないもので、あなたと別れて以来、夜明け前の月ほど憂鬱なものはありません。
用語の意味
有明 : 有明の月のこと、夜が明けても残っている月 つれなく : 冷淡に 暁ばかり :「暁」とは、夜明け前のまだ暗いうち、当時、男が女のところから帰っていく時間帯でもある、「ばかり」とは、「〜なし」と合わせ、「ほど〜なものはない」という意味
031 坂上是則 平安時代中期
〈原文〉
朝ぼらけ有明の月と見るまでに吉野の里に降れる白雪
〈現代語訳〉
夜が明け始める頃、まるで有明の月かと思うほどに、吉野の里に降っている白雪よ。
用語の意味
朝ぼらけ : 夜が明けてきて、うっすらと辺りが見える頃、秋冬と結びつくことが多い言葉 有明の月 : 夜明けの空に残って、明るく光っている月 吉野の里 : 大和国(現在の奈良県吉野郡)吉野の辺り
032 春道列樹 ?〜920
〈原文〉
山川に風のかけたるしがらみは流れもあへぬ紅葉なりけり
〈現代語訳〉
山のなかの川に、風がかけた流れ止めの柵は、流れきれずにいる紅葉だったのだ。
用語の意味
山川 : 山のなかを流れる川 しがらみ : 川の流れをせき止める柵、杭を打ち並べ、それに木の枝や竹を横たえたもの あへぬ : あふの打ち消しで、〜しきれない、という意味
033 紀友則 ?〜905
〈原文〉
久方の光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ
〈現代語訳〉
日の光が降り注いでいるのどかな春の日に、どうして落着いた心もなく、桜の花は散っていくのだろうか。
用語の意味
ひさかたの : 光、天、空、月、雲、雨などに掛かる枕詞 光のどけき : 日の光ののどかな、穏やかな しづ心 : 静心、落ち着いた心 花 : 桜の花のこと 〜らむ : 推量の助動詞で、「どうして〜だろう」という意味
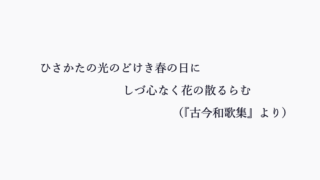
034 藤原興風 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに
〈現代語訳〉
年老いた私は(友人たちももう亡くなり)、一体誰を親友にすればよいのだろうか。長寿の高砂の松でさえ、昔からの友ではないのだから。
用語の意味
知る人にせむ : 親しい友人としよう 高砂の松 : 高砂は播磨国加古郡高砂(現在の兵庫県高砂市南部)の浜辺、松の名所として知られる 昔の友ならなくに : 昔からの友ではないのに
035 紀貫之 868〜945
〈原文〉
人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける
〈現代語訳〉
あなたの心はどうでしょうかね、人の心は分かりませんが、昔馴染みのこの里では、梅の花はかつてのように今もよい香りで匂っていますよ。
用語の意味
人はいさ : ここで「人」は、あなたである宿の女主人のこと、「いさ」とは、さあ、どうでしょうか、という意味 ふるさと : 昔馴染みの土地という意味、この歌では、旧都の奈良を指す 花 : 普通桜を指すが、ここでは梅の花を意味する
036 清原深養父 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづこに月宿るらむ
〈現代語訳〉
夏の夜は短く、まだ宵だと思っているうちに明けてしまったが、西の山陰に行き着くことのできなかった月は、一体雲のどの辺りに宿をとっているのだろうか。
用語の意味
夏の夜は : 「は」と、夏の夜が他の季節と比較し、短いことを強調している 宵 : 日暮れまもなく 月宿るらむ : 月を人間に見立てた擬人法、「らむ」は推量
037 文屋朝康 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
白露に風の吹きしく秋の野はつらぬきとめぬ玉ぞ散りける
〈現代語訳〉
草葉の上の白露に風がしきりに吹きつけている秋の野は、まるで糸を通していない真珠の玉が、美しく散り乱れているようだ。
用語の意味
白露 : 草の上に光っている水滴 吹きしく : 「しく」は漢字で「頻く」と書き、「しきりに〜する」、風の吹きしくで、「しきりに風が吹いている」という意味 つらぬきとめぬ : 真珠の玉は普通糸を通して、留めているも、この歌では留めていないので、風が吹いてばらばらに散る
038 右近 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しくもあるかな
〈現代語訳〉
あなたに忘れ去られる我が身のことは何ほどのことも思いません。ただ、私を愛すると神に誓ったあなたの命が、神の罰を受けないかと惜しまれてなりません。
用語の意味
身 : 自分自身のこと 誓いてし : 「て」は完了の助動詞「つ」の連用形、「私を愛すると神に誓った」 人 : あなたのこと
039 参議等 880〜951
〈原文〉
浅茅生の小野の篠原しのぶれどあまりてなどか人の恋しき
〈現代語訳〉
茅の生えた寂しく忍ぶ小野の篠原の「しの」のように、あなたへの思いを忍んでいるものの、もはや忍びきることはできず、どうしてこのようにあなたが恋しいのだろうか。
用語の意味
浅茅生の : 浅茅とは、まばらに生えている茅のこと、生は、生えている場所を意味する 小野の : 小は、調子を整える接頭語、野原のこと 篠原 : 篠竹の生えている原っぱのこと 忍ぶれど : 我慢すれども あまりて : 忍ぶ心を我慢しきれないで などか : どうして
040 平兼盛 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
忍ぶれど色に出でにけりわが恋は物や思ふと人の問ふまで
〈現代語訳〉
知られまいと恋しい思いを隠していたが、隠しきれずに態度に表れてしまったようだ、私の恋は。「恋をしているのでは」と人が尋ねるほどまでに。
用語の意味
忍ぶれど :「忍ぶ」は、こらえるという意味、人に知られまいと秘密にしてきたけれど 色 : 表情のこと、「色に出づ」で恋心が表情に出ること けり : 感動の助動詞で、今気づいた驚きを表す 物や思ふ :「物思ふ」は、恋について思い煩うこと、「や」は、疑問の係助詞 人 : 第三者、他人
041 壬生忠見 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
恋すてふわが名はまだき立ちにけり人知れずこそ思ひそめしか
〈現代語訳〉
恋をしているという私の噂が、もう世間の人たちのあいだに広まってしまったようだ。人知れず、密かに思いはじめたばかりなのに。
用語の意味
てふ : といふ 名 : 世間の噂や評判 まだき :「早くも」という意味 けり : 今初めて気づいたという感動や驚きを表す助動詞 思いそめしか :「思い初め」と書き、「恋がまだ始まったばかり」という意味、「しか」は過去の助動詞「き」の已然形で、係助詞「こそ」のあとに続くと、「〜けれども」という意味になる
042 清原元輔 908〜990
〈原文〉
契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波こさじとは
〈現代語訳〉
約束をしましたよね、お互いに涙で濡れた袖をしぼりながら、波があの末の松山を決して越すことがないように、私たちの愛も決して変わらないと。
用語の意味
契りきな :「契る」とは、約束する、という意味、「き」は体験過去の助動詞、「な」は感動を表す終助詞 かたみに : お互いに 袖をしぼり : 涙で濡れた袖を絞るというニュアンスから、泣き濡れる、ということ 末の松山 : 現在の宮城県多賀城市周辺 波こさじ : 波越さじ、「じ」は打ち消しの推量、意志を表す助動詞、末の松山はどんな高い波でも越せないということから、永遠を意味し、「私の愛が決して変わらないこと」を表す
043 権中納言敦忠 906〜943
〈原文〉
逢ひ見ての後の心にくらぶれば昔は物を思はざりけり
〈現代語訳〉
あなたに逢って愛し合った後の恋しい気持ちと比べると、逢いたいと思っていた昔の恋心の苦しみなどは無いと同じようなものだったなぁ。
044 中納言朝忠 910〜966
〈原文〉
逢ふことの絶えてしなくばなかなかに人をも身をも恨みざらまし
〈現代語訳〉
あなたと一度も結ばれていないなら、あなたの冷たさも、自分の不幸も、こんなに恨むことはなかっただろうに。
045 謙徳公 924〜972
〈原文〉
哀れともいふべき人は思ほえで身のいたづらになりぬべきかな
〈現代語訳〉
私を哀れだと慰めてくれる人がいるようにも思えず、私はただ、あなたを恋しく思いながら虚しく死んでいくのでしょう。
046 曽禰好忠 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
由良の門を渡る舟人かぢを絶えゆくへも知らぬ恋の道かな
〈現代語訳〉
由良の門を渡る船人が、梶をなくして、どこへ漕いでいったらいいのか行方が分からないように、これからどうすればいいのか途方に暮れる恋の道だよ。
047 恵慶法師 生没年不詳(平安時代中期)
〈原文〉
八重むぐらしげれる宿のさびしきに人こそ見えね秋は来にけり
〈現代語訳〉
幾重にも雑草の生い茂ったこの家は寂しく、誰も訪ねてはこないが、ここにも秋だけは確かに訪れるようだ。
048 源重之 ?〜1000頃
〈原文〉
風をいたみ岩うつ波のおのれのみくだけて物を思ふころかな
〈現代語訳〉
風が激しく、岩に打ち当たる波が(岩はなんともないのに)自分だけが砕け散ってしまうように、(あなたは平気で)私だけが心も砕けるように恋の思いに悩んでいるこの頃よ。
049 大中臣能宣朝臣 921〜991
〈原文〉
みかきもり衛士のたく火の夜はもえ昼は消えつつ物をこそ思へ
〈現代語訳〉
宮中の御門を守る御垣守である衛士の燃やすかがり火が、夜に赤々と燃え、昼は消えているように、私の心も夜は情熱に燃え、昼は消え入るように物思いにふけり、日々恋に悩んでいる。
050 藤原義孝 954〜974
〈原文〉
君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな
〈現代語訳〉
あなたに逢えるなら惜しいとも思わなかった命ですが、こうしてあなたと逢瀬が叶った今では、長く生きていたいと思うようになりました。